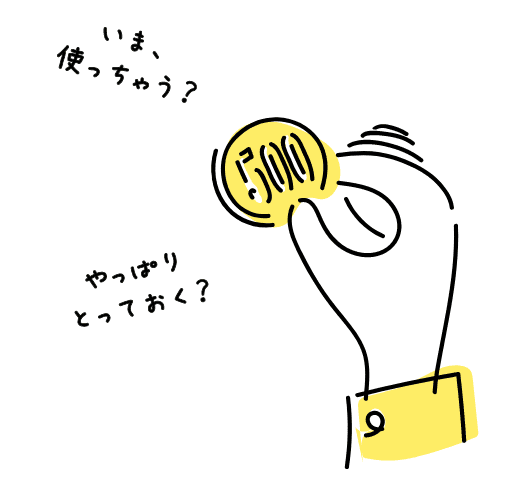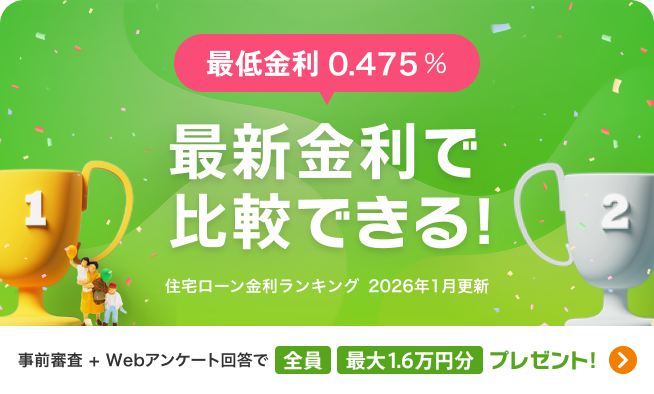高市政権の発足で住宅ローン金利は上がる?物価・賃上げが家計に与える影響を読み解く
2025年10月21日、第104代内閣総理大臣に高市早苗氏が任命されました。新総理には外国人政策や国防といった観点で期待が集まっていますが、国民の多くは物価高に代表される経済政策の方向性にも注目しています。特に住宅ローンの利用を検討している人にとっては、「今後の金利見込み」や「借りるタイミングはいつがいいか」は気になる情報ではないでしょうか。 高市政権は、物価上昇と賃上げを伴う「成長重視」の政策を打ち出していますが、その裏で大規模な財政出動による国債発行が増えれば、長期金利の上昇につながる可能性も指摘されています。そこで、今回は高市政権の経済政策が住宅ローンにどう関係してくるかをわかりやすく整理し、これからマイホーム購入を考える人が知っておきたいポイントを紹介します。
01高市政権、成長重視の「積極財政」へ。住宅ローンの金利にどう影響する?
高市政権の経済政策における大きな特徴は「景気を良くするために、積極的にお金を使うこと」です。具体的には公共投資や社会保障などに資金を投入し、物価や給料の上昇を目指すことで消費・投資マインドを引き上げて経済の好循環を生み出そうとしています。
一方で、資金を投入するには財源が必要です。財源確保には大きく分けて「税率を上げる(新しい税制度を設ける)」もしくは「国の借金である国債を発行する」の2つがありますが、前者だと個人の手取りが減ってしまい消費マインドが下がる恐れがあるため、高市政権は後者を選ぶと予想されています。
国債の発行額が増えると一般的に長期金利が上がる傾向にあることから、それに連動しやすい住宅ローンの固定金利も上昇し、返済コスト増につながるかもしれません。そのため、これから住宅ローンを利用する人は、日銀の金融政策の動向にも注目しておくほうがよいでしょう。
2025年10月に開催された金融政策決定会合で、日銀は政策金利を現状の0.5%のまま据え置きました。これは2025年3月から6会合連続の決定で、アメリカの関税政策や新総理誕生直後の日本の経済政策など、不透明な要素を慎重に判断した結果のようです。ただし、日本の物価上昇圧力は依然として強く、長期金利の上昇余地が高まっているといった植田日銀総裁の発言もあり、年内の利上げにも含みを持たせています。
以上のことから、これから住宅ローンを借りる人は「政策金利が当面低くても、将来の長期金利上昇リスクを織り込んでおくこと」が重要です。高市政権の家計を温めるための政策が、結果的に住宅ローンの利用コスト上昇につながる可能性も十分考えられます。
02高市政権下で固定金利に上昇圧力、変動金利は低水準が続く見通し
先述のように、住宅ローンの固定金利は国が発行する国債の金利(長期金利)の影響を受けやすい特徴があります。この長期金利は近年、上昇傾向にあり、2025年11月20日には一時17年半ぶりに1.8%まで上がりました。
長期金利のこうした動きの背景には、「これから国がたくさんお金を使うのではないか」という財政拡大への期待や不安があるからです。高市政権が掲げる「積極的にお金を使って景気を良くする」という方針も、そうした市場心理に影響を与えています。
長期金利上昇がすぐに住宅ローンに結びつくわけではありませんが、今後の政府と日銀の金融・財政政策次第で固定金利がじわじわと上がる可能性が高くなっています。特に日銀と政府が「物価上昇率2%超えを容認した経済成長戦略」を続ければ円安・インフレが定着し、固定金利の一層の上昇につながりかねません。
一方、変動金利は日銀の政策金利に連動する短期金利が基準となっています。2025年10月の金融政策決定会合で日銀は政策金利の現状維持を決めたため、現在の水準を維持する見通しです。近いうちにインフレ抑制などを目的に日銀が政策金利を引き上げる恐れはあるものの、経済にダメージを与える可能性もあるので、急激な利上げはあまり考えられない状況です。
以上のことから、これから住宅ローンを借りる人は「当面は変動金利で様子を見つつ、将来の繰り上げ返済や借り換えを視野に入れる」という姿勢を心掛けるとよいでしょう。中には、「変動金利が上がったら固定金利に切り替える」と考えている人もいるかもしれませんが、変動金利が上がり始めたころには固定金利のほうがすでに上がっていることが多いため、そのような判断はあまり現実的ではありません。低金利のうちに元本を減らしておき、将来の金利上昇局面で家計への負担を少しでも抑えることを優先する考え方も選択肢の1つです。
03物価上昇と賃上げで「実質負担」はどう変わる?
それでは高市政権が目指す、デフレ脱却を目標に掲げた「物価と給料が一緒に上がる経済」において、家計の実質負担はどのように変わるのでしょうか。
結論からいうと、経済政策が上手くいけばインフレで物価が上がっても家計が楽になる可能性があります。なぜなら、仮に物価が毎年2%上がっていても、収入も同じ、もしくはそれ以上に増えていけば住宅ローン返済の「実感としての負担」は軽くなるからです。ただし、経済政策が上手くいかず、物価だけが上がって給料が変わらなければ家計への圧迫感は増し、日々の生活を苦しく感じる人が増えるでしょう。
そのため、住宅ローンの返済計画を考える際は「金利の数字」だけでなく、「実際の暮らしにどれだけ余裕があるか」で考えることも大切です。仮に住宅ローン金利が1.5%で「金利が高い」と感じても、給料が毎年2%ずつ上がっていけば、家計にそれほど大きなダメージは受けないでしょう。
また、このように物価や給料が上がる環境が続けば、相対的にお金の価値は下がる(100円の物が120円になると、1円の価値は下がる)ので、名目上は同じ返済金額であっても、住宅ローンで返すお金の価値は徐々に小さくなっていきます。
インフレが続く日本で住宅ローンを借りるときは、「金利や住宅価格」といった数字に一喜一憂することなく、将来的な給料や物価を含めた「暮らし全体のバランス」で考えることが重要だといえます。
04これから住宅ローンの借り入れを検討中の人が意識したい3つの視点
高市政権下では、物価と給料が同時に上昇する経済を目指しており、今後の結果次第では住宅ローンの“実質負担”が変わる可能性があります。ここからは、これから住宅ローンを組む人が押さえておきたいポイント3つを紹介していきます。
返済に余裕を持つ
まず、意識しておきたいのは「金利上昇リスク」です。高市政権は経済成長と賃上げを後押しする姿勢を打ち出していますが、それは国債発行額の増加やインフレ進行によって金利上昇につながるリスクも抱えています。そのため、住宅ローンの借り入れ時は「将来的に金利が上がっても返せる余裕を持つこと」が何より重要になるでしょう。
一般的に住宅ローンの返済に余裕があるとされる返済額(返済比率)は、年収の25~30%以内です。たとえば、年収500万円の家庭は毎月の返済額10万円前後が目安(返済比率24%)になります。これなら金利が0.5%上昇しても返済額の増加は毎月7000円程度ですむため、少しぐらい金利が上がっても家計への大きなダメージにはなりにくいでしょう。
「繰り上げ返済」や「借り換え」を選択肢に入れる
2つ目は、「政策や金利の変化に合わせて見直せる設計にしておくこと」です。高市政権の経済政策は景気を押し上げる一方、長期金利はもちろん将来的には短期金利の上昇にも影響を及ぼす可能性があります。そのため、住宅ローンは「借りたら終わり」ではなく、今後の金利動向を見据えて、柔軟に返済計画を見直していくことが大切です。
ただし、見直すときは住宅ローン減税の適用が終わるタイミングに注意してください。住宅ローン減税は一定条件を満たすことで新築の種類のよって10年間もしくは13年間、住宅ローンの残債に応じて所得税や住民税の減税を受けられる制度です。早い段階で繰り上げ返済をするとあまり節税効果を得られないうえ、控除期間が終わったあとは優遇が受けられなくなり、実際の支出負担が大きく感じられることがあります。
たとえば、夫婦共働きで世帯年収600万円、借入金額3500万円(35年返済)の場合、金利0.6%なら毎月の返済額はおよそ8万9000円ですが、仮に金利が0.5%上がって1.1%になると、毎月の返済額は8000円増の約9万7000円(年間では約10万円もの負担増)です。このケースで住宅ローン減税適用後の11年目に50万円を繰り上げ返済(期間短縮型)すると、将来支払う利息が減ることで総返済額を約60万円減らせる可能性があります。
繰り上げ返済のタイミングは支払利息軽減効果を考慮することが大切です。控除期間が終わった後であれば、早く繰り上げ返済を行うことで住宅ローン減税の恩恵を最大限に受けながら、最終的な支払利息を抑える効果が期待できます。そのため、住宅ローン減税の適用期間終了後を目安に、将来の繰り上げ返済や借り換えを視野に入れた返済計画を立てておくことをおすすめします。
「固定金利」か「変動金利」かは、生活の安定度で選ぶ
3つ目は「金利タイプの選び方」です。金利タイプには主に固定金利と変動金利の2つがありますが、どちらにも一長一短があります。そのため、「どちらが得か」よりも「どちらが安心か」という視点で考えるのがおすすめです。
仮に安定した収入が見込める共働き家庭であれば、低金利が続くうちは変動金利で家計負担を抑え、金利が上がったときの繰り上げ返済の資金を貯めておくのもよいでしょう。一方、ボーナスなどの収入が不安定で将来的に子どもの教育費が増える見込みがあるなど、毎月の家計のやりくりが心配な家庭ほど固定金利で返済額を一定にしておくほうが安心です。
たとえば、借入金額4000万円で35年の住宅ローンを組んだ場合、変動金利0.5%なら月々の返済額は約10万4000円ですが、固定金利2.0%なら月々の返済額は約13万2000円になります。固定金利のほうが総返済額は約400万円多くなるものの、仮に金利が上がっても返済額は変わらないので、あらかじめ予算の範囲内で購入すれば計画的な返済を続けていけるでしょう。
変動金利と固定金利のどちらが適しているかは人それぞれの状況によって異なりますが、一般的には「家計に多少の変動を許容できる人」は前者、「返済額の安定を重視する人」は後者を選ぶのが基本です。
05家計の“耐久力”で乗り切る住宅ローン戦略を立てよう!
高市政権は発足したばかりでもあり、経済政策の方向性はまだ十分に見通せない部分もあります。しかし、これまでの言動からインフレ抑制よりも経済刺激策が中心になるとみられていて、中長期的には金利上昇につながりやすい環境が続く可能性があります。そのため、これから住宅ローンを組む人に求められるのは「金利が上がる・下がる」を当てることではなく、どんな状況でも返せる“家計の耐久力”を知ることです。
「住宅ローンは政策の影響を受けるけれど、最終的にコントロールできるのは自分の家計」といった意識を持ち、「金利が変化した場合の返済額」や「収入が変わったときの家計」といった複数の条件でシミュレーションしてみましょう。当サイト内の住宅ローンシミュレーターでは、年収やローン期間、金利タイプなどを入力するだけで「毎月の返済額」「借入可能額」「将来の返済負担」などを簡単に確認できます。現在、住宅購入を検討している方は、ぜひ試してみてください。

監修:新井智美
CFP®/1級ファイナンシャル・プランニング技能士
プロフィール
トータルマネーコンサルタントとして個人向け相談の他、資産運用など上記相談内容にまつわるセミナー講師を行う傍ら、年間100件以上の執筆・監修業務を手掛けている。
関連キーワード