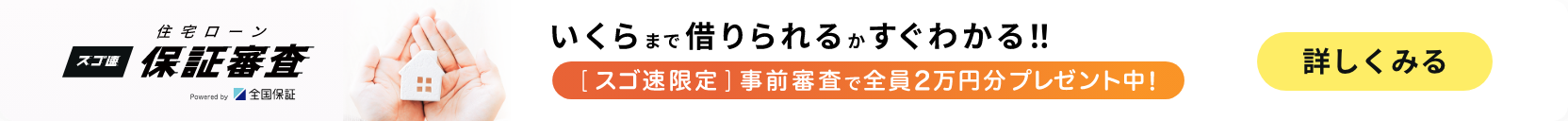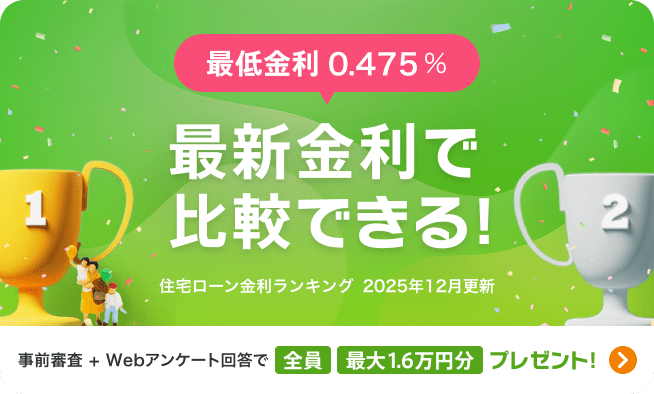【2025年】住宅ローンに影響あり!地価2.7%上昇の最新路線価と借入前の注意点を解説
2025年7月1日、国税庁から最新の令和7年分路線価が発表されました。路線価とは、「地価の目安」となるもので、今回は全国平均で2.7%の上昇となっています。これにより、全国の地価は4年連続で上がったことになります。 地価が上がると、住宅ローンを組む際に審査対象となる土地の「担保評価額」も高くなります。その結果、金融機関から評価される金額が増え、希望する借入額に届くかもしれません。一方で、固定資産税や相続税、贈与税といった各種の税負担が増える可能性もあるため、注意が必要です。 この記事では、令和7年分路線価を基に、これから家を買おうと思っている人にどんな影響があるかを分かりやすく解説します。
- 01「路線価」とは?なぜ毎年ニュースになるの?
- 02令和7年の最新路線価、どの地点がどれくらい上昇した?
- 03路線価が上がると、住宅ローンが借りやすくなる?
- 04路線価が上がると税金もアップ?“見えないコスト”に要注意!
- 固定資産税が高くなることも
- 路線価の上昇で相続税・贈与税も増える!?
- 05これから住宅ローンを借りる人への5つのアドバイス
- 自分が買いたい土地の路線価をチェックする
- 金融機関の担保評価をもとに、借入可能額を試算してみる
- 金融機関に「最新の路線価で審査してください」と伝える
- 返済負担が増えないように、金利タイプも慎重に選ぶ
- 税金の増加リスクも含めて「維持できるか」を考える
- 06住宅ローン選びで後悔しないために、まず「借りられる金額」と「返せる金額」をシミュレーションしよう
01「路線価」とは?なぜ毎年ニュースになるの?
「路線価(ろせんか)」とは、路線(道路)に面する標準的な宅地の1㎡当たりの価額※のことです。国税庁が毎年7月に発表しており、これを基に相続税や贈与税などの税金が計算されます。路線価は、その年の1月1日時点の地価水準を基にして決められます。
「なんだか専門的で難しそう…」と思うかもしれませんが、路線価は私たちの生活にも身近に存在しています。例えば住宅を買うにあたって住宅ローンを組む場合、購入する住宅を担保にして金融機関からお金を借りることがあります。そのとき、金融機関は「この住宅における土地部分はいくらくらいの価値があるか」を路線価などから判断し、融資金額を決めます。
また、親から土地を相続したり、贈与を受けたりする際にも、路線価は重要です。相続税や贈与税は、この路線価をもとに計算されるため、税額に大きく関係するからです。
こうした理由から、路線価は毎年7月に更新されるたびにニュースで取り上げられ、多くの人が注目する指標になっているのです。
02令和7年の最新路線価、どの地点がどれくらい上昇した?
国税庁が発表した令和7年分路線価は、全国平均では前年より2.7%の上昇となり、地価の上昇はこれで4年連続となります。背景には物価の上昇や円安、各地で進む再開発ラッシュなどがあると見られています。
また、住宅地と商業地のどちらも上昇しており、特に商業地の上昇幅が大きくなっています。
- 住宅地:+2.1%
- 商業地:+3.9%
商業地の上昇には、インバウンド(訪日外国人客)の回復が強く影響しているとされ、東京や大阪、福岡、名古屋といった大都市圏では再開発の影響も相まって、顕著な上昇傾向が見られます。
例えば、東京都中央区銀座5丁目(鳩居堂前)では、1㎡あたりの路線価が4432万円と、日本最高水準を記録しました。これは高級ブランドの出店が集中しているエリアならではの動きといえます。
以下に、令和7年分の都道府県庁所在都市における最高路線価を、「上昇したエリア」と「横ばい・下落したエリア」に分けてまとめました。
都道府県庁所在都市の最高路線価がアップした都道府県
| 都道府県 | 最高路線価 | 変動率 |
|---|---|---|
| 北海道 | 774万円 | 6.3% |
| 青森 | 16万円 | 3.2% |
| 岩手 | 23万円 | 2.2% |
| 宮城 | 370万円 | 1.9% |
| 秋田 | 14.5万円 | 7.4% |
| 栃木 | 34万円 | 3.0% |
| 埼玉 | 592万円 | 11.9% |
| 新潟 | 50万円 | 6.4% |
| 長野 | 29.5万円 | 3.5% |
| 千葉 | 248万円 | 11.2% |
| 東京 | 4808万円 | 8.7% |
| 神奈川 | 1720万円 | 1.4% |
| 山梨 | 26.5万円 | 1.9% |
| 富山 | 54万円 | 3.8% |
| 石川 | 102万円 | 8.5% |
| 福井 | 40万円 | 5.3% |
| 岐阜 | 52万円 | 2.0% |
| 静岡 | 118万円 | 2.6% |
| 滋賀 | 29.5万円 | 3.5% |
| 京都 | 832万円 | 10.6% |
| 大阪 | 2088万円 | 3.2% |
| 兵庫 | 584万円 | 9.8% |
| 奈良 | 87万円 | 10.1% |
| 岡山 | 192万円 | 7.3% |
| 広島 | 371万円 | 3.9% |
| 香川 | 38万円 | 2.7% |
| 高知 | 21.5万円 | 2.4% |
| 福岡 | 968万円 | 2.5% |
| 佐賀 | 23.5万円 | 9.3% |
| 長崎 | 79万円 | 1.3% |
| 熊本 | 210万円 | 1.9% |
| 大分 | 58万円 | 3.6% |
| 宮崎 | 24万円 | 4.3% |
| 鹿児島 | 93万円 | 1.1% |
| 沖縄 | 156万円 | 4.0% |
都道府県庁所在都市の最高路線価が横ばい・下落した都道府県
| 都道府県 | 最高路線価 | 変動率 |
|---|---|---|
| 山形 | 17.5万円 | 0.0% |
| 福島 | 20万円 | 0.0% |
| 茨城 | 22万円 | 0.0% |
| 群馬 | 13.5万円 | 0.0% |
| 愛知 | 1288万円 | 0.0% |
| 三重 | 19.5万円 | 0.0% |
| 和歌山 | 37万円 | 0.0% |
| 鳥取 | 9.1万円 | ▲3.2% |
| 島根 | 14万円 | 0.0% |
| 山口 | 14.5万円 | 0.0% |
| 徳島 | 29.5万円 | 0.0% |
| 愛媛 | 69万円 | 0.0% |
全国平均で2.7%上昇したものの、地方の都市では地価があまり変わらなかったり、逆に下がったりしている場所も見られます。ちなみに全国で唯一、鳥取県が前年よりも地価が下がっています。
横ばい・下落した地域では、次のような理由で地価が下がりやすくなっていると考えられます。
- 人口が減ったり高齢化が進んだりして、家や土地の需要が少なくなっている
- 街の中心部に空き店舗が増えるなど、にぎわいがなくなっている
- 土地を持っていても買いたい人が少なく、売りづらい(資産としての価値が下がっている)
- 空き家が増え、周辺の地価下落に影響している
このようなエリアでは、たとえ今は安く家を買えたとしても、将来売るときに値段がつきにくかったり、資産価値が今よりもさらに下がったりするかもしれません。また、土地の評価額が低いと、住宅ローンの審査で「担保価値」が低く見積もられ、希望する金額を借りられない可能性があることにも注意が必要です。
03路線価が上がると、住宅ローンが借りやすくなる?
「地価が上がると住宅ローンを借りやすくなる」と聞いたことがあるかもしれません。しかし、これは必ずしも「得をする」「家を買いやすくなる」といった意味ではないことに注意しましょう。
住宅ローンでは、購入する土地や建物を「担保」として金融機関に差し出すことで、借り入れを行います。担保とは、万が一返済ができなくなった場合に、金融機関が売却して貸付金を回収するための資産のことです。このとき、路線価が上がっている土地は「担保としての評価額(担保評価)」が高く見積もられる傾向があります。
評価額が高い土地は、借入可能額が増える場合もあります。同じ自己資金を用意していても、担保評価が高い土地を購入するほうが、より多くの金額を借りられる可能性があるということです。特に年収や勤続年数にやや不安がある人にとっては、担保価値の高さがローン審査を補う「プラス材料」として働くケースもあります。
ただし、「借入可能額が増える=お得」とは限りません。地価が上がっているということは、土地そのものの価格も高くなっている可能性が高く、特に注文住宅の場合はこれから建物を建てる費用との合計額が増える可能性があるからです。
また、借入額が増えれば当然、返済額も増え、家計への負担が長期化するリスクにもつながります。物件価格や将来の返済も含めて、資金計画全体を見ながら冷静に借入額を判断することが重要です。
04路線価が上がると税金もアップ?“見えないコスト”に要注意!
地価の上昇は、メリットだけでなく思わぬ落とし穴があります。地価の上昇によって、さまざまな税金の負担が増える可能性があるからです。
固定資産税が高くなることも
土地を所有していると毎年かかる「固定資産税」は、土地や建物の評価額(=固定資産税評価額)を基に計算されます。この評価額は、市区町村が定める独自の基準に基づいており、おおむね実勢価格(時価)の70%程度とされています。
路線価とは直接関係はありませんが、地価全体が上昇すれば、次回の評価替え(3年ごと)のタイミングで固定資産税評価額が見直され、税額が増える可能性があります。特に都市部や再開発エリアでは、評価額の上昇によって想定以上に税負担が増えるケースもあるでしょう。
ちなみに、固定資産税の評価額は3年に一度見直されます。直近の評価替えは2024年に実施されており、次回は2027年の予定です。
路線価の上昇で相続税・贈与税も増える!?
相続や贈与によって土地を受け取る際も、路線価は重要な指標となります。相続税・贈与税の評価額は、「路線価 × 土地の面積」などで算出されるため、地価の上昇はそのまま課税額の増加につながりやすいのです。
特に注意が必要なのは、評価額が非課税枠(基礎控除)を超えてしまう場合です。たとえ土地を売ったり、お金を得たりしていなくても、「土地の評価額が高い」というだけで相続税や贈与税が発生するケースがあります。なお、相続税は相続が発生した年の1月1日時点の路線価をもとに計算されるため、発表が7月であっても、相続が発生した年の1月1日時点の年の路線価が適用されます。
路線価の上昇は住宅ローン審査では有利に働く一方で、保有や相続に関する税金の負担が増えるリスクもあります。家を建てる、土地を買う、相続する──どの場面においても、将来発生するコストを含めた資金計画を立てることが大切です。
05これから住宅ローンを借りる人への5つのアドバイス
2025年の最新路線価は、住宅ローンの借入可能額アップや審査の通りやすさに影響する可能性があります。上手に活用すれば、有利な条件でマイホームを手に入れられるチャンスにもつながるかもしれません。
ただし、路線価の上昇には注意点もあるため、正しく理解することが大切です。ここでは、これから住宅ローンを借り入れる人向けに、損をしないための5つのポイントを解説します。
自分が買いたい土地の路線価をチェックする
土地の価格や税金、住宅ローン審査にも関わる「路線価」は、購入前に必ず確認しておきたい指標です。国税庁の「路線価図」サイトでは、住所や地図から簡単に検索できます。
例えば、同じ市内でも駅から徒歩5分の住宅地は1㎡あたりの路線価が20万円前後でも、郊外のバス便エリアでは10万円を下回るケースもあります。このように、エリアや立地条件によって評価額に大きな差があるため、土地選びの比較材料としても重要です。
金融機関の担保評価をもとに、借入可能額を試算してみる
住宅ローンでは、担保評価額に応じて借入可能額が決まります。金融機関では、公示地価や基準地価格、路線価などを参考に決定するのが一般的で、担保評価額が高い土地ほど借入可能額が増える傾向にあります。そのため、不動産会社や銀行で事前にシミュレーションしておくと安心です。
金融機関に「最新の路線価で審査してください」と伝える
住宅ローン審査では、古いデータで評価されることがあります。新しい路線価に基づく評価額の方が担保価値が上がり、条件が有利になることもあるため、念のため「最新の路線価で評価してもらえるか」を金融機関の担当者に確認しましょう。
例えば、昨年の路線価が「1㎡あたり25万円」だった土地が、今年「1㎡あたり28万円」に上昇していた場合、そのまま古い評価で審査が進めば担保評価額は低く見積もられてしまいます。新しい路線価で評価してもらえれば、担保評価額が数十万円単位で変わる可能性もあり、借入可能額や審査通過率にも影響します。
返済負担が増えないように、金利タイプも慎重に選ぶ
借りられる金額だけでなく、「どう返すか」も重要です。最近は日銀の金利政策の影響で、住宅ローン金利は今後じわじわと上昇するのではないかと言われています。傾向にあります。特に変動金利は、今は金利が低めですが、今後金利が上がると返済額が増えるリスクもあります。
毎月の返済額や総返済額をしっかり比較し、固定金利やミックスプランなども視野に入れて、自分の収入やライフプランに合った金利タイプを選ぶことが大切です。合わせて無理のない返済計画を立てることも忘れないようにしましょう。
税金の増加リスクも含めて「維持できるか」を考える
路線価の上昇は、固定資産税や相続税など、将来的な税金の負担増につながります。例えば、固定資産税が年間10万円だった土地が、路線価の上昇により固定資産税評価額が見直され、3年後に年間12万円に増えたとすると、3年間で合計6万円の差が生まれます。こうした税金の積み重ねは、長期的に家計を圧迫する要因になりかねません。
マイホーム購入後は、「ローンの返済」だけでなく、「維持するためのコスト」も発生します。「買って終わり」ではなく、「持ち続けられるかどうか」まで見据えて、無理のない資金計画を立てましょう。
06住宅ローン選びで後悔しないために、まず「借りられる金額」と「返せる金額」をシミュレーションしよう
いま、地価の上昇により住宅ローンの担保評価額が上がりやすくなっているため、「借りやすさ」が高まっている状況です。しかし、借りられる金額が増えたからといって安心は禁物です。固定資産税や相続税といった“これから発生するコスト”の増加リスクや、今後の金利上昇による返済負担の増加も十分に考慮しなければなりません。
大切なのは、「いくら借りられるか」ではなく、「いくらなら無理なく返せるか」を早い段階で把握しておくことです。路線価や金利の動きをしっかりと把握し、自分に合った借り方を選べる人こそ、後悔のないマイホーム購入に近づけます。
こんな方には「スゴ速住宅ローン保証審査」がおすすめ!
- 今の年収で、住宅ローンはいくらまで借りられるのか知りたい
- 金利や地価が上がる前に、借入可能額を把握しておきたい
- 金融機関に行く前に、スマホで事前審査を済ませておきたい
そんな方におすすめなのが、リクルートの「スゴ速住宅ローン保証審査」です。最短5分で入力完了、複数の金融機関と連携しているため、借入可能額や保証の可否がすぐに分かります。また、借入金額と返済負担のバランスを見極めるには、住宅ローンシミュレーターの活用が効果的です。「自分はいくら借りられるの?」「毎月の返済額はどのくらい?」など、さまざまな疑問は、目的別に用意された4つのシミュレーターでスムーズに解消できます。

監修:新井智美
CFP®/1級ファイナンシャル・プランニング技能士
プロフィール
トータルマネーコンサルタントとして個人向け相談の他、資産運用など上記相談内容にまつわるセミナー講師を行う傍ら、年間100件以上の執筆・監修業務を手掛けている。