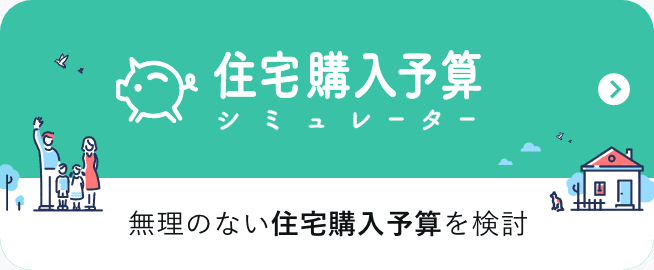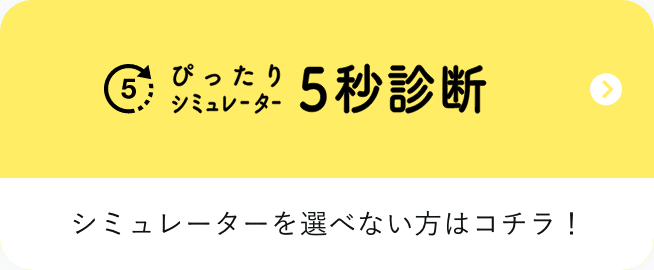家を買うメリットってなんだろう?持ち家と賃貸で比較してみよう
終の棲家を考えると、「持ち家にするか」「このまま賃貸にするか」という問題で悩む方も多いでしょう。特に将来的には、どちらの方が得になるのかが一番気になるところですよね。しかしこの2つの選択肢は「費用」だけでなく、長く住むことを考えた上での「実用面」「資産価値」なども考える必要があります。今回は「持ち家か、賃貸か」という問題について、できるだけ分かりやすく解説します。
01持ち家、賃貸それぞれのメリット・デメリットは?
「持ち家」と「賃貸」には費用、資産としての評価、そして実用面それぞれにメリット、デメリットがあります。基本的な特徴とともに、その違いを理解しておきましょう。
持ち家のメリット
持ち家の主なメリットは以下の通りです。
- 資産になる(社会的信用度が高まる)
- ローンを完済すれば、毎月の住居費は少なくて済む
- 団体信用生命保険に加入すれば、住宅ローン契約者(主に世帯主)が万一死亡、高度障害状態になった場合に、以降のローンを支払わなくて済む
- 間取りや内外装などを自分たち好みにカスタマイズできる
ローン完済後は住居費が固定資産税や管理修繕費のみになるので、老後の年金生活を維持していくためには有効な選択になります。リフォームも自由なので、家の中をバリアフリー化するタイミングも自由に選べます。また持ち家があることは、満足感や安心感にもつながるでしょう。
持ち家のデメリット
持ち家のデメリットは以下の通りです。
- 家の購入時の費用(諸費用・頭金など)がかかる
- 所有している限り固定資産税などの税金がかかる
- 老朽化による修繕費、水回りやバリアフリー化のためのリフォーム費などがかかる
- マンションの場合は、管理費や修繕積立金がかかる
- 家族構成やライフスタイルに変化があっても、簡単に住み替えができない
- 場所によっては災害リスク(台風や水害、地震など)がある
- 売却時に希望価格で売れない、買い手がつかないなどの可能性がある
不動産は一度購入すると、立地などの条件によっては簡単に売却できない可能性もあります。定期的なメンテナンス費用も必要です。そして最大の難点は、住宅購入には多額の資金が必要なことでしょう。購入手続時に必要となる「諸費用」は、100万円以上の金額になることもあります。頭金や手付金なども必要です。また「住宅ローン」を組む際は、金融機関からのローン審査をクリアしなければなりません。
また住宅ローンの借入額にも注意が必要です。収入に見合う借り入れをしないと、月々の返済で生活が成り立たなくなってしまいます。ローン返済中に転職や失職などによって、収入が減った場合のリスクも考えておくことも大切です。
賃貸のメリット
賃貸の主なメリットは以下の通りです。
- 初期費用が比較的低額で済む(家賃の5カ月程度が相場)
- 住宅ローンによる将来的な破綻リスクはない
- 年収減などで安い賃貸に移るなど、引っ越しがしやすい
- 設備のメンテナンスなど、維持費が少ない
- 保有資産ではないので、不動産価格の下落などの影響を受けない
賃貸のメリットは「初期費用が低額」「住宅ローンの負債がない」「すぐに引っ越しできる」の3点に集約できるでしょう。特に「引っ越ししやすい」ことは大きなメリットの1つです。例えば老後は老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅への入居を考えた場合でも、賃貸であればすぐに住まいを移すことができます。収入や働く場所、家族構成に合わせて最も住みやすい住宅を選ぶことができる点が、賃貸スタイルの魅力と言えるでしょう。
賃貸のデメリット
賃貸のデメリットについては以下の通りです。
- 家賃を一生払い続けなければならない
- 改築、バリアフリー化など自由にリフォームができない
- 防音性の悪い物件や老朽化への対応が万全ではない物件もある
- 世帯主が死亡や急病などの場合でも住居費を払い続けなければならない
- 高齢になると、賃貸契約を結びにくい
- 年金収入のみだと、家賃の負担が大きい(経済的、精神的不安がある)
賃貸の主な問題は「住居の快適性」と「家賃の負担」です。マンションや集合住宅などでは十分にメンテナンスされていない物件もありますが、勝手にリフォームもできないので住居の快適性は低くなりがちです。
また老後に大きな負担となるのが家賃です。住居費は、一般に月収の25%以内が理想とされています。年金暮らしでは、収入に対する家賃の占める割合が大きくなるので、経済的な余裕がないと精神的にも不安な生活になるおそれがあります。
02持ち家と賃貸で一生の住居費はどれくらい変わる?
では具体的な事例を用いて、実際に持ち家と賃貸の住居費を比較してみましょう。今回の事例では30歳から85歳(平均寿命)になるまでの住居費についてシミュレーションします。ここでは、持ち家の場合の住宅ローン控除は含めないことにします。
持ち家の場合
住宅の購入価格は4000万円を想定(各項目の想定値は、平均的な相場を参考に設定)。
住宅頭金(任意):400万円(ここでは住宅価格の10%を想定)
諸費用(登記費用など):100万円
住宅ローンの総返済額:4555万7820円
借入額3600万円、期間35年、固定金利1.4%、ボーナス払いなし、月々の支払い額10万8471円で試算すると、「4555万7820円(年間返済額130万1652円)= 10万8471円 × 12カ月 × 35年」となります。
もし年2回のボーナス月に17万円ずつ加算できれば、月々の支払いを8万円台に抑えることも可能です。
固定資産税:872万6685円
固定資産税(標準税率1.4%)は住宅の購入価格ではなく、固定資産税評価額(地価公示価格の7割相当)にもとづいて計算します。今回の事例では、固定資産税評価額を購入価格4000万円の7割の2800万円(土地2000万円・建物800万円)と仮定します。
<各々固定資産税額(試算時年額)>
土地:4万6667円(固定資産税評価額2000万円 × 小規模住宅用地の軽減措置1/6 × 標準税率1.4%)
建物:11万2千円(固定資産税評価額(800万円 × 標準税率1.4%)
合計:15万8667円
85歳まで住むと仮定すると、「872万6685円 = 15万8667円 × 55年」となります。
※市街化区域に居住する場合は、さらに「都市計画税」も納める必要があります。
持ち家の費用合計額:5928万4505円(税金込み・修繕費や管理費なし)
住宅の購入にかかる費用に固定資産税を加えると、30歳から85歳まで住む場合の合計費用の概算は5928万4505円です。税金や住宅ローンの金利を合わせると、4000万円の物件がこれだけの金額になることが分かりますね。また頭金がシミュレーションより少ない場合は、借入額が増えるため、負担する住宅ローンの金利の合計額もさらに増えます。
<上記への加算額>
上記に加えて修繕費などを見積もる必要があります。
マンションは管理費や修繕費などもかかります。管理費・修繕積立金が月平均1万5000円かかるとすると、55年間の合計はで「990万円 = 1万5000円(1カ月)× 12カ月 × 55年」と1000万円近くになります。マンション(持ち家)の管理費・修繕費を含む費用合計額は、6918万4505円になります。
戸建住宅は外壁の修繕、水回りのリフォームなどがかかります。立地や住宅の構造にもよりますが、一般的な木造2階建て住宅でそれぞれ200万円前後とすると、55年間で約400万円の修繕費は必要です。戸建て住居(持ち家)の修繕費などを含むと、費用の合計額は6328万4505円になります。
賃貸の場合
賃貸の場合もシミュレーションしてみましょう。上記と同様に30歳から85歳まで賃貸で暮らすと想定し、家賃設定は住宅ローンの例と同程度の月10万8471円とします。賃貸住宅の家賃を払う場合も、住宅ローンを組む場合と同様に、住宅費は年収の25%程度までが適正とされ、月10万8471円の住宅ローンを組む人は月10万8471円以下の物件を借りると考えられるからです。
初期費用:55万3202円
敷金21万6942円 + 礼金10万8471円 + 前家賃10万8471円 + 仲介手数料(消費税込)11万9318円
家賃の総額:7451万9577円(更新料込み)
家賃10万8471円に入居期間55年で「7159万860円 = 10万8471円 × 12カ月 × 55年」となります。ただし関東圏などの賃貸住宅では、2年ごとに契約更新のための更新料が別途かかることが一般的です。55年間の更新料の合計は「292万8717円 = 10万8471円 × 27回」となります。家賃と合わせると、7451万9577円になります。
賃貸の費用合計額:7507万2779円
初期費用と家賃の総額を合わせると、「7507万2779円 = 55万3202円 + 7451万9577円」となります。
上記への加算額(家賃とは別枠で管理費・共益費を考える場合)
賃貸マンションの場合、家賃とは別に毎月、「管理費」や「共益費」といった共用部分の維持管理費用がかかるケースもあります。一般的に管理費・共益費は、家賃の5~10%が相場と言われているため、今回の月額10万8471円の賃貸物件で1万円(9.2%)の管理費・共益費かかると仮定すると、「660万円 = 1万円(1カ月)× 12カ月 × 55年」が加算されます。賃貸マンションの管理費・共益費を含む費用合計額は、8167万2779円になります。
持ち家(一戸建て)
| 住宅頭金 | 400万円 |
|---|---|
| 諸費用(登記費用など) | 100万円 |
| 住宅ローンの総返済額 | 4555万7820円 |
| 固定資産税 | 872万6685円 |
| 修繕費※ | 400万円 |
| 合計 | 6328万4505円 |
賃貸
| 初期費用 | 55万3202円 |
|---|---|
| 家賃の総額 | 7159万860円 |
| 更新料 | 292万8717円 |
| 合計 | 7507万2779円 |
上記結果から、費用面(管理費・修繕費などを含む)で比較すると、持ち家の方が賃貸より安くなる可能性があります。ただし上記試算は一例ですので、住宅ローンの借入額、借入期間、金利などにより、結果は異なります。持ち家と賃貸のそれぞれのメリット・デメリットに優先順位をつけて、判断するとよいでしょう。
03今後、持ち家と賃貸どちらの需要が増えていく?
総務省統計局「平成30年住宅・土地統計調査」によれば、居住世帯全体の持ち家率は61.2%となっており、2013(平成25)年と比べて0.5%減少しています。一方、借家の住宅総数に占める割合は35.6%となっており、2013(平成25)年と比べて0.1%上昇しています。
2020(令和2)年には「コロナショック」が加わりました。国土交通省「建築着工統計調査報告(令和2年8月)」によると、新設住宅着工戸数は6万9101戸で前年同月比9.1%減となり、14カ月連続の減少となっています。コロナ禍で住宅の建設や販売が制限されたためと考えられます。こうした状況下の新築住宅は、需給バランスによって価格が変動しやすいと言えるでしょう。
一般世帯総数は2023(令和5)年以降減少!住宅購入の行方は?
国立社会保障・人口問題研究所「日本の世帯数の将来推計(全国推計) 2015~2040年」によると、一般世帯総数は2015(平成27)年には5333万世帯だったが、その後増加を続け、2023(令和5)年には5419万世帯となり、ピークを迎えると予測されています。その後は減少に転じ、2040 (令和22)年の一般世帯総数は5076万世帯となると考えられています。世帯数が減る2023(令和5)年以降は、「持ち家需要」も減ると考えられます。中古住宅などを含めると、住宅価格が低下傾向になる可能性もあり、住宅購入を検討するチャンスになるかもしれません。
ただし全体的な不動産需要が減ることによって、人気のあるエリアとそうでないエリアの「格差」が大きくなる可能性があります。例えば都心近郊エリアではほとんど価格が下落しない反面、郊外エリアだと数%レベルの下落になるような現象です。
このような地域格差については、マイホームの買い替えや住み替えを検討する場合に注意が必要です。いざ売りに出してみても思うように買い手がつかない、かつての相場よりも安くなっているという事態では、住宅の売却代金を元手に新たな住まいへ買い換える、あるいは老人ホームに入居するなどの計画に支障が出るからです。最初の住宅購入時には、資産価値が下がらないか、その後の住宅相場をしっかり見極めましょう。
04持ち家を選ぶ際は諸費用を含めて綿密な資金計画を立てよう
終の棲家を「持ち家」にすべきか「賃貸」にすべきか、それぞれのメリットを検討してみましょう。「持ち家」には資産価値がある、好みに応じてアレンジできる、安心感などがあります。「賃貸」には住宅ローンの負債がない、いつでも転居できるなどがあります。「持ち家」を選ぶ場合は住宅の購入時の諸費用を含めて、綿密な資金計画を立てておくことが大事です。気になる方は当サイト内の「住宅ローンシミュレーション」を試した上で、具体的な資金計画の大枠をつかんでおきましょう。

監修:岩永真理
IFPコンフォート代表、一級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP®、住宅ローンアドバイザー
プロフィール
大手金融機関にて10年以上勤務。海外赴任経験も有す。夫の転勤に伴い退職後は、欧米アジアなどにも在住。2011年にファイナンシャル・プランナー資格(CFP®)を取得後は、金融機関時代の知識と経験も活かしながら個別相談・セミナー講師・執筆(監修)などを行っている。幅広い世代のライフプランに基づく資産運用や住宅購入、リタイアメントプランなどの相談多数。
関連キーワード