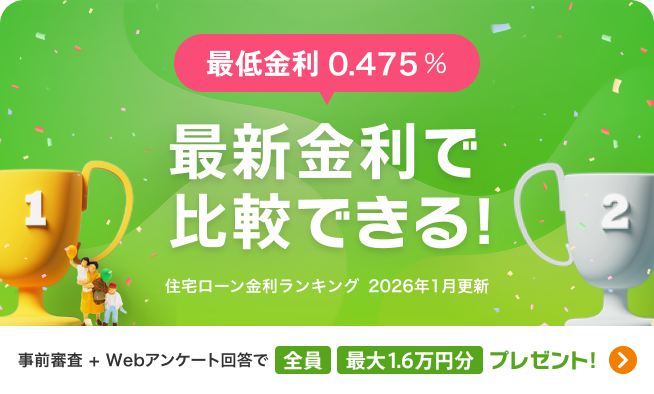2025年度|リフォームに活用できる補助金・助成金、減税制度を紹介
リフォームを検討する中で、補助金や助成金を使いたいと考えている人も多いのではないでしょうか。リフォームに使える補助金・助成金の制度には、さまざまな種類があります。 同じ内容のリフォーム工事であっても、制度によって給付される補助金の額が異なるケースもあり、どの制度が自身のリフォームに適したものなのかよくわからないといった声も聞かれます。 この記事では、リフォームする際に利用できる2025年度の補助金・助成金制度についてまとめました。減税制度も合わせて紹介しますので、併用してお得にリフォームを実現しましょう。
01リフォームに使える補助制度
まずは国が行っている、以下のリフォームに関する補助制度について紹介します。
- 住宅省エネ2025キャンペーン
- 子育てグリーン住宅支援事業
- 先進的窓リノベ2025事業
- 給湯省エネ2025事業
- 賃貸集合給湯省エネ2025事業
- その他の制度
なお、ここで紹介する各種制度の内容は2025年8月時点の情報であり、新年度以降に内容が変更になる可能性もあります。実際に利用を検討する際は、最新の情報を必ず確認してください。
国が提供する補助制度
では、国が住宅省エネ2025キャンペーンとして提供している4つのリフォームに関する補助制度の内容について詳しく解説していきます。
なお、住宅省エネ2025キャンペーン(リフォーム)の対象者は子育て世帯に限らず、全世帯です。
子育てグリーン住宅支援事業
子育てグリーン住宅支援事業は、2050年カーボンニュートラルの実現に向け、エネルギー価格などの物価高騰の影響を特に受けやすいとされる子育て世帯などに対して、2030年度までに予定されている『新築住宅のZEH基準相当の省エネ性能確保』の義務化に向けた支援を行うとともに、既存住宅についての省エネ改修等への支援を行う事業です。
補助金の対象
補助金を受けるには、次の2つの条件を満たす必要があります。
- グリーン住宅支援事業者と工事請負契約等を締結し、リフォーム工事をする
- リフォームする住宅の所有者等である
対象のリフォーム工事
子育てグリーン住宅支援事業では、次の8点のいずれかに該当するリフォーム工事が対象です。
- 必須工事
- 開口部の断熱改修
- 躯体の断熱改修
- エコ住宅設備の設置
- 任意工事
- 子育て対応改修
- 防火性向上改修
- バリアフリー改修
- 空気清浄機能・換気機能付きエアコンの設置
- リフォーム瑕疵保険等への加入
必須工事である1~3に該当するリフォーム工事のうち、2つ以上の工事を実施した場合に補助が受けられます。4~8の任意工事については、必須工事のうち2つ以上のリフォーム工事を行ったうえで実施し、交付申請時に合わせて申請する場合に限られます。
また、1つの申請あたりの補助額の合計が5万円未満の工事については補助の対象外です。
対象となる期間と要件
2024年11月22日から交付申請(遅くとも2025年12月31日)までに着工し、かつ、着工までに工事請負契約が締結されていること。
リフォームにおける補助上限額
工事内容に応じて40万〜60万円/戸
手続き期間
- 交付申請の予約:申請受付開始から予算上限に達するまで(遅くとも2025年11月14日まで)
- 交付申請:申請受付開始から予算上限に達するまで(遅くとも2025年12月31日まで)
注意点
この事業による補助金を受けるには、工事施工業者が補助対象者に代わって交付申請等の手続きを行い、補助金の交付を受け、そして交付された補助金を補助対象者に還元するものとして事務局に登録された者でなければなりません。未登録の事業者による施工だと、補助金対象外となりますので注意しましょう。
先進的窓リノベ2025事業
既存住宅の早期の省エネ化を図り、エネルギー費用負担の軽減および住まいの快適性の向上、2030年度の家庭部門からのCO2排出量削減、「高い生活の質」の実現に貢献するとともに、先進的な断熱窓の導入によって、価格低減を促進することで関連産業の競争力強化や経済成⾧を実現することを目的とする事業です。
補助対象
既存住宅に行う開口部の断熱性能を向上する事業が対象です。
※賃貸住宅も対象ですが、目的が居住用でなければなりません。
補助額
補助対象工事により設置する製品の性能と大きさ、および設置する住宅の建て方に応じた製品ごとの補助額(定額)の合計(1戸あたり200万円が上限)。
対象期間
- 契約期間:工事着手日以前
- 工事着手日の期間:2024年11月22日以降に対象工事に着手したもの
- 交付申請期間:申請受付開始から予算上限に達するまで(遅くとも2025年12月31日まで)
- 交付申請の予約期間:申請受付開始から予算上限に達するまで(遅くとも2025年11月14日まで)
施工会社は補助対象者に代わり交付申請等の手続きを行い、補助金の交付を受け、交付された補助金を補助対象者に還元するものとして事務局に登録された者でなければなりません。また、交付申請もしくは交付申請の予約までに事業者登録が必要です。
給湯省エネ2025事業
家庭のエネルギー消費で大きな割合を占める給湯分野について、高い効率を持つ給湯器の導入支援を行い、その普及拡大によって、「2030年度におけるエネルギー需給の見通し」の達成に寄与することを目的とする事業です。正式な名称は「高効率給湯器導入促進による家庭部門の省エネルギー推進事業費補助金」となっています。
補助対象
戸建、共同住宅によらず、既存住宅に高効率給湯器を設置する事業。
補助額
補助額は設置する給湯器によって基本額が以下のとおり異なります。
- ヒートポンプ給湯機(エコキュート):6万円/1台
- 電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯機(ハイブリッド給湯器):8万円/1台
- 家庭用燃料電池(エネファーム):16万円/1台
参考:給湯省エネ2025事業
着工日と交付申請時期
- 着工日:1台目の給湯日の設置開始日
- 以後の予約:契約工事全体の着手日
- 以降の交付申請:工事の引渡しまたは共同事業者による共同事業者による給湯器の利用開始のいずれか早いほう
また、住宅省エネ2025キャンペーン以外にも、以下の事業が行われています。
既存住宅の断熱リフォーム支援事業
既存住宅における断熱リフォーム支援事業は、15%以上の省エネ効果が見込まれる断熱性能の高い断熱材、窓、ガラスの建材を用いて、既存住宅の断熱リフォームを行った際に補助金が交付される事業です。
この事業では、断熱材、窓、ガラスを組み合わせて断熱改修を行う「トータル断熱」と、窓を用いて居間をメインに断熱改修する「居間だけ断熱」の2つを行っており、併用はできません。
補助金の対象
常時居住する専用住宅の個人所有者、もしくは個人の所有予定者(戸建て住宅、集合住宅の個別住戸の場合)が対象です。
補助額
- 補助率は補助対象経費の1/3以内
- 高性能建材については一戸につき上限120万円(戸建て住宅)
- 集合住宅の場合は一戸につき上限15万円(同時に玄関ドアの改修を行う場合は20万円/戸)
申し込み方法
- 公募期間内に申請する
- 交付決定通知書が発行される
- 交付決定通知を受けた後に契約・工事を実施
- 完了後一定期間内に完了実績報告書を提出し、補助金が交付される
その他の要件
交付申請後に所有を予定している場合は、工事完了後、完了実績報告者を提出する際に登記事項証明書の写しを提出し、所有したことを証明する必要があります。
また、居間だけ断熱の場合、居間は必ず改修しなければなりません。
施工会社はあらかじめ事業に登録した業者である必要はなく、補助事業に対応できる業者であればどの会社でも構いません。高性能建材を使用した断熱リフォームを検討している場合には、リフォーム会社に詳細を問い合わせてみるといいでしょう。
長期優良住宅化リフォーム推進事業
長期優良住宅化リフォーム推進事業は、長期間にわたって良好な状態で住み続けられる構造や設備を備えた、長期優良住宅にリフォームする場合に補助金が交付される事業です。
補助金を受けるための要件
この補助金を受けるためには、次の4つの要件に全て当てはまる必要があります。
- 工事前にインスペクション(建物状況調査)を実施し、維持保全計画・リフォーム履歴を作成すること
- リフォーム工事完了後に一定の性能基準を満たしていること
※詳しくは本事業の「住宅性能に係る評価基準」を参照 - 性能向上に資する改修工事、三世代同居対応改修工事、子育て世帯向け改修工事といった所定の工事を行うこと
- 住戸面積、居住環境、維持保全計画の内容などが要件に適合していること
補助額
補助金額は対象となるリフォーム工事の1/3ですが、以下のとおり、工事後の性能によって補助金の上限額が変わります。
- 認定長期優良住宅型:所管行政庁から長期優良住宅(増改築)の認定を受けたもの(全ての性能項目で認定基準に適合することが必要
- 評価基準型:性能項目のうち、劣化対策、耐震性、省エネルギー対策について評価基準に適合するもの
| タイプ | 1戸あたりの補助上限額 |
|---|---|
| 認定長期優良住宅型 | 160万円(210万円) |
| 評価基準型 | 80万円(130万円) |
※1 申請あたりの補助金額が10万円(補助対象工事費頭が30万円以下は補助対象外
申し込み方法
- 所有する住宅をリフォームする場合、主に補助事業者である施工会社が手続きを行う
- 施工会社はリフォーム工事の事業者登録を事前に行っている必要があり、申請にあたっては施工会社と工事請負契約の締結が必要
- リフォーム工事を行う住宅が決まったら、所在地などの情報を登録する
- 補助金は一度施工会社に交付されるが、その後、リフォーム工事代金から差し引かれて精算するケースが多くなっている
子育て支援型共同住宅推進事業
共同住宅(分譲マンション及び賃貸住宅)を対象とした取組みを支援することにより、子どもと親の両方にとって健やかに子育てができる環境の整備を進めることを目的とした事業です。
補助対象となる共同住宅
賃貸住宅の新築・改修、分譲マンションの改修
補助対象事業
- 転落防止の手すりや補助錠の設置、防犯性の高い窓や玄関ドアの設置など、子どもの安全確保に資する設備の設置に対する補助
- 多目的室(キッズルーム・集会室)の設置やプレイロット(遊具・水遊び場・砂場)の設置など、居住者等による交流を促す施設の設置に対する補助
交付申請受付期間
2025年4月1日(火)~2026年2月27日(金)
完了実施報告書提出期限
2026年2月3日(火)
補助額
補助金額は対象となるリフォーム工事の1/3ですが、以下のとおり、補助対象事業によって補助金の上限額が変わります。
- 子育て支援型共同住宅:住宅の戸数に100万円を乗じた額
- 居住者などによる交流を促す施設の建設:1棟ごとに500万円
02地方自治体が提供する補助金・助成金
国が提供している補助金・助成金とは別に、各都道府県や市区町村で住宅関連の補助金や助成金制度を設けているところもあります。自治体の補助金や助成金は国費が充てられていなければ、原則国の補助金制度と併用することが可能です。詳しくは住まいのある自治体に確認してみるのがおすすめですが、ここでは代表的なものを2つ紹介します。
東京都目黒区|住宅リフォーム資金助成
東京都目黒区では、区民が区内の業者を利用して住宅をリフォームする場合、工事費用の一部助成を受けられます。
補助金の対象となる工事
- 一般リフォーム工事(室内のリフォーム、屋外改修工事)
- 自宅のアスベスト除去工事(区外の業者による施工でも可)
- 区民が区内に所有する賃貸用住宅の空き家・空き室バリアフリー工事
助成金額
- 一般リフォーム:工事費用の10%(千円未満切り捨て・上限10万円)
- 省エネリフォーム対象工事のみの20%(千円未満切り捨て・上下20万円)
- アスベスト除去工事の10%(千円未満切り捨て・上限は20万円)
- 空き家・空き室バリアフリーリフォーム工事の10%(千円未満切り捨て・上限10万円)
対象期間
2025年4月1日から審査受け付け開始
申し込み方法と注意点
着工前に必要書類を全てそろえて、区の住宅課へ提出します。必ず着工の2週間程前までに申請を済ませ、審査結果通知を受けてから工事をスタートしなければなりません。通知前に着工してしまうと助成を受けられないため要注意です。
自治体が実施する住宅リフォーム支援制度を検索しよう
お住まいの自治体でどんな補助金・助成金制度があるのか知りたい方は、一般社団法人住宅リフォーム推進協議会が提供する「地方公共団体における住宅リフォームに係わる支援制度検索サイト」を活用するのがおすすめです。検索サイトで気になる情報があったら、最新の情報については各自治体の窓口に問い合わせてみましょう。
03リフォームに使える減税制度
耐震や省エネ、介護のためのバリアフリー化といった目的で自宅をリフォームする場合、減税制度の対象となる可能性もあります。減税制度の対象になると、確定申告することで減税分が還付されます。先に紹介した国や地方自治体による補助金・助成金の制度と併用すれば、よりお得にリフォーム工事ができるかもしれません。
押さえておきたい5つの減税措置
それでは、リフォーム工事で使える以下5つの減税措置について詳細を確認していきましょう。
- 所得税の控除
- 贈与税の非課税措置
- 固定資産税の減額
- 登録免許税の特例措置
- 不動産取得税の特例措置
所得税の控除
住宅ローン(一体型ローン)やリフォームローンを利用して自宅をリフォームした場合、一定の要件を満たしていれば所得税の税額控除を受けられます。
新築住宅もしくは買取再販住宅を購入した場合は最大13年間、中古住宅を購入した場合は最大10年間、年末の借入残高の0.7%が税額控除されます。所得税から引ききれなかった部分は住民税から差し引かれます。
住宅ローン控除とは別に、リフォームを行った人に対する減税制度も用意されています。10年以上のローンを組んで一定のリフォームを行った場合、毎年の住宅ローン残高の0.7%を10年間、所得税から控除するというもので、所得税から控除しきれなかった部分は翌年の住民税からも控除が可能です。借入限度額は2000万円、また最大控除額は140万円であることも覚えておきましょう。
また、ローンを利用せず自己資金で2025年12月31日までにリフォームした人であっても、長期優良住宅であれば「投資型減税」を適用可能です。控除額は「4万5300円 × 家屋の床面積(平方メートル)」で求められ、1年のみ所得税から控除されます。控除しきれない分は翌年度の所得税から控除される仕組みです。ただし控除対象限度額は650万円、最大控除額は65万円となっています。また、住宅ローン控除との併用はできません。
贈与税の非課税措置
他人から金銭や資産の贈与を受けた場合には贈与税が課税されますが、自宅のリフォーム費用を親もしくは祖父母(直系尊属)から贈与された場合、一定の要件を満たせば贈与税は非課税となります。この特例を「住宅取得等資金の非課税制度」と呼びます。
この制度を受けるためには、2024年1月1日から2026年12月31日までの間に、父母や祖父母など直系尊属からの贈与によって自宅をリフォームするなどの要件が必要です。
非課税限度額は、贈与を受けた人ごとに
- 省エネ等住宅の場合:1000万円まで
- それ以外の住宅の場合:500万円まで
となっています。
詳しく知りたい方はこちらの記事を参考にしてください。
固定資産税の減額
窓の改修工事をはじめとした省エネ改修工事を実施した住宅について、翌年分の固定資産税額が1/3もしくは2/3減額されるという制度もあります。この減税を受けるにあたっては、行ったリフォームが以下に当てはまらなければなりません。また、工事完了後3ヶ月以内に申請する必要があります。
- 耐震リフォーム
- 省エネリフォーム
- バリアフリー改修
- 長期優良住宅化リフォーム
固定資産税は地方税のため、詳細については各市区町村へ問い合わせるといいでしょう。
登録免許税の特例措置
マイホームを取得する場合やリフォームされた中古住宅を購入する場合は、家屋の所有権移転登記に係る登録免許税の軽減を受けられる可能性があります。
中古物件購入であれば税率は2.0%から0.3%に軽減されますが、宅地建物取引業者が中古住宅に対して一定の良質なリフォームを実施し、その住宅を個人が取得した場合については、登録免許税の税率が0.1%まで軽減されます。
税率の軽減を受けるにあたっては、市区町村が交付する「住宅用家屋証明書」が必要です。証明書発行のためには、床面積が50平方メートル以上であることや一定の耐震性を有していることなどの要件を満たしていなければなりません。また、新築または引き渡しから1年以内に登記する必要がある点も要注意です。
適用期間は2027年3月31日までとなっていますが、延長される可能性もあるため、注意しておきましょう。
不動産取得税の軽減措置
自分で居住するために中古住宅を購入し、適用用件を満たすリフォームを行った場合、不動産取得税の軽減が適用可能です。軽減額は新築年月日によって異なります。
不動産取得税の軽減措置には、2つの種類があります。
- 耐震基準に適合しない中古住宅を購入し、耐震改修工事を行った場合
- 宅地建物取引業者が中古住宅を買い取り、住宅性能の一定の向上を図るための改修工事を行った後に、個人の居住用住宅として譲渡する場合
ちなみに1は期限が決められていませんが、2については2027年3月31日までに宅地建物取引業者が中古住宅を取得し、その日から2年以内に改修工事を行ったうえで個人に譲渡し、居住する必要があります。また、この場合の中古住宅は新築後10年を経過したものでなければなりません。
具体的には、以下の全ての要件を満たした場合に、新築年月日に応じた額が減額されます。
- 改修工事対象住宅を取得した日から2年以内に、以下の全ての事項を満たすこと
- 住宅性能向上改修工事を行う
- 改修工事を行った住宅を個人に譲渡する
- 譲渡を受けた個人が自分の居住目的で利用している
- 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上240平方メートル以下であること
- 1982年1月1日以後に新築されたものまたは耐震基準に適合していることが証明されたもの
減額額
改修工事対象住宅の新築年月日に応じて、最大減額額が決められています。ちなみに新築年月日が1985年7月1日から1989年3月31日に該当する場合の最大減額額は13万5000円です。
要件や申請時期は都道府県ごとに異なるため、詳細については自治体のホームページなどで確認しましょう。
04補助・減税制度を利用するときに知っておきたいポイント
ここまで紹介してきた補助金・助成金制度や減税制度を利用するにあたり、あらかじめ押さえておくべきポイントについて紹介していきます。
補助制度と減税制度は併用できる
補助金・助成金制度と減税制度はどちらもお得にリフォームできる仕組みですが、その違いはよくわからないという人も多いのではないでしょうか。それぞれの制度がどのようなものか、簡単に見ていきましょう。
- 補助金・助成金制度
- 国や地方自治体がリフォームを行う個人や事業者に対して、その費用の一部を支給する制度
- 減税制度
- 控除などにより、対象者が本来納めるべき税金を減らすことができる制度
このように2つは全く違う制度のため、基本的に併用可能です。まずは利用を希望する補助金制度などに申請し、承認されればリフォーム工事に対する補助金が支給されます。工事費用から補助金制度による交付分を差し引いた金額が、減税制度の控除対象となります。
事前によく制度を確認しておく
リフォームを含む住宅関連の支援事業は、予算や締め切りが決められているものが大半です。そのため、新年度になると制度自体がなくなったり、内容が変更されたりすることがあります。
また、リフォーム工事の着工前に申請しなくてはならない事業も多いので、利用前に制度内容をしっかり確認しておかないと、いざ使いたいときに使えないという事態になりかねません。
要件がたくさんあって、細かな箇所に大切な内容が記載されているケースも散見されます。利用したい場合はあらかじめ入念にリサーチをしつつ、不安な場合は制度を実施している国・市区町村の窓口やリフォーム業者に相談するようにしましょう。
05知らないと損するかも!? リフォームで利用できる補助金や減税制度を大いに活用しよう
新年度を迎えると、リフォームに関する補助金・助成金制度も大きく変わります。中には、こどもみらい住宅支援事業のように今年度から新たに実施されるものもあるため、これからリフォームを検討しているのであれば情報収集は欠かせません。制度を知らないと損してしまうこともあるので、事前のリサーチを忘れないようにしましょう。

監修:新井智美
CFP®/1級ファイナンシャル・プランニング技能士
プロフィール
トータルマネーコンサルタントとして個人向け相談の他、資産運用など上記相談内容にまつわるセミナー講師を行う傍ら、年間100件以上の執筆・監修業務を手掛けている。
関連キーワード