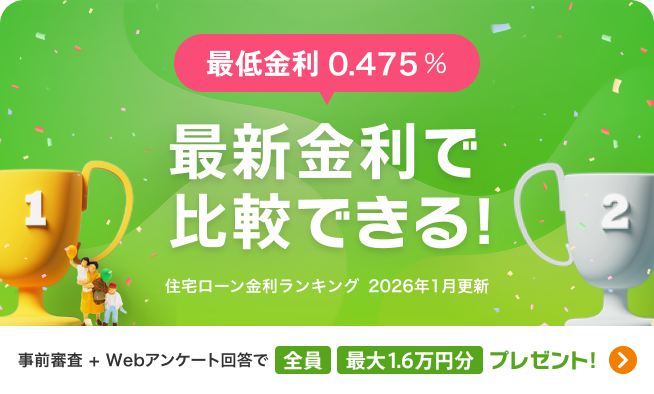トランプ関税ショックで日本の住宅ローンに異変!金利はどう動く?今後の注意点を解説
2025年4月、再び大統領に収入したトランプ氏は、自国産業の保護を名目に、これまでに比べて関税を大幅に強化する政策を打ち出しました。これにより世界経済は大きく混乱し、株価が一時的に乱高下するなど、市場は不安定な動きを見せています。 日本国内でも長期金利の上昇が懸念されており、今後の住宅ローン金利にも影響を及ぼすのではないかとの見方が強まっています。これから住宅ローンを借りる人や、すでに変動金利で借りている人にとって、今後の金利動向は見逃せないポイントの1つでしょう。 この記事ではトランプ関税の概要をはじめ、長期固定金利・変動金利の最新情報について解説します。また、住宅ローンを利用するうえで知っておきたいポイントや「仮に金利が2%になっても慌てないための備え」についても紹介するので、今後の住宅ローンに不安を抱いている方は参考にしてください。
- 01トランプ関税とは?日本にも影響があるの?
- トランプ関税による日本への影響
- 02トランプ関税で日本の住宅ローンはどうなる?3つの注目ポイント
- 長期金利が一時的に下がり、固定金利も利下げ傾向に
- 円高が進み日銀が金利を上げにくくなる
- 金融機関の住宅ローン審査が厳しくなる可能性がある
- 032025年5月の住宅ローン金利はどう推移している?変動・固定の最新動向をチェック
- 04これから借りる人・変動金利で借りている人が今すぐ知っておくべき住宅ローンの判断ポイント
- すでに変動金利で借りている人は、今のうちに「今後」を考える
- これから借りる人は「変動金利2%」まで耐えられるかが分かれ目
- 05変動金利年2%で返済額シミュレーションしてみよう
- 06トランプ関税は住宅ローンの金利にも影響!世界情勢と金融政策を注視しよう
01トランプ関税とは?日本にも影響があるの?
トランプ関税の目的は、簡単にいうと、「自国産業を保護すること」です。関税は海外からの輸入品に対してかかるため、海外で安く生産された商品を自国内で販売する場合、必然的に価格は高くなります。その結果、国内で生産された商品価格との差が縮まり、アメリカの産業や雇用が守られると考えたわけです。トランプ大統領は前回(2017~2021年)の大統領就任時から一貫して「アメリカ・ファースト」を掲げ、国内の労働者を守る政策を推進してきました。
しかし、新たな関税を導入することで結果的にアメリカ国内の商品価格が高くなる恐れがあること、世界的な貿易摩擦を生む懸念があることなどから、かえって世界全体で経済が悪化する恐れも指摘されています。当然ながら、日本もトランプ関税の影響を大きく受けると考えられていますが、具体的にどのような影響を受けるのでしょうか。
トランプ関税による日本への影響
トランプ関税が発動すると、日本企業のさまざまな業種で輸出が滞り日本経済全体が冷え込む恐れがあります。なぜなら、対立の当事者であるアメリカと中国は、日本にとって最大の貿易相手国であり、その当事者双方が争うことで、日本の主要な輸出産業も取引減少やコスト増といったダメージを受ける可能性があるからです。
また、たとえ日本企業が直接、関税対象とならなくても、米中貿易の停滞によるサプライチェーンの混乱や部品調達コストの上昇を通じて間接的に影響を受ける可能性があります。
大企業がダメージを受ければ、当然その下請けを担っている中小企業にも影響は波及するでしょう。その結果、日本国内全体が不景気になるかもしれません。
実際に、投資家たちの間では世界経済の不安定化が懸念されていて、その影響は為替の急変や株を中心とした金融市場の乱高下といった形で表れています。
特に、日本の長期金利は債券市場の動向に連動するため、米国の経済政策が不透明になると日本の国債利回りにも影響します。住宅ローン金利(特に固定型)にも波及する可能性があるため、今後の金利動向には注意が必要です。
02トランプ関税で日本の住宅ローンはどうなる?3つの注目ポイント
トランプ関税をきっかけにして世界経済や金融市場が不安定になると、日本の住宅ローン金利も影響を受ける可能性があります。そこで、これから住宅ローンを検討する方に向けて、今後注目すべき3つのポイントを紹介していきます。
長期金利が一時的に下がり、固定金利も利下げ傾向に
アメリカは世界経済をリードする存在で、米ドルや米国債は世界的に高い信頼を得ています。しかし、今回のトランプ関税による世界経済の混乱は、そのアメリカが発端となっているため、投資家たちは米ドル以外で信頼できる資産の逃避先を探しました。
その結果、安全資産として知られる日本国債が選ばれ、2025年4月4日の債券市場では、固定型住宅ローン金利に連動しやすい10年物国債に急激な買い注文が入りました。
一般的に「国債の価格が高くなる=金利が下がる」という逆相関の関係にあるため、急激な買いが入ったことで長期金利は低下し、それに伴って固定型住宅ローン金利も一時的に下がるという現象が起きています。
ただし、トランプ関税強化の先行きがどうなるかは不透明です。日本国内のインフレ動向や、日銀の金融政策変更によっては金利が今後上昇する恐れもあるので、住宅ローンの借り入れには今までよりもさらに慎重な判断が求められます。
円高が進み日銀が金利を上げにくくなる
トランプ政権による関税強化の不透明さによってアメリカの信頼が低下すると、為替相場ではドルを売って円を買う動きが加速します。つまり、円高になりやすい状況が生まれるのです。円高が進むと、日本の輸出企業の利益が落ち込み、景気が悪化しやすくなることが考えられます。
また、円高局面では、海外から輸入する原材料やエネルギー価格などが安くなります。これは一見すると消費者にとってよいことだと思うかもしれません。しかし、輸入大国である日本では、輸入価格が下がることで物価が上がりにくくなるため、日銀が経済にとってよい影響を及ぼす指標として目指している「物価上昇率2%」の達成が難しくなります。一般的に、金利を上げると物価はさらに上がりにくくなるので、円高が進んだ場合、日銀は金利の上昇を抑える方向で政策を検討するでしょう。
直近の2025年4月30日から5月1日に開催された金融政策決定会合では、トランプ政権による関税政策そのものや経済に与える影響の不確実性が高いため動向を見極めるという名目で政策金利を0.5%のまま据え置く方針となりました。
その過程においては企業や企業団体から景気を支えるために「金利を引き下げて欲しい」という要望が出ることもありましたが、実際に日銀が利下げに踏み切る可能性は低いとされています。その理由としては現在の金利水準が依然として低いことや物価上昇率が目標に達していないこと、金融政策の柔軟性を維持する必要があることなどが挙げられており、当面の間金利水準は0.5%のままで維持されるのではないかと予想されています。
金融機関の住宅ローン審査が厳しくなる可能性がある
トランプ関税強化による住宅ローンへの影響は金利だけでなく、審査にも及ぶ恐れがあります。なぜなら、一般的に世界経済に不安が広がると、金融機関は貸し倒れリスクに備えて、お金を貸すことに慎重になるからです。その結果、以下のような動きが起こるかもしれません。
- 審査基準(年収・勤続年数・職業など)の引き上げ
- 借入可能額の引き下げ
- 金利優遇条件のハードル引き上げ
仮に金融機関が上記の対応を取り始めると、これまでと同じ条件であっても「数か月前なら通っていたローンが今は通りにくい」ということが起こります。そのため、資金に余裕がある人とそうでない人との間で、住宅ローンを「借りやすい人」と「借りにくい人」の差が拡大するでしょう。
その中でも特に影響を受けやすいのは、「自営業・フリーランス・非正規雇用の方」「転職直後や勤続年数が短い方」です。どちらも収入が安定しているとはみなされにくく、銀行がリスクを感じて貸し渋ったり、借入可能額が少なくなったりする可能性があります。
このような不安定な時期だからこそ、複数の金融機関で事前審査を行って比較したり、頭金を増やして借入額を抑えたりするなど、事前にできる備えをしておくことが重要です。
032025年5月の住宅ローン金利はどう推移している?変動・固定の最新動向をチェック
トランプ関税強化の発表を受けて、実際の日本国内の住宅ローン金利はどのように推移しているのでしょうか。以下はメガバンク3行が取り扱う住宅ローン金利の一覧(2025年5月時点)です。
| 金融機関名 | 変動金利の適用金利(年) |
|---|---|
| みずほ銀行(ローン取扱手数料型) | 0.525%~ |
| 三菱UFJ銀行 | 0.595%~ |
| 三井住友銀行 | 0.595%~ |
※適用金利はいずれも申し込み条件によって変わる可能性あり
変動金利は一部で上昇傾向も見られますが、それほど大きな動きはなく、住宅ローン金利全体では、依然として低水準で推移しています。ただし、変動金利は市場金利の影響を受けやすいので、今後の経済動向を注視しておくほうがよいでしょう。
一方、全期間固定型のフラット35の適用金利については2025年4月時点で年1.94%だったのが、2025年5月には年1.82%になり、わずかではあるものの低下しました。これは先述した長期金利の動向や市場の需給バランスによる影響だと思われます。
04これから借りる人・変動金利で借りている人が今すぐ知っておくべき住宅ローンの判断ポイント
トランプ関税はまだ発動したばかりですので、日本の住宅ローンへの影響はそこまで大きくありません。しかし、住宅ローンの借り入れは長期間に及ぶため、万が一のことを考えて備えておくことは大切です。
そこで、ここからはこれから住宅ローンを借りる人、もしくは変動金利ですでに借りている人に向けて、今すぐ知っておくべき住宅ローンの判断ポイントを解説します。
すでに変動金利で借りている人は、今のうちに「今後」を考える
2025年5月時点で日銀はトランプ関税による影響を見定めるために、急激な金利引き上げには慎重な姿勢を見せています。そのため、これから短期間で変動金利がすぐに大きく上がる可能性は低いでしょう。ただし、近年続く日本の消費者物価指数の上昇は日銀の目標である2%を超えることも多く、長期的に見れば金利が上がる局面に備えておく必要があるのも確かです。その選択肢の1つとして「借り換え」が挙げられます。
借り換えを実行すれば今よりも金利が低いローンに切り替えたり、金利タイプを変更したりできる場合があります。特に固定金利型に変更すれば将来の金利上昇リスクを回避できるほか、借り換え先のローンによっては、団信(団体信用生命保険)の保障が充実し、万が一の事態により備えられるようになるかもしれません。一般的に10年以上前に借り入れた住宅ローンは現在の金利より高いケースが多いので、一度見直してみるとよいでしょう。
これから借りる人は「変動金利2%」まで耐えられるかが分かれ目
これから住宅ローンの利用を検討している人にとって、固定金利よりも適用金利が低い変動金利は大きな魅力を感じるかもしれません。ただし、変動金利は「借りたあとに金利が上がった場合、本当に返していけるか?」を事前によく考えておくことが大切です。野村総合研究所(NRI)の予測では、日銀の物価目標が達成された場合、政策金利は最終的に2%前後まで上がる可能性があるとしています。
つまり、政策金利の影響を受けやすい変動型住宅ローンの金利も、年2%に近づくリスクがあるということです。そのため、余裕を持った返済を心掛けるためにも金利が2.0%まで上がったケースはもちろん、できれば月々の返済額が1.5倍近くになったケースでも返済できるかをシミュレーションしておくことをおすすめします。そのうえで余裕を持った資金計画や固定金利を含めた選択肢を検討してみてください。
05変動金利年2%で返済額シミュレーションしてみよう
それでは、実際に金利が上昇した場合における借入金額別の毎月の返済額(元利均等返済)をシミュレーションしてみたので、参考にしてください。
借入金額3000万円の場合における毎月の返済額
| 借入期間 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 金利 | 35年 | 40年 | 45年 | 50年 |
| 0.50% | 7万7875円 | 6万8971円 | 6万2051円 | 5万6520円 |
| 0.75% | 8万1235円 | 7万2362円 | 6万5474円 | 5万9975円 |
| 1.00% | 8万4685円 | 7万5856円 | 6万9012円 | 6万3557円 |
| 1.25% | 8万8225円 | 7万9453円 | 7万2665円 | 6万7267円 |
| 1.50% | 9万1855円 | 8万3151円 | 7万6432円 | 7万1101円 |
| 1.75% | 9万5573円 | 8万6950円 | 8万310円 | 7万5059円 |
| 2.00% | 9万9378円 | 9万847円 | 8万4299円 | 7万9137円 |
借入金額4000万円の場合における毎月の返済額
| 借入期間 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 金利 | 35年 | 40年 | 45年 | 50年 |
| 0.50% | 10万3834円 | 9万1961円 | 8万2735円 | 7万5360円 |
| 0.75% | 10万8313円 | 9万6483円 | 8万7298円 | 7万9966円 |
| 1.00% | 11万2914円 | 10万1142円 | 9万2016円 | 8万4743円 |
| 1.25% | 11万7634円 | 10万5938円 | 9万6887円 | 8万9689円 |
| 1.50% | 12万2473円 | 11万868円 | 10万1910円 | 9万4802円 |
| 1.75% | 12万7431円 | 11万5933円 | 10万7081円 | 10万79円 |
| 2.00% | 13万2505円 | 12万1130円 | 11万2398円 | 10万5516円 |
借入金額5000万円の場合における毎月の返済額
| 借入期間 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 金利 | 35年 | 40年 | 45年 | 50年 |
| 0.50% | 12万9792円 | 11万4951円 | 10万3418円 | 9万4200円 |
| 0.75% | 13万5392円 | 12万604円 | 10万9123円 | 9万9958円 |
| 1.00% | 14万1142円 | 12万6428円 | 11万5021円 | 10万5929円 |
| 1.25% | 14万7043円 | 13万2422円 | 12万1109円 | 11万2112円 |
| 1.50% | 15万3092円 | 13万8586円 | 12万7387円 | 11万8503円 |
| 1.75% | 15万9288円 | 14万4917円 | 13万3851円 | 12万5098円 |
| 2.00% | 16万5631円 | 15万1412円 | 14万498円 | 13万1895円 |
上記表のように、同じ借入金額であっても金利が高く、借入期間が短いほど毎月の返済額は増えます。
例えば、借入金額3000万円、借入期間35年の場合、金利0.5%のときの毎月の返済額は7万7875円ですが、同じ条件で金利が2.0%になると約1.28倍の約9万9378円です。
また、借入期間が長いほど毎月の返済額は減る反面、総返済額は増えるので資金計画を立てるときは注意してください。
06トランプ関税は住宅ローンの金利にも影響!世界情勢と金融政策を注視しよう
2025年4月から始まったトランプ関税は、日本経済だけでなく、国内の住宅ローン金利にも間接的な影響を及ぼしています。これから住宅ローンを利用する人は万が一のことを考え、将来の金利上昇や為替変動だけでなく、金融機関の審査姿勢が厳しくなることも想定しておいたほうがよいでしょう。資金計画を立てるうえで大切なのは目先の金利の上下に振り回されるのではなく、「今の家計で無理なく返せるかどうか」を軸にして判断することです。
そのうえで必要に応じて借り換えや金利タイプの変更などを選択肢として検討しておくと余裕を持った資金計画を立てられます。住宅ローンを安心して利用するためにも、まずは自分にとって無理のない借入額や毎月の返済額を知ることから始めてみてはいかがでしょうか。 当サイト内には、住宅ローンの予算作成に役立つ便利な「住宅ローンシミュレーター」や、審査が不安な人でもいくらまで借りられるかすぐにわかる「スゴ速 住宅ローン保証審査」というサービスがそろっているので、ぜひ試してみてください。

監修:新井智美
CFP®/1級ファイナンシャル・プランニング技能士
プロフィール
トータルマネーコンサルタントとして個人向け相談の他、資産運用など上記相談内容にまつわるセミナー講師を行う傍ら、年間100件以上の執筆・監修業務を手掛けている。
関連キーワード