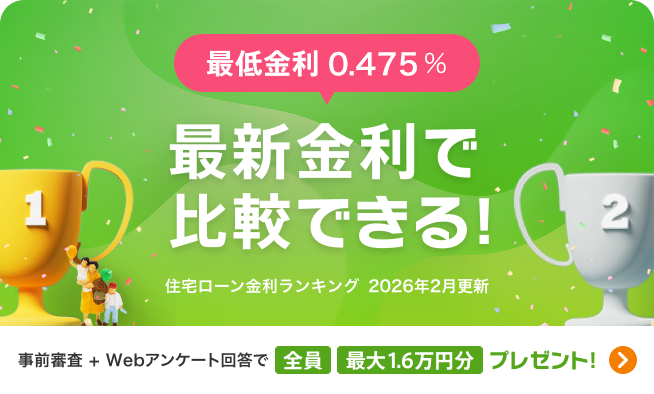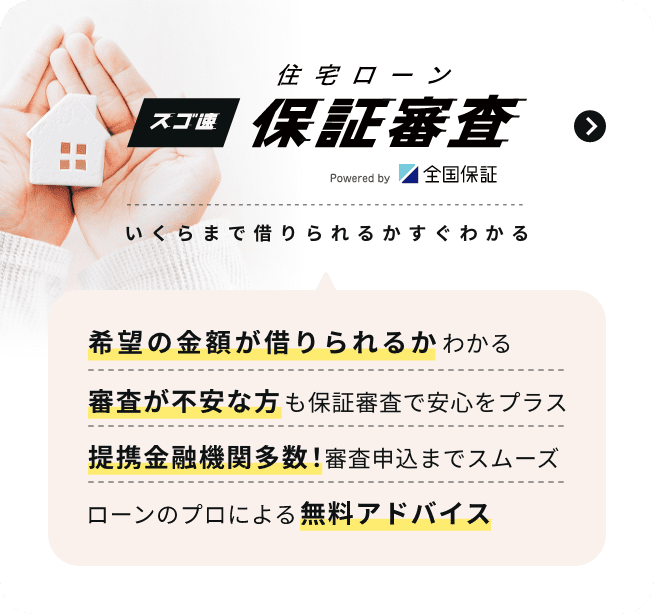2025年、引っ越し費用が高騰!タワマン購入者も要注意、対策方法も解説
「念願のマイホームを購入!いよいよ引っ越し」と思っていたら、想像以上に引っ越し費用が高かった――そんな驚きの声が増えています。特に2025年は、ドライバー不足や物流費の上昇といった背景から、引っ越し費用が過去最高水準まで高騰する可能性が指摘されています。マイホーム購入と並行してしっかり準備をしないと、引っ越し費用だけで大幅に予算オーバーしてしまうかもしれません。 特に注意したいのが、タワーマンションへの引っ越しです。タワーマンションでの作業は、エレベーターの制限や搬入ルールの厳しさなど、特有の条件によって引っ越し業者に支払う追加コストが発生しやすく、通常よりも慎重な計画が必要といえます。 本記事では、2025年の引っ越し費用が高騰している背景を解説するとともに、タワーマンションの引っ越しが高くなりやすい理由、その対策などを詳しく紹介します。
01なぜ引っ越し費用が高騰しているのか?
引っ越し比較・予約サイト「引越し侍」によると、2024年3月における家族の引っ越し費用は平均22万8106円で、前年に比べて約12.4%上昇しました。2021年以降、引っ越し費用相場は右肩上がりで、2025年は過去最高になると見込まれています。歴史的な高騰の背景にあるのは、物流業界の人手不足や繁忙期の需要増などです。
「2024年問題」で深刻化するドライバー不足
2025年の引っ越し費用高騰の大きな要因として挙げられるのが、物流業界の「2024年問題」です。
2024年問題とは、2024年4月1日から、働き方改革関連法による時間外労働の年間960時間上限規制が、トラックドライバーにも適用されたことに起因する、物流に関わる諸問題のことです。
時間外労働の上限設定で、これまで長時間労働に頼ってきた物流業界では、対応できる案件数が減少しています。引っ越し業者でもドライバー不足が深刻化しており、次のような問題が生じています。
- 業者あたりの対応できる件数が減り、需要に供給が追いつかなくなる
- ドライバーの賃金上昇分が引っ越し費用に転嫁される
- 長距離引っ越しのコスト増が顕著で、引っ越し距離が長いと追加料金が発生しやすくなる
上記の問題の結果、過去最高水準といわれるほど、引っ越し費用が高騰しているのです。
繁忙期の引っ越し需要の増加
特に、3〜4月の繁忙期における引っ越し費用が高騰しています。この時期は、新年度のスタートに合わせて引っ越しする人が多く、例年引っ越しの依頼が混み合います。そこに、先ほどの2024年問題が追い討ちとなって、かつてないほどに値上がりしている状況です。
引っ越しの繁忙期は上記の3〜4月と、秋の転勤シーズンにあたる9〜10月です。繁忙期に関しては、早めに予約をしないと、予約のタイミングによっては既に予約が埋まっており、引っ越しができないリスクさえあります。予約できずに「引っ越し難民」となった人々は、急きょ高額な引っ越し業者に依頼せざるをえないケースも多いため、ますます価格は高くなっていきます。
繁忙期を避ければ引っ越し費用を抑えることはできるものの、進学や転勤などが春に集中する傾向は変わらないため、現状では費用の高騰は不可避です。
ガソリン代・物価上昇の影響
燃料費や物価の上昇も、2025年の引っ越し費用を押し上げる大きな要因となっています。
特に、ガソリン代やダンボール・梱包資材などは引っ越し作業に欠かせないものの、価格が高騰しており、業者はこれらのコスト増を吸収しきれず、見積もり額や基本料金の引き上げにつながっています。
とりわけ、ガソリン代が高くなる長距離の引っ越しでは、費用がさらに高額になりやすい状況です。
02タワーマンションの引っ越し費用が高額になりやすい理由
タワーマンションは利便性の高さや高級感などから人気ですが、引っ越し費用が割高になりやすい点がネックです。なぜ、タワーマンションの引っ越し費用は高額になるのか、理由を見ていきましょう。
エレベーターの使用制限
タワーマンションでは、引っ越しの際に住民用のエレベーターを自由に使えないことが多く、荷物専用のエレベーターを事前に予約する必要があります。場合によっては、住民用エレベーターを使う際にも事前の申請や予約が必要です。
もし希望日に予約が取れないと、引っ越し日を変更しなければならない可能性もあるため、早めの確認と手配が大切です。
管理組合規定の厳格化
物件によっては、管理組合の規定で、利用できる引っ越し業者が2~3社に限定されている場合があります。依頼する側からすると業者の競争が少ないため、料金が割高になるケースもあります。
さらに、作業時間やエレベーターの使用時間に関して、厳しいルールが設けられている物件もあります。こうした物件では、早朝や夜間の作業ができないので、作業する時間帯によっては追加料金を請求されやすくなるでしょう。
作業時間の長さ
高層階になるほど、地上との往復分だけ作業時間が長くなり、人件費も増える傾向があります。作業時間の長さによって、追加料金が発生する業者もあるため注意が必要です。
物件によっては、入口付近まで大型トラックの乗り入れができないケースもあります。その結果、軽トラックなどの小さな車両に荷物を移し替えなければならず、費用が上乗せされることもあるでしょう。
駐車スペースの問題
タワーマンションの多くは、敷地内の駐車スペースの数が限られています。長時間駐車することが難しく、荷物の搬入に制限がかかるケースも考えられます。場合によっては、作業を複数回に分けざるを得ず、結果的に費用がさらにかさむ場合もあるのです。
03タワーマンションの引っ越しをスムーズに行うためのポイント
前述のとおり、タワーマンションへの引っ越しは、通常の引っ越しよりも時間や手間、費用がかかります。引っ越し費用が高騰している状況では、次に挙げる事前準備が重要です。
タワーマンションへの引っ越し経験が豊富な業者を選ぶ
タワーマンション特有のエレベーター制限や搬入ルールに詳しい業者を選ぶことで、スムーズな引っ越しが可能になります。オプションでタワーマンションの管理人に対する引っ越し申請の手続きを代行してくれる業者もあるので、あらかじめ確認しておくとよいでしょう。
【タワーマンションにおける引っ越し業者選びのポイント】
- タワーマンション専門プランのある業者を優先する
- 過去の口コミや評判をチェックする
- 複数社で相見積もりを取り、費用やサービス内容を比較する
タワーマンションに特化した業者は、追加費用が発生しやすいポイントや注意点を把握しているため、事前に対策を講じやすく、結果として費用を抑えやすいというメリットがあります。
なお、物件の管理規約で指定業者が定められている場合もあるため、事前に確認しておくと安心です。
搬入する荷物の量を減らす
タワーマンションは、駐車場から入口までの距離が長く、専用エレベーターでの往復が必要になることから、運搬に時間がかかりがちです。
そのため、不要な物品は引っ越し前に処分しておき、荷物をなるべくコンパクトにまとめておきましょう。荷物が少なければ、作業効率が上がり、結果的に引っ越し費用の節約につながります。
大型家具・家電の搬入計画を立てる
大型の家具や家電を運ぶ際、エレベーターや廊下、ドアのサイズによっては、室内まで搬入できない恐れがあります。大型アイテムの運搬が必要な場合、事前に寸法を測っておき、搬入可能かチェックしておくことが必須です。
エレベーターに入らない場合には階段を使用することになりますが、高層階となると現実的ではありません。クレーン車でベランダから搬入するなど、特別な手配が必要となるケースも。ただ、高層階はそもそもクレーンが届かないので、ベランダからの搬入も難しいでしょう。
それでも新居に運び込みたい場合は、家具や家電の分解・組み立てサービスを利用するのが一般的です。分解・組み立てサービスは、多くの引っ越し業者がオプションで提供しています。特に、ピアノを運び入れたいときは、専門業者に依頼して分解・組み立てしてもらう必要があります。
このように、大型家具・家電の搬入には大きな手間と費用がかかるため、引っ越しを機に新居で新たに購入することも検討すべきでしょう。
共用部分の養生(傷防止対策)をしっかり行う
タワーマンションのエントランスや廊下、エレベーターなどの共用部分は、引っ越し作業中に傷つけないよう、適切に養生を行う必要があります。物件によっては、管理人から養生について指示を受けたり、作業後に廊下の傷チェックを受けたりすることもあります。
この点からも、タワーマンション特有のルールや養生に慣れている、専門の引っ越し業者に依頼するのが安心です。
04タワーマンションへの引っ越しは計画的に!
ここまで見てきたように、タワーマンションへの引っ越しは、管理規約の確認やエレベーターの予約、タワーマンションの引っ越しにノウハウのある引っ越し業者の選定など、事前準備が重要です。新生活をスムーズにスタートするためにも、搬入ルールを遵守し、近隣住民への配慮を怠らないようにしましょう。
また、近年は引っ越し費用が高騰しています。マイホーム購入時は、住宅ローン返済額にばかり目が行きがちですが、引っ越し費用も大きな支出です。想定外に高い出費で資金繰りが厳しくならないよう、引っ越し費用の最新相場を踏まえた、余裕のある資金計画を立てる必要があります。繁忙期とオフシーズンの費用差を把握しておくことも、資金計画に役立つでしょう。時期にこだわらないなら、オフシーズンに引っ越すことで費用を抑えられます。
資金計画を立てるにあたっては、自分の年収や返済能力をベースに、借入可能額や毎月返済額をシミュレーションしておきましょう。マイホーム検討の第一歩として、当サイトの住宅ローンシミュレーターをぜひご活用ください。
-
借入可能額シミュレーター
今の家賃と同じ額のローン返済だと、いくらまで借り入れできるのか試算できる -
毎月の返済額シミュレーター
買いたい物件の価格から、毎月の支払い額がいくらになるか試算できる

監修:新井智美
CFP®/1級ファイナンシャル・プランニング技能士
プロフィール
トータルマネーコンサルタントとして個人向け相談の他、資産運用など上記相談内容にまつわるセミナー講師を行う傍ら、年間100件以上の執筆・監修業務を手掛けている。