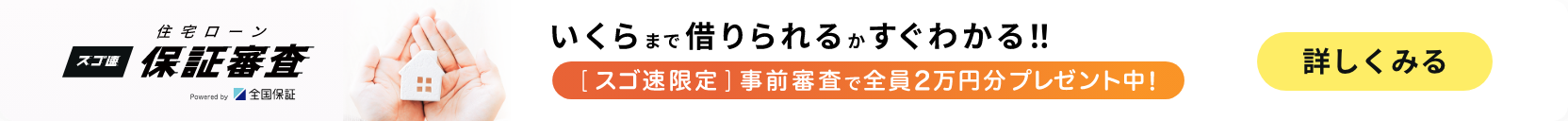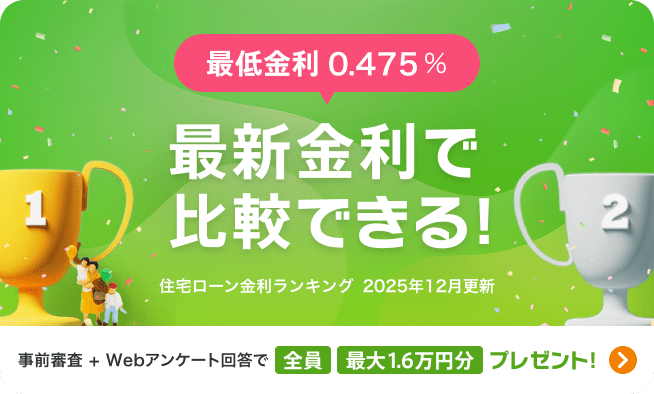控除対象になる床面積40平米ってどのくらい?「坪」や「畳」など単位の違いや理想の住宅の広さを解説
2021年度の税制改正で、住宅ローン控除の適用対象の床面積が「40平米(40平方メートル)以上」に緩和されたことが話題になりましたが、「40平方メートル」がどのくらいの広さなのか、すぐにイメージできますか?今回は、「平方メートル」や「坪」、「畳(じょう)」など、住まいに関する広さの単位について改めて確認するとともに、理想の「広さ」について考えてみましょう。
01住まいの広さを測る単位
日本では住宅の広さを測る単位として、主に「畳(帖)」「平方メートル」「坪」の3つが使われています。不動産売買契約書では原則として平方メートルが使われますが、広告やパンフレットなどでは「畳」や「坪」が使われていることも珍しくありません。
平方メートル(㎡)は国際的に広く用いられている単位で、1平方メートルは1辺の長さが1メートルの正方形の面積に当たります。一方、「畳(帖)」と「坪」は、いずれも日本独自の単位です。それぞれの広さは下記のようになります。
| 単位 | 広さ |
| 平方メートル | 1辺の長さが1メートルの正方形の面積 |
| 畳(帖) | 畳1枚分の面積。約1.62平方メートル |
| 坪 | 約3.3平方メートル。ほぼ畳2枚分の広さ |
2021年度の税制改正で住宅ローン控除の対象が「床面積40平方メートル以上」となりましたが、40平方メートルを「畳」で表すと25畳(約40.5平方メートル)、坪で表すと約12.5坪(41.25平方メートル)よりそれぞれ少し広い大きさになります。
なお、「畳」は畳1枚分の広さとされていますが、地域等によって1枚分の広さは異なります。例えば、西日本を中心に使われる「京間」と呼ばれる畳は約1.82平方メートル、東海地方を中心に使われる「中京間」は約1.65平方メートル、東日本を中心に使われる「江戸間」は約1.55平方メートル、地域に関わらず団地やマンションで使われる「団地間」は約1.44平方メートルです。したがって、同じ「6畳」と表記されている部屋でも、実際の広さが異なることになり、不動産取引においてトラブルの原因となってしまいかねません。
そこで不動産公正取引協議会では、畳1枚の広さ(=1畳)について1.62平方メートル(各室の壁芯面積を畳数で除した数値)以上とする規約を設けています。つまり、壁や柱の厚みの中心線で測られる壁芯面積で16.2平方メートル以上ある部屋であれば、「10畳」と表記して良いことになります。ちなみに、ここで言う「畳」はあくまでも単位であり、畳を敷いている部屋でなければ「●畳」と表示できないということではありません。
また、「畳」ではなく「帖(じょう)」と表記される場合もありますが、意味は同じです。「帖」は畳敷きの和室と、フローリングなどの洋室を区別するために使われるようになったと言われており、「畳」と「帖」とで表す広さは同じです。
02豊かな生活に必要な広さはどのくらい?
では、快適な住まいにはどのくらいの広さが必要なのでしょうか?一般的には「狭いよりも広い住まいの方が快適だ」と考える人が多いかもしれませんが、広い住まいにも「掃除が大変」、「冷暖房の効率が悪い」などの弱点がありますし、一部には「狭い方が落ち着く」という人もいるため、一概に「住まいは広ければ広いほど快適」とは言えません。「どのくらいの広さの家を選べば良いのかわからない」という人は、住宅面積の目安として国土交通省が「住生活基本計画」の中で示した「居住面積水準」を参考にすると良いでしょう(※1)。「居住面積水準」には最低居住面積水準(健康的で文化的な生活のために最低限必要な面積)と誘導居住面積水準(豊かな生活を実現するために必要と考えられる面積)とがあり、家族の人数によってそれぞれ以下のようになっています。
最低居住面積水準
健康的で文化的な住生活の基礎として必要不可欠な住宅の面積。
単身者は25平方メートル、2人以上の世帯は「10平方メートル×世帯人数+10平方メートル」とされています。
最低居住面積水準を基にした世帯人数別の面積例
| 単身 | 2人 | 3人 | 4人 | |
| 面積水準 (平方メートル) | 25 | 30 【30】 | 40 【35】 |
50 【45】 |
【 】は未就学児が1名いる場合の面積
誘導居住面積水準
豊かな住生活の実現の前提として、多様なライフスタイルを想定した場合に必要と考えられる住宅の面積。地域や住宅の種類別に、それぞれ以下のようになっています。
一般型誘導居住面積水準(一般地域の戸建て住宅を想定)
単身者は55平方メートル、2人以上の世帯は「25平方メートル×世帯人数+25平方メートル」とされています。
一般型誘導居住面積水準を基にした世帯人数別の面積例
| 単身 | 2人 | 3人 | 4人 | |
| 面積水準 (平方メートル) | 55 | 75 【75】 | 100 【87.5】 |
125 【112.5】 |
【 】は未就学児が1名いる場合の面積
都市居住型誘導居住面積水準(都市部の共同住宅を想定)
単身者は40平方メートル、2人以上の世帯は「20平方メートル×世帯人数+15平方メートル」とされています。
都市居住型誘導居住面積水準を基にした世帯人数別の面積例
| 単身 | 2人 | 3人 | 4人 | |
| 面積水準 (平方メートル) | 40 | 55 【55】 | 75 【65】 |
95 【85】 |
【 】は未就学児が1名いる場合の面積
この水準を目安として考えると、たとえば3人家族で「豊かで快適な生活」を実現するには、一戸建てなら100平方メートル、都市部のマンションなら75平方メートルが必要になるということになります。
03実際にはどのくらいの広さの家を買う人が多いの?
では、実際に住宅を購入した人はどのくらいの広さの家を買っているのでしょうか?
独立行政法人住宅金融支援機構が住宅ローン「フラット35」の利用者を対象に行った調査(※2)で、2020年4月から2021年3月に購入した住宅の床面積の平均は、注文住宅が124.4平方メートル、中古一戸建住宅が113.2平方メートル、建売住宅が101.1平方メートル、新築マンションが66.2平方メートル、中古マンションが67.9平方メートルでした。また、購入時の家族の人数は、注文住宅が3.6人、中古一戸建と建売住宅が3.1人、マンションは新築・中古ともに2.4人でした。
購入した住宅面積と家族人数の平均
| 住宅の種類 | 面積の平均 | 家族の人数の平均 |
| 注文住宅 | 124.4平方メートル | 3.6人 |
| 中古一戸建住宅 | 113.2平方メートル | 3.1人 |
| 建売住宅 | 101.1平方メートル | 3.1人 |
| 新築マンション | 66.2平方メートル | 2.4人 |
| 中古マンション | 67.9平方メートル | 2.4人 |
先ほど紹介した国土交通省が示した誘導居住面積水準では、一般的なエリアの戸建て住宅で3人家族が豊かな暮らしを実現するのに必要な面積は「100平方メートル」でした。したがって、一戸建て住宅の場合は、本調査の対象者は豊かな暮らしを実現するのにおおむね十分な広さの住まいを手に入れたことになります。一方、マンションの場合は、誘導居住面積水準の指標は3人暮らしで「75平方メートル」でしたので、新築・中古共に「豊かな暮らしを実現するのに必要な面積」には少し足りないようです。
同調査によるとマンションの床面積の平均は、2015年以降6年連続で縮小しています。特に首都圏ではマンションのコンパクト化が進んでいること、マンション価格の高騰が続いていることなどから、国土交通省が「豊かな暮らしに必要な面積」としている広さのマンションを確保するのは難しくなっていると言えそうです。
※2 出典:独立行政法人住宅金融支援機構「2020年度フラット35利用者調査」
実際に住宅の購入を検討する際には、どのぐらい住宅ローンが借りられるのかを確認し、その金額内で希望の広さの物件が買えるエリアを探してみると良いでしょう。「借入可能額シミュレーター」では現在の家賃や希望する返済期間などを入力するだけで借入可能額の目安が確認できます。

監修:相山華子
ライター、OFFICE-Hai代表、2級ファイナンシャル・プランニング技能士
プロフィール
1997年慶應義塾大学卒業後、山口放送株式会社(NNN系列)に入社し、テレビ報道部記者として各地を取材。99 年、担当したシリーズ「自然の便り」で日本民間放送連盟賞(放送活動部門)受賞。同社退社後、2002 年から拠点を東京に移し、フリーランスのライターとして活動。各種ウェブメディア、企業広報誌などで主にインタビュー記事を担当するほか、外資系企業のための日本語コンテンツ監修も手掛ける。20代で不動産を購入したのを機に、FP(2級ファイナンシャル・プランニング技能士)の資格を取得。金融関係の記事の執筆も多い。
関連キーワード