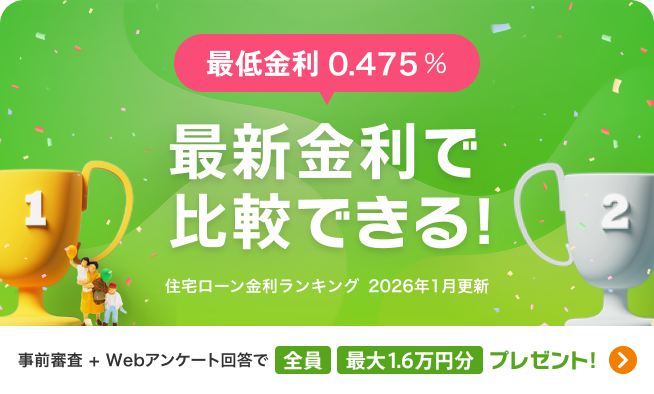高市政権で株価5万円台へ!住宅ローンを組む前に知っておきたい4つのポイント
2025年10月27日、日経平均株価は史上初めて5万円を突破しました。国内では「景気が上向くかもしれない」という期待感が広がりつつあり、財政出動を重視する高市政権の誕生によって、その流れがさらに加速するとの見方も出ています。 こうした好景気への期待は株式市場だけでなく、不動産市場にも波及しています。しかし、住宅購入を検討する人にとっては、必ずしも「株高=追い風」とは限りません。株価が上がる局面では地価が上昇しやすく、住宅価格や住宅ローンの返済計画に影響する可能性があるためです。 そこで本記事では、これから住宅ローンを検討する方に向けて、「今の株高が住宅購入にどう影響するのか」や「今後の借り入れで注意したいポイント」についてわかりやすく解説します。
- 01高市政権の誕生で、なぜ株価が5万円を超えたのか?
- 景気を下支えする“積極的な財政政策”への期待
- 「低金利が続く」との見方が株価を後押し
- 円安で輸出企業の業績が好調に
- 02なぜ「株価」が上がると「地価」も上がるのか?
- 03これから住宅ローンを借り入れる人が受ける“3つの影響”
- 家の価格が上がる
- 金利が上がる可能性もある
- 固定資産税などの負担が増える可能性がある
- 04住宅ローンを借り入れる前に確認しておきたい4つのポイント
- 返済できる金額を「今」ではなく「未来」から考える
- 返済シミュレーションを複数パターンで行う
- 人気エリアにこだわりすぎず、選択肢を広げてみる
- 長く心地よく暮らせる家を選ぶ
- 05株価や地価が上がっている今こそ、マイホーム購入は「焦らず、冷静に」判断しよう
01高市政権の誕生で、なぜ株価が5万円を超えたのか?
高市政権の誕生をきっかけに、なぜ株価が5万円を超えたのでしょうか。もともと日経平均株価は国内のインフレ基調とともに上昇傾向にありましたが、2025年10月21日の高市政権誕生からその動きに拍車がかかりました。
それは高市政権が政策方針として掲げた「経済最優先」が投資家の期待を集めたことと関係しています。そこで、まずは直近の株価上昇を支える背景について解説します。
景気を下支えする“積極的な財政政策”への期待
高市首相は、これまで首相就任前から「政府が財政支出を拡大し、景気回復を図る」という積極的な財政政策を一貫して主張してきました。特に、防災インフラの強化やデジタル分野への投資など、成長につながる分野への支出拡大が想定されており、市場では「政策が本格的に動き出すのではないか」という期待感が高まっています。
実際にどこまでの対策が実行されるかはまだわかりませんが、仮に大規模な財政出動が行われれば、大企業を中心に業績面でプラスに働くでしょう。そうした目論見から、「企業の売上が伸びそう」「個人収入が増えて消費が拡大するかもしれない」という期待感が高まっていて、株式市場の上昇につながっています。
「低金利が続く」との見方が株価を後押し
近年の日本は消費者物価指数2%以上の上昇が続いていて、物価高に悩む消費者の声も強くなっています。本来、インフレ対策としては利上げが有効だとされ、実際に2024年3月のマイナス金利解除以降、日銀は緩やかな利上げを進めてきました。
しかし、高市政権は景気刺激策を優先すると考えられており、企業がお金を借りにくくなる利上げには消極的な立場です。そのため、「現在の低金利環境がまだしばらく続くだろう」という予想が強まり、投資家に安心感を与え株価上昇を支える要因となっています。
ただし、10月の金融政策決定会合で日銀の植田総裁は「物価と賃金の見通しが実現する確度が高まっている」と、慎重ながらも今後の利上げの可能性に言及しました。市場では「春闘の結果が出てくる来年春にも金利を引き上げるのでは」と予想する声もあり、低金利環境がいつまでも続くという前提が変化し始めているのも事実です。
現時点で急速な金融引き締めは見込まれていないものの、「近いうちに金利がある程度上がるのは避けられない」という意識が投資家の間にも広がっており、こうした思惑が今後の株価や不動産市場の動きに影響を与える可能性も一部では指摘され始めています。
円安で輸出企業の業績が好調に
これまで日本は欧米に比べて低金利だったこともあり、為替市場では円安が進んでいました。円安になると、海外で得た収益を円に換えたときの金額が増えるので、主に自動車や電機メーカーといった輸出比率の高い企業にとって追い風になります。こうした業績への期待感が強まり、日本企業の収益見通しが上方に評価されたことで、株式市場全体にも活気が広がりました。
さらに、円安局面では海外投資家にとって日本株が相対的に割安に映ります。自国通貨ベースでは購入コストが下がるため、「安く買える日本株」に資金が流入しやすくなり、この海外勢の買いも日経平均株価の押し上げ要因となりました。
02なぜ「株価」が上がると「地価」も上がるのか?
では、冒頭で述べたように、なぜ株価が上がると地価も上がりやすいのでしょうか。それは株価が上がることで企業の利益や手元の資産が増えて「お金を使いやすいムードが広がる」ため、全体的な購買力が増加し、結果として不動産需要も高まるからです。
すでに不動産市場ではその影響が出ていて、実際に2025年の路線価(土地の評価額)は全国平均で前年比2.7%も上昇しています。特に都市部は外国人投資家による需要も高く、東京都では前年比で8.1%も上昇するなど地価の上昇になかなか歯止めがかからない状況です。
高市政権の誕生で円安、株高がさらに加速する可能性があり、「株高からの地価上昇」という流れもしばらく続くことが懸念されています。
03これから住宅ローンを借り入れる人が受ける“3つの影響”
ここまで日経平均株価が上昇している理由と、それに伴う地価上昇の原因について解説してきました。では、これから住宅購入を予定している人は具体的にどのような影響を受けるのでしょうか。ここからは株高・地価上昇が住宅ローンに与える影響について解説していきます。
家の価格が上がる
まず考えられる影響は、住宅価格そのものの上昇です。住宅価格は主に「建物の建設費」と「地価」の2つで成り立っており、建設需要が高まると建築費用も増加します。さらに、地価が上がると必然的に住宅価格総額も上昇してしまいます。
デフレ時代であれば、「もう少し待てば安くなるかも」という考え方が通用していたケースもありましたが、現在のようにインフレが続く状況だと様子を見ているうちにかえって支払い総額が上がってしまうことも考えられます。
同じエリアの土地でも後から購入した人のほうが高値で買うケースもあるため、購入タイミングの見極めが重要です。
金利が上がる可能性もある
次に気を付けておきたい影響は「金利動向」です。一般的に株価が上がって景気が良くなりすぎると、過熱感を冷ますために日銀は金利を上げる傾向にあります。お金を借りたときのコスト(支払い利息)を増やすことで企業や個人の資金調達を抑え、お金を使わせないようにして物価を調整するというわけです。
実はすでに住宅ローンではこの影響が出始めていて、固定金利はわずかではあるものの上昇傾向です。「低金利の今のうちに住宅ローンを借りる」という判断も1つの考え方だといえます。
固定資産税などの負担が増える可能性がある
3つ目は、税金などの住宅を購入するとかかるランニングコストの上昇です。特に毎年3月下旬ごろに発表される公示地価は固定資産税や都市計画税など、住宅を所有すると毎年支払わなければいけない税金を計算するうえでの参考数値となっています。つまり、公示地価が上がると、支払う税金も増える可能性が高いということです。
住宅を購入するときは、つい住宅ローンの毎月の返済額だけを重視して考えがちですが、実際に購入したあとにかかる税金などの「維持費」を念頭に入れておくのも忘れないようにしましょう。
04住宅ローンを借り入れる前に確認しておきたい4つのポイント
これから住宅ローンを契約する人が受ける3つの影響については理解できたでしょうか。経済政策に力を入れる高市政権下では住宅価格や金利などが今後も上がる可能性が高まっています。
そこで、最後に住宅ローンを借り入れる前に確認しておきたい4つのポイントについて整理するので、一緒に確認しましょう。
返済できる金額を「今」ではなく「未来」から考える
住宅ローンは一般的に30年以上の長期間にわたる契約です。そのため、「今の年収」だけでなく、「将来の支出やライフイベント」を見据えた金額設定が大切になります。金融機関が示す借入上限額は、あくまでも「借りられる金額」であり、「契約者が返せる金額」とは別物です。
実際に返済できる金額は教育費や介護にかかるお金はもちろん、住宅の修繕費、将来の転職による収入の変化など、人それぞれのライフプランで大きく異なります。そのため、現在の家計状況だけでなく、10年後や20年後も無理なく返済できる計画を立てることが重要です。「返せる金額」とは、あくまでも未来の自分や家族を守るための安心ラインであることを心掛けてください。
返済シミュレーションを複数パターンで行う
返せる金額を検討するときは事前に自分の年収や借入金額、金利などからシミュレーションしておくことが大切です。しかし、ここで忘れてはいけないのが「返済シミュレーションは現在の数字だけを出すものではない」ということです。たとえば、いざというときに備えて「金利が0.5%上がったとき」「ボーナスがなくなったとき」「子どもの習い事が増えたとき」など、条件を変えて様々なパターンを想定しておくことが望ましいといえます。
仮に返済額が月々1万円の違いでも、30年間の返済ではトータルで300万円以上の差になることも考えられます。返済シミュレーションは「金利や収入が変化したときに、暮らしの余裕がどう変わるかを知るためのツール」という意識を持ち、複数のパターンを試して「どんなときでも無理なく返せるライン」を見つけておきましょう。
人気エリアにこだわりすぎず、選択肢を広げてみる
近年、住宅価格が上昇していますが、今後もしばらくはその状況が続くと予想されています。特に駅近や大型商業施設に近い人気エリアほど競争は激しく、土地価格も高騰しがちです。通勤・通学のことを考えて「特定の路線沿い」や「駅から徒歩10分圏内」など、「絶対にこれだけは譲れない」という条件にこだわり過ぎると、理想の住宅に出会うチャンスを逃すかもしれません。
自分に合った住宅を探すためには本来の希望よりも少し選択肢を広げてみると、価格や広さ、日当たりなどの条件でバランスのよいエリアの土地が見つかることも多いでしょう。最近は郊外でも交通アクセスや商業施設が充実した地域も増えているため、特に物件探しを始めたばかりのころは、あまり場所にこだわりすぎず「どんな暮らしをしたいか」から考えたほうが、予算と満足度の両方を満たす住宅が見つかりやすいでしょう。
長く心地よく暮らせる家を選ぶ
住宅を探すときは価格やデザイン性を重視してしまいがちですが、多くの人にとって一生の買い物であることを考えると「10年後、20年後も快適に暮らせるか」という観点を持つことも重要です。住宅ローンは完済まで数十年かかるので、その間のことを考えてメンテナンス性や断熱性、立地の安全性も考慮しましょう。
断熱性の高い住宅は冷暖房費が抑えられて家計にやさしく、駅や病院、学校などへのアクセスがよい場所にある住宅は将来の資産価値向上につながりやすいです。住宅探しをするときは現在の価格だけでなく、「暮らしが持続するか」「将来的な資産価値はどうなるか」といった長期的な目線を持つことが後悔しないためのポイントになります。
05株価や地価が上がっている今こそ、マイホーム購入は「焦らず、冷静に」判断しよう
株価や地価が上がると、思わず「今のうちに買わなきゃ」と焦ってしまいがちですが、マイホームは勢いではなく、「将来にわたる暮らしの計画」で決めることが重要です。高市政権の誕生でさらにインフレが進む懸念もありますが、今こそ焦らず冷静に判断しましょう。
住宅ローンとは何十年という長い年月をかけて付き合うことになるので、安心して返せるラインを知るためにも将来を見据えた複数のシミュレーションを試しておくことをおすすめします。当サイト内には目的別に応じた「住宅ローンシミュレーター」があるので、自分の家計に合った「ちょうどいい借り方」を見つけるためにもぜひ活用してみてください。

監修:新井智美
CFP®/1級ファイナンシャル・プランニング技能士
プロフィール
トータルマネーコンサルタントとして個人向け相談の他、資産運用など上記相談内容にまつわるセミナー講師を行う傍ら、年間100件以上の執筆・監修業務を手掛けている。
関連キーワード