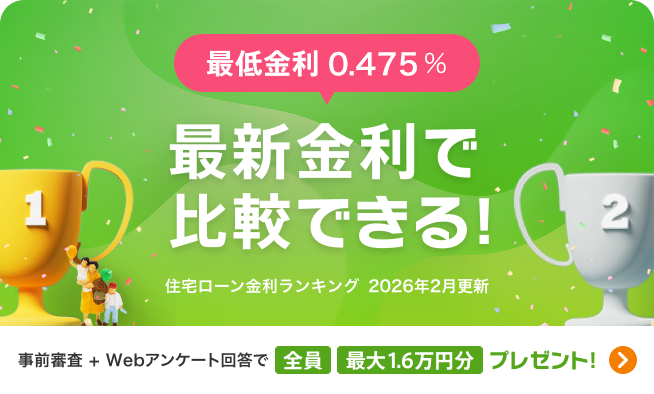住宅市場にねじれ──売りたい78%、買いたい26%…金利上昇が左右する価格動向
近年、日本の不動産市場は日銀の低金利政策を背景に活況を呈してきましたが、足元では需給バランスに変化が見られます。野村不動産ホールディングスの2025年7月の最新調査では、売却に前向きな人が多い一方、購入を検討する人は減少しており、市場心理に大きな乖離が生じていることが浮き彫りになりました。さらに、回答者の8割超が「金利は今後上昇する」と見ており、買い控えの傾向が強まる懸念も指摘されています。 こうした状況の中、不動産価格はこれからどのように動くのか、そして住宅ローンを借りる予定の人はどのような戦略をとるべきなのでしょうか。今回は最新調査をもとに、不動産市場の現状と今後の展望を解説します。
01売りたい78%、買いたい26%──鮮明になった住宅市場のねじれ
野村不動産ホールディングスが2025年7月に実施した「住宅購入に関する意識調査アンケート(第29回)」によると、「今、不動産は売り時だと思う」「どちらかと言えば売り時だと思う」と回答した人の割合は78.2%でした。前回の2025年1月(78.9%)からわずかに低下したものの、依然として売り手の意欲が非常に高い水準にあります。
一方で、「買い時だと思う」「どちらかといえば買い時だと思う」と回答した人の割合は26.2%にとどまり、前回調査より5.8%減少しました。同様の回答は2024年2月以降、減少傾向が続いており、購入に前向きな層が縮小していることがわかります。
以上の調査結果からは、売却を希望する人の割合が非常に高い一方で、購入を希望する人が大幅に減少しているという「住宅市場のねじれ」が鮮明になっています。こうした状況が長引くと、供給側の過剰感から不動産価格は抑制され、長期的な価格調整につながるかもしれません。
ただし、市場環境が変化して「買い時感」が回復すれば、価格を再び押し上げる要因ともなり得るでしょう。現在は需給バランスが偏っており、価格形成や市場動向への影響が懸念される状況だといえます。
02金利上昇を8割以上が予想、広がる買い控えムード
不動産の買い手が慎重になる背景には、今後の金利動向への不安があります。それは同調査の「今後、住宅ローン金利はどうなると思うか」という質問の結果からも明らかです。同質問では81.7%の人が「上がると思う」と回答しました。前回から6.2%減少したものの、4回連続で最多回答となっており、住宅ローン利用者・検討者の間で「金利上昇は避けられない」という見方が定着していることがわかります。
金利が上がると住宅ローンの毎月の返済額は増えるため、特に長期ローンを検討している世帯にとっては将来の金利上昇リスクを懸念せざるを得ないでしょう。その結果、売り手の意欲が高いにもかかわらず、買い手がついてこない「市場の停滞」が起こりやすくなっていて、この動きが長期化すれば不動産価格に値下げ圧力がかかる可能性も高まるでしょう。
03不動産価格の行方──上がる41.4%、下がる17.0%で二極化に
同調査では今後の不動産価格の展望についても質問しており、「上がると思う」と答えた人は41.4%でした。これに対し、「横ばいで推移すると思う」が29.6%、「下がると思う」が17.0%で、結果として46.6%の人が不動産価格の高止まり、もしくは下落を予想している結果です。
上がると思うと答えた人の理由としては、「資材・人件費の高騰」「円安による輸入コスト増」といった物価上昇による影響と、「投資マネーの流入」「都市部需要の底堅さ」という近年続いている活発な不動産需要を挙げています。一方で、下がると思うと答えた人は、「金利上昇による返済負担増」や「売り手の多さによる供給過多」「不透明な景気見通し」を理由に挙げており、不動産価格のピークを感じているようです。
「横ばいで推移すると思う」が3割近くを占めているように、現時点では価格を押し上げる要因と下押しする要因の間に決定的な決め手はなく、今後の不動産価格がどうなるかは不透明感が強い状態がしばらく続きそうです。
04これから住宅ローンを借りる人が備えるべき4つの視点
ここまで見てきたように、不動産市場の先行きは不透明感が増しています。そんな状況だからこそ、住宅ローンを検討する際に押さえておきたい4つの視点があるので、一緒に確認していきましょう。
相場を読むよりも資金計画を優先する
マイホームを目的に不動産を購入する人は、「価格が上がるか下がるか」を気にするよりも家計に合った返済計画の優先を第一に考えましょう。今後、不動産価格が上がるかどうかは誰にもわかりませんが、一時の上昇ムードが落ち着きつつあるのは確かです。
だからといって、物件の価格が下がるのを待っているばかりでは、希望する物件を他の人に先に購入されてしまうかもしれません。そのため、「いつ買うか」よりも「どう返すか」を重視してマイホーム選びをしたほうがスムーズな物件選びにつながり、新生活のスタートも切りやすくなるはずです。
住宅ローン返済は“返済比率30%以内”を崩さない
返済比率とは、年収に占める「年間返済額の割合」を指します。一般的に、住宅ローンの場合は25~30%以内に抑えるのが家計に無理のない範囲だといわれています。
不動産・住宅情報サービスを手掛けるLIFULL HOME’Sが実施した「住宅ローンに関する意識調査」によると、「世帯月収に占める返済比率1割以上2割未満」で「もっと借入額を減らせばよかった」と回答したのは17.7%でした。返済比率が高くなるにつれて後悔の割合は増加し、「2割以上3割未満」では24.5%、「3割以上」では39.1%にまで上っています。
この結果からも、返済比率30%を超えると生活の維持に無理が生じやすいことがわかります。逆に30%以内に抑えれば、金利や価格が変動しても生活基盤を崩しにくく、安心して返済を続けやすいといえるでしょう。
金利上昇に備えるなら固定金利や借入金額を工夫する
不動産価格の先行きは不透明感があるのに対して、金利はほとんどの人が上昇すると考えています。その対策としては、固定金利で返済額を安定させるのが有効です。たとえば、2025年9月時点でフラット35の最も多い金利は約1.9%、変動金利は金融機関によって違うものの約0.7%程度を推移しており、両者の差は年間約1.2%あります。
仮に借入金額4000万円、返済期間35年でそれぞれの毎月の返済額と総返済額を比較すると、以下のようになります。
| 金利タイプ | 毎月の返済額 | 総返済額 |
|---|---|---|
| 0.7%(変動) | 約11万円台 | 約4800万円 |
| 1.9%(全期間固定) | 約13万円台 | 約5600万円 |
今回のシミュレーションでは、毎月の返済額で約2万円、総返済額で約800万円も全期間固定型の支払いが高くなりました。しかし、変動型は金利上昇が進むと全期間固定型以上に返済額が増えるリスクがあり、返済計画の安定性を確保する意味では全期間固定型の「金利が変わらない」という特徴は魅力的です。
たしかに、変動金利には「返済額が5年間変わらない」「金利変更時も最大で前回の125%が上限」といったルールがある商品が多いものの、金利が急上昇すると利息分だけで毎月の支払いが終わり、元本の返済が後回しになる懸念もあります。そのため、固定金利を選択しない人は頭金を多めに用意したり、借入額を抑えたりするなど返済額の増加に備える戦略が重要となるでしょう。
いずれにしても、金利上昇局面においては金利タイプごとの特徴と数字を比較して、自分の家計やリスク許容度に合った選択をすることが大切です。
繰り上げ返済や借り換えを視野に入れて将来に備える
住宅ローンの返済は長期間にわたるので、契約時の条件で最後まで完済できるとは限りません。そのため、金利環境やライフスタイルの変化に対応できるような方法を考えておくことが、将来の安心につながります。
具体的には、繰り上げ返済や借り換えといった選択肢です。返済期間35年、借入金額4000万円、変動金利1%でローンを組んだ場合、5年後に100万円を繰り上げ返済するだけで総返済額を124万円削減可能(実際には金利が見直されるため、あくまで一定金利が続いた場合の参考値)です。
また、借入残高3000万円、返済期間残り25年のケースでは、金利1.5%における毎月の返済額は約11万9981円(総返済額約3599万円)ですが、金利1.0%のローンに借り換えると、毎月の返済額は約11万3062円(総返済額約3392万円)となり、毎月の返済額は約7000円、総返済額は約200万円も節約できます。
金利上昇リスクが高まると予想されるこれからの住宅ローンでは、環境や収入の変化に応じて返済途中でも柔軟に対応できる返済プランをあらかじめ想定しておきましょう。
05金利上昇局面で問われるのは、住宅ローンの無理のない返済!
最新の調査結果からは住宅市場で「売りたい人が多い一方で、買いたい人が少ない」というねじれが起きていることが鮮明になりました。また、8割を超える人が今後の金利上昇を予想するなど、市場の不透明感が高まりつつある状況です。不動産価格の行方を読むのは難しいタイミングなので、住宅ローンを検討する際は市場の動きよりも自分の家計に合った資金計画を優先してください。
当サイト内には目的別の各種シミュレーターがあり、月々の支払額から予算を考えたい人は「借入可能額シミュレーター」、毎月の支払いが気になる人は「毎月の返済額シミュレーター」がおすすめです。自分に無理のない返済額を知って、マイホーム探しをスムーズに進めるためにもぜひ試してみてはいかがでしょうか。

監修:新井智美
CFP®/1級ファイナンシャル・プランニング技能士
プロフィール
トータルマネーコンサルタントとして個人向け相談の他、資産運用など上記相談内容にまつわるセミナー講師を行う傍ら、年間100件以上の執筆・監修業務を手掛けている。