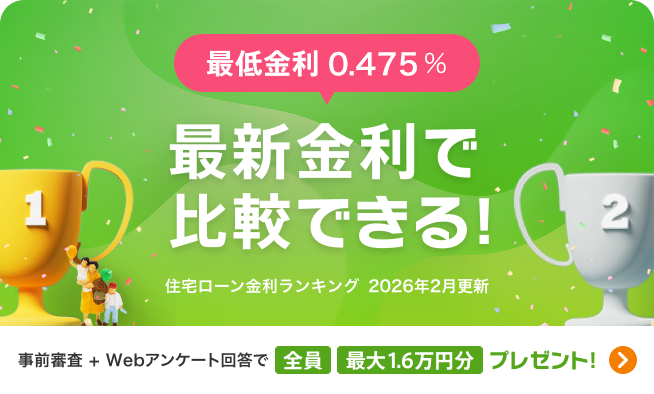高年収ほど悩む?「買えるのに満足できない」住宅購入ストレスとは
近年続く不動産価格上昇により、多くの地域、特に東京都心部では「かなりの予算を用意しても、希望する広さや立地の物件を手に入れにくい」という声が増えています。一見すると贅沢な悩みに聞こえるかもしれませんが、実際には多くの人が住宅購入に強いストレスを抱えていることが、最新調査から明らかになっています。 特に高年収層は「通常なら購入できるはずなのに理想に届かない」というジレンマに直面しやすく、住宅購入に対する満足度の低さが悩みの種になっているそうです。そこで本記事では、住宅購入に伴うストレスの背景を整理しながら、ミドル層にも役立つ「予算と理想の折り合いの付け方」や「無理のない返済計画の考え方」を解説します。
01高年収層ほど悩む!「買えるのに満足できない」住宅購入ストレス
不動産仲介関連サービスを手掛けるTERASSが、一都三県在住の住宅購入検討者1097名を対象に実施した「住宅購入検討者に関する意識調査」によると、「物件探しに対してどの程度ストレスを感じているか」という質問で「とても感じる」「やや感じる」と答えた人の割合は約70%にのぼりました。なかでも年収1000万~1500万円の層では約80%がストレスを感じており、特に都心居住者にその傾向が強い結果となっています。
一般的に高収入と呼ばれる世帯が、なぜマイホーム探しにストレスを感じているのでしょうか。その理由としては以下の3点が挙げられます。
- 価格と希望条件のギャップ
- 予算内での選択肢の制約
- 立地やエリアへのこだわりの強さ
まず、価格と希望条件のギャップです。都心部の物件価格が高騰している影響で、年収1000万~1500万円の世帯でも希望条件を満たす物件がなかなか見つかりません。同調査では「現実的に検討している金額」の平均が約7056万円と回答されたのに対し、都心の中古マンションは70㎡クラスでも1億円以上する物件が多く、予算内で選べる物件が限られてしまいます。
さらに、もともと都心に住んでいる人ほど、「都心部に住み続けたい」という意欲が強いため、そのこだわりが価格やエリアの選択肢を狭め、結果的にストレスを増幅させています。
いずれにしても、調査結果からは「物件を買えない」わけではなく、「予算はそれなりにあるのに、理想通りの物件を手に入れられない」といったギャップこそが、高年収層にとって大きな悩みの源になっていることがうかがえます。
02ミドル層にも広がる、「そもそも選択肢が少ない」住宅購入ストレス
住宅購入でストレスを感じているのは、世帯年収600万~800万円前後のミドル層にも広がっています。その要因は「そもそも選べる物件の幅が狭い」という現実です。
不動産の鑑定評価やデータサービスを扱う東京カンテイによると、2025年8月時点で東京23区内の中古マンション70㎡あたりの平均価格は1億721万円であり、多くの家庭にとって手が届きにくい水準となっています。
ミドル層の限られた予算でマイホームを手に入れようとすると、「立地」「延べ床面積」「築年数」といった条件面で妥協せざるを得ません。予算の壁によって希望条件を満たす物件が見つかりにくく、購入のためには希望している条件の何かを犠牲にしなければいけない現実がストレスにつながっていることが考えられます。つまり、ミドル層の悩みも「理想と現実のずれ」であり、本質的には高年収層のストレスを感じる要因と同じです。
高年収層は「多額の予算を出しても満足できない」、ミドル層は「そもそも予算の範囲で選べる物件が少ない」という点で若干の違いはありますが、どちらも「理想通りのマイホームが手に入らない」というジレンマに苦しんでいるといえます。
032025年、東京の住宅相場のリアルとは?
ここまで都心の不動産価格高騰を背景に、高年収層とミドル層の双方で住宅購入満足度が低くなっていることを述べてきました。では、東京の住宅相場は実際にどの程度の水準なのでしょうか。ここからは最新データをもとに、東京の住宅相場のリアルを紹介します。
1億円の家はどれくらいの広さ?何人で暮らせる?
東京カンテイの調査によると2025年8月の東京23区における70㎡あたりの中古マンション価格は1億721万円です。
また、東日本レインズの「首都圏中古マンション・中古戸建住宅 地域別・築年帯別成約状況 【2025年04~06月】」では、東京都区部の築26~30年物件の成約単価は1㎡あたり約129万円とされています。仮に予算1億円の場合、購入できる広さは約77㎡が目安です。
このことから、都心では1億円あっても現実的には60~70㎡台の住まいが相場といえるでしょう。では、70㎡の住宅にはどれくらいの世帯人数が適しているのでしょうか。それについては、国土交通省の「住生活基本計画」が参考になります。
同資料によると、豊かな住生活実現の前提として必要と考えられる誘導居住面積水準の計算式(2人以上の世帯)は、共同住宅を想定した都市居住型で「20㎡×世帯人数+15㎡」、郊外の戸建てを想定した一般型は「25㎡×世帯人数+25㎡」です。仮に夫婦2人の場合は都市居住型で55㎡なのに対して、一般型では75㎡ほど必要になる計算で、マンションなら余裕の広さですが、郊外の戸建ての場合は70㎡の住宅だと狭く感じる可能性があります。
以下に、都市居住型の具体的な家族構成と誘導居住面積水準を満たしているかどうかの一覧表を作成したので、参考にしてください(年齢による人数換算の仕方:0–2歳=0.25人、3–5歳=0.5人、6–9歳=0.75人、10歳以上=1.0人)。
| 家族構成 | 誘導居住面積水準を満たすのに必要な㎡数 | 誘導居住面積水準を満たしているかどうか |
|---|---|---|
| 夫婦2人 | 55㎡ | 〇 |
| 夫婦+0~2歳1人 | 60㎡ | 〇 |
| 夫婦+3~5歳1人 | 65㎡ | 〇 |
| 夫婦+6~9歳1人 | 70㎡ | 〇 |
| 夫婦+10歳以上1人 | 75㎡ | × |
この表から分かる通り、70㎡の住宅は「夫婦+未就学~小学校低学年までの子ども1人」までは水準を満たす一方で、それ以上になると狭さを感じやすいことがわかります。
立地を東京23区外に広げると、同じ予算でも広い住宅を購入しやすくなります。たとえば2025年7月時点で東京都全体の70㎡換算平均は8908万円なので、1億円あれば約79㎡の広さが購入可能です。条件を少し緩めるだけで、住空間のゆとりが大きく変わることがわかります。
なお、最低限の基準として「最低居住面積水準(10㎡×世帯人数+10㎡)」もありますが、こちらはあくまで健康で文化的な生活を営むための下限であり、快適性を示すものではありません。
7000万円の家はどれくらいの広さ?暮らせる世帯イメージは?
TERASSの調査によると、都心居住者の住宅平均予算は約7056万円です。東日本レインズの成約㎡単価「約129万円」を基にすると、54.3㎡=7000万円÷129万円となり、予算7000万円で購入できる住宅の延床面積は約54㎡が目安といえます。
都心の平均単価で考えると、7000万円ではファミリー向けの70㎡クラスには届かず、DINKS(共働き夫婦)や小さな子ども1人の世帯向けに現実的な広さです。
東京都区部でも築年数や駅までの距離を妥協すれば、60㎡台後半の物件が7000万円前後で見つかることもありますが、すべての条件を満たしたハイグレード物件を手に入れることは難しいでしょう。
一方で、70㎡あたりの中古マンション価格の東京都平均は約9000万円(東京23区内は1億721万円)です。探すエリアを広げれば、予算7000万円で100㎡近い物件を購入でき可能性もあります。
04住宅購入ストレスを感じないために!予算と理想のギャップを埋める3つの方法
住宅購入は、ほとんどの人にとって一生に一度といえる大きな買い物です。せっかく夢のマイホームを探すなら、できるだけストレスを減らしたいもの。ここでは、予算と理想のギャップを埋めるための3つの方法を紹介します。
郊外や再開発エリアに注目し、立地条件を見直す
都心の人気エリアは価格が高騰しているため、すべての希望条件を満たすのは難しいのが実情です。そこで、まずは少し郊外や再開発が進むエリアにも目を向けてみましょう。
近年は鉄道網や再開発によって、通勤・生活の利便性が改善されるエリアも増えています。立地を柔軟に考えることで、同じ予算でも広さや築年数、駅距離のバランスが取れた住まいを見つけやすくなります。
たとえば、都内であれば公共インフラや商業施設、交通アクセスの改善計画があって新しい住まいとしての魅力が増している「有明エリア(江東区)」、再開発計画があって家賃・物件価格が比較的抑えめな「小岩駅周辺(江戸川区)」などが候補に挙がるでしょう。また、再開発意欲のあるエリアで東京に比較的近く価格と広さのバランスがよい埼玉県川口市、千葉県内でも再開発や大型の商業施設が整備されてきている船橋市などは狙い目だといえます。
築年数を妥協してオーダーリノベーションで理想に近づける
不動産価格は築年数が浅いほど高く、特に新築にこだわると価格が跳ね上がりやすいため、住宅探しのストレスにつながります。そのため、都心で住宅を探す場合は「築20~40年程度の中古物件をリノベーション前提で探す」という選択肢がおすすめです。
東日本レインズの資料によると、都心の築年数30年以上の成約㎡単価は77.3万円です。70㎡の物件なら購入価格の目安は約5410万円です。
フルリノベーション費用の相場は1㎡あたり15万~25万円なので、70㎡の場合は1050万~1750万円程度を見込んでおくとよいでしょう。つまり、総額で6500万~7000万円前後(購入価格約5410万円+リノベーション費用1000万~1600万円)で70㎡のマイホームを購入できる計算です。
工事範囲や水回りの移設など、どこまで工事をするかによってリノベーション費用は変わります。抑えれば1㎡あたり10万~15万円で収まる場合があるものの、新築や築浅物件を1億円で購入するよりも、中古マンション+リノベの方が「価格」と「理想」のバランスを取りやすいでしょう。
リノベーションの中でも特に近年は、予算に応じて内装や設備を自分好みに変えられる「オーダーリノベーション」が人気です。オーダーリノベーションについては下記の参考記事でも紹介しているので、よろしければそちらも参考にしてください。
住宅ローンの借入金を調整して、無理のない返済計画を立てる
マイホーム購入で特に意識しておきたいのが、「無理のない返済計画を立てること」です。日本では不動産のみならず、さまざまな物価全般が上昇しており、それを抑制するために今後金利が上昇する可能性が高くなっています。
金利が上がると当然住宅ローンの総返済額も増えてしまうため、これからは「借りられる金額」ではなく、「無理なく返せる金額」での住宅ローン利用を考えましょう。
一般的に金融機関は住宅ローン審査で「年収の7~10倍程度までは借入可能」としているところが多いですが、実際に安心して返済できる水準は「年収の5~7倍以内が目安」だといわれています。とはいえ、7倍に近づくほど生活に余裕がなくなりやすいので、5倍程度を安全圏、7倍を上限と考えるのが賢明です。
また、借入額を少し抑えるだけでも、家計の負担が大きく変わることも覚えておきましょう。たとえば、金利1.5%、返済期間35年の場合における借入額と毎月の返済額の違いは以下のとおりです。
| 借入額 | 毎月の返済額 |
|---|---|
| 6000万円 | 約18万2000円 |
| 7000万円 | 約21万2000円 |
上記のとおり、借入額を1000万円減らして6000万円にすると毎月の返済額を約3万円抑えられるうえ、仮に年収800万円のミドル層であれば返済比率も27%程度に収まり、生活のバランスもある程度取りやすくなります。
ただし、今回のシミュレーションでは金利が1%上昇すると、毎月の返済額が借入額7000万円の場合で約26万8000円、借入額6000万円の場合でも約23万円まで増えると想定されるため、変動金利で借り入れる際の金利上昇リスクは常に頭に入れておかなくてはいけません。いずれにしても、将来の収入や教育費を見据え、金利上昇にも耐えられる水準で借入額を決めることが重要です。
05住宅購入ストレスを減らすカギは「優先順位」と「返済可能額」の整理!
住宅購入におけるストレスは「予算があっても理想に届かない」という現実が大きな要因です。これは高年収層だけでなく、ミドル層にとっても共通のテーマといえます。
結局のところ、住宅購入の本質は「理想と現実のバランスをどうとるか」です。エリア・築年数・返済額のどれを優先するかでストレスの度合いも大きく変わります。そのため、まずは自分と家族にとっての優先順位を整理し、無理なく返せる金額を明確にしておくと住宅探しがスムーズに進むでしょう。
当サイトでは、住宅ローン予算づくりに役立つシミュレーターを用意しています。適切な予算を知りたい人におすすめの「住宅購入予算シミュレーター」、金利の違いで毎月の支払いがどれぐらい変わるかを比較したい人に向いている「毎月の返済額シミュレーター」など、住宅ローン予算の作成に役立つ各種シミュレーターがそろっているので、これから住宅探しをする予定の人は、ぜひ試してみてください。

監修:新井智美
CFP®/1級ファイナンシャル・プランニング技能士
プロフィール
トータルマネーコンサルタントとして個人向け相談の他、資産運用など上記相談内容にまつわるセミナー講師を行う傍ら、年間100件以上の執筆・監修業務を手掛けている。
関連キーワード