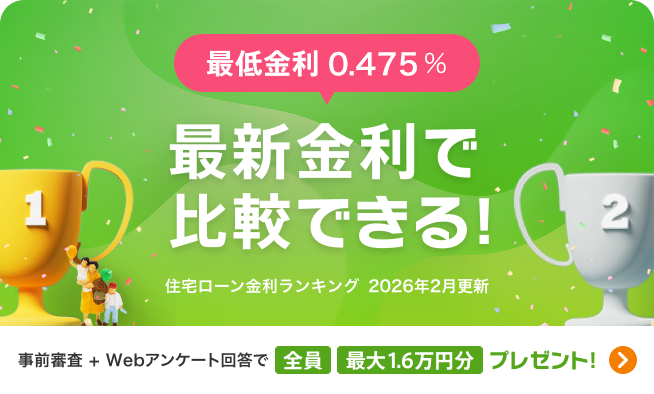「在宅避難」できる家が欲しい!追加コストは住宅ローンでどう備える?
地震や水害などの災害時、自宅で避難生活を送りたいと考える方は多く、ある工務店が行った調査でも、約6割が「在宅避難が理想」と回答しています。こうしたニーズの増加に伴い、最近は耐震性に加えて「在宅避難できる家づくり」が注目を集めています。 しかし、在宅避難するには、太陽光発電や蓄電池、食品や飲料水の備蓄スペースなどを設ける必要があり、追加で数十万〜数百万円のコストがかかるケースもあります。地震や水害などによる災害に対する備えの必要性を感じながらも、予算面に不安を抱える方も少なくありません。 この記事では、「在宅避難できる家」に必要な設備や追加コストの目安、住宅ローンを活用した資金計画の工夫を解説します。
01なぜ「在宅避難」が注目されるのか
兵庫県の工務店「WHALE HOUSE」が、2025年7月に実施した「地震後の在宅避難と住宅性能」に関する調査によると、「理想は在宅避難」と回答した人が約6割に上る一方、現実的には約半数が「避難所を選ぶ」と回答し、理想と現実のギャップが浮き彫りになりました。
在宅避難を望む理由は、「落ち着いて過ごしたい」(59.3%)、「プライバシーが保たれる」(57.3%)、「家族全員と一緒にいられる」(52.8%)といった回答でした。対して、避難所を選ぶ理由として多かった回答は「自宅の倒壊・火災の懸念」(44.3%)、「備蓄が不十分」(34.3%)、「防災の知識がなく、避難所の方が安心」(31.8%)などが挙げられています。
災害に見舞われた際の心理面や生活面を考えると、住み慣れた自宅で避難を続けたいものの、安全性や備えへの不安から、現実的には避難所へ避難せざるを得ないと考える方が多いようです。
こうした理想と現実のギャップを埋めるには、自宅の耐震性を強化するのはもちろん、電力や水の確保、備蓄スペースの整備など、在宅避難を可能にする家づくりが欠かせません。とはいえ、数十万〜数百万円の追加コストがかかる可能性もあるため、資金計画にどう盛り込むかがポイントになるでしょう。
02在宅避難できる家に必要な追加コストとは
災害時に自宅で避難生活を続けるには、建物の耐震性を高めるだけでは不十分です。電気や水道などのライフラインが止まっても、復旧までのあいだ暮らしを維持できる設備や備蓄環境を整える必要があります。ここでは、そのためにかかる主な追加コストと目安を確認してみましょう。
耐震等級3・構造計算(20万~40万円前後)
在宅避難を続けられるようにするには、まず耐震性を高めることが欠かせません。耐震等級の最高等級である「等級3」を満たす家づくりは必須といえるでしょう。
耐震等級3として認められるには、許容応力度計算(地震時、柱や梁などにかかる力を数値で確認し、建物が揺れに耐えられるかを検証する計算)などの構造計算を行う必要があります。これには、設計や工法に応じて20万〜40万円程度の追加費用が必要です。等級3として認められるには、住宅性能評価の申請などの追加手続きも求められるため、総額で50万〜80万円程度は見込んでおきたいところです。
高いように感じるかもしれませんが、在宅避難できる家の大前提になる部分であり、優先的に検討すべきコストといえます。適切な費用で施工できるよう、複数社から見積もりを取って比較しましょう。
太陽光発電+蓄電池(200万〜300万円前後)
災害による停電時、在宅避難の強い味方になるのが電力の自給です。太陽光発電システムと蓄電池を組み合わせれば、停電時も照明や通信環境、冷蔵庫など生活の基盤を維持できます。太陽光発電と蓄電池の導入費用の目安は次のとおりです。
太陽光発電と蓄電池の導入費用の目安
| 単位面積あたりの価格 | 一般的な相場 | |
|---|---|---|
| 太陽光発電システム | 1kWあたり約28.6万円 (2024年の新築平均) |
約114万〜163万円 (4〜5kW) |
| 蓄電池 | 1kWhあたり約14万円 (工事費を含む) |
約70万〜150万円 (5〜10kWh) |
両者をセットで導入した場合、200万〜250万円前後が標準的な相場です。大容量タイプを選ぶ場合は300万円前後になるケースもあります。電力自給ができれば災害時の安心に加え、普段の電気代を削減できるのも大きなメリットです。
エコキュート・非常用水タンク(35万〜60万円前後)
電気でお湯をつくって貯める給湯器「エコキュート」や非常用水タンクを設置しておけば、災害時でも生活用水やお湯が使えるようになります。導入費用の相場は、工事費込みで約35万〜60万円前後です。大容量タイプや高性能モデルを選ぶ場合は、80万円前後になることもあるでしょう。
特にエコキュートの非常用取水栓付きモデルなら、断水時でもタンク内の水を手動で取り出し、そのまま生活用水として利用することもできます(※飲用は避けてください)。例えば370Lタイプなら3〜4人家族で3日分程度の生活用水に相当し、避難所へ水を取りに行く手間を減らせます。
もちろん、日常の給湯設備としても性能が高く、光熱費の節約につながります。災害時でも水が使える安心感は大きいため、在宅避難のために欠かせない設備の一つです。
備蓄収納スペース(設計工夫で+α程度)
在宅避難に備えるには、食料や飲料水を保管できる収納スペースも欠かせません。新築時にパントリーや床下収納を設置すれば、そのまま備蓄収納として活用できます。費用の目安は、床下収納で1ヶ所あたり5万〜15万円程度、パントリーも造作棚を取り付けるだけなら費用はそれほどかかりません。
また、住宅全体の収納率(床面積に対する収納スペースの面積の割合)を12〜15%程度になるよう設計すれば、備蓄収納も自然に確保でき、導入コストを抑えられるでしょう。
ここまで見てきたように、在宅避難できる家づくりには、耐震性の強化、太陽光発電システムと蓄電池、給湯設備の導入、備蓄収納スペースの確保などが必要です。総額で数十万円〜数百万円の追加コストがかかるのが一般的です。
金額だけ聞くと大きな負担に思えるかもしれませんが、住宅ローンに組み込むことで、仮に35年返済の場合だと月々数千〜1万円程度の負担増にとどまります。住宅ローンを活用した資金計画を立てることが、在宅避難できる家づくりをかなえるためのポイントなのです。
03住宅ローンで備える資金計画の工夫
在宅避難できる家づくりに必要な数十万〜数百万円の追加コストは、資金計画の工夫次第で無理なく負担できます。どのような工夫が考えられるのか紹介しましょう。
住宅ローンに組み込んで初期費用を抑える
太陽光発電システムや蓄電池など、建物本体に付属する大きな設備にかかる費用は、住宅ローンに組み込むことができます。低金利な住宅ローンに含めれば、数百万円の追加コストの負担感を和らげられるでしょう。
例えば、太陽光発電システムと蓄電池の設置費用250万円を、固定金利2%・ボーナス払いなしの15年ローンで借り入れた場合、毎月返済額は約1万6000円の増。350万円かかったとしても、毎月返済額の増額分は2万2500円です。
返済期間を長くすれば、毎月返済額が数千円増額するだけで収まるケースもあるため、初期費用を現金で用意するより、家計への影響を小さくできるかもしれません。
国の補助金・優遇制度を活用する
在宅避難を可能にする設備の多くは省エネにもつながるため、国や自治体の補助金・助成金制度を活用できる場合があります。こうした制度を使えば、実質的な負担を軽減できるでしょう。例えば、国の「ZEH(ゼッチ)補助金」を使うと、以下の補助が受けられます。
・ZEH補助金の内容
| 補助メニュー | 補助額 |
|---|---|
| ZEH基準を満たす住宅の新築 | 55万円/戸 |
| ZEH+を満たす住宅の新築 | 90万円/戸 |
| 蓄電システムの導入(追加補助) | 2万円/kWh、上限20万円 |
ZEHで蓄電システムを導入した場合には最大75万円、ZEH+なら最大110万円(特定のエコキュートとV2Hを導入した場合は最大122万円)の補助を受けることが可能です。
近年注目されている、V2H(Vehicle to Home)の導入に対する補助金も充実しています。V2Hとは、電気自動車(EV)やプラグインハイブリッド車(PHEV)に貯めた電気を、家でも利用できるようにするシステムのこと。自動車を蓄電池代わりに使えるので、在宅避難への備えとしても役立ちます。
個人宅での導入に国の補助金を利用した場合、機器については費用の1/3(補助上限30万円)、工事費については全額(上限15万円)が補助され、合計で最大45万円を受け取れます。また、東京都など一部の自治体では、最大100万円の補助を追加で受けられる場合もあるため、あらかじめ確認しておきましょう。
補助金は、予算上限に達すると期間内でも受付終了となるケースが多いため、早めに申請することが負担を軽くするコツです。
無理のない返済負担率を守る
追加コストを住宅ローンに組み込めるといっても、ローン返済で家計が圧迫されるようでは本末転倒です。一般的に、住宅ローンを無理なく返済するには、年間返済額を年収の25〜30%以内に収めるべきとされます。年収600万円の方であれば、年間返済額を150万〜180万円(毎月約12万5000〜15万円)以下にするのが目安です。
ただし、この比率は利用しているローンが住宅ローンのみの場合です。他にもローンの支払いがある場合は、返済負担率(年収における年間のローン全体の額が占める割合)にも気をつける必要があります。
できれば返済負担率は25%程度にとどまるよう、住宅ローンの返済額を決めましょう。
在宅避難用に200万円を上乗せした場合、35年ローン・金利1%で毎月約5600円の負担増となります。この金額を含めて、上記の基準内に収まる資金計画を立てましょう。
将来の繰り上げ返済・借り換えで調整する
長期ローンで毎月の返済負担を軽減する場合でも、繰り上げ返済やローンの借り換えを活用することで、資金計画を柔軟に変更できます。
例えば、3000万円を固定金利1.0%・35年ローンで借り入れるケースを考えてみましょう。このときの毎月返済額は約8万5000円、総支払額は約3560万円です。10年後に100万円を繰り上げ返済する場合、期間短縮型であれば返済期間は1年3カ月の短縮となり、総支払額(利息額)は約27万5000円減少します。
借り換えについても同様に試算してみましょう。ローン残高2000万円で残り返済期間が25年のとき、金利1.5%のローンから金利0.8%のローンへ借り換えた場合、毎月の返済額は約8万円から約7万4000円へと減少します。総返済額も約192万円削減でき(借り換え時の諸費用を除く)、返済負担が軽くなるでしょう。
こうした工夫を組み合わせることにより、長期ローンであっても、家計の状況に応じて柔軟に対応できるのです。
04命と暮らしを守る家づくりは、住宅ローンで計画的に
在宅避難を前提とした家づくりは、災害に対する備えとなるだけでなく、快適な暮らしや省エネにもつながります。長期的なメリットが期待できる一方、太陽光発電システムや蓄電池などを導入するには、数百万円単位の追加コストが必要です。決して小さくない負担ですが、住宅ローンに組み込んで計画的に返済すれば、災害に対する備えを無理なく強化できます。
当サイトの住宅ローンシミュレーターを活用して、予算内でどこまで追加コストを見込めるか確認することが、命と暮らしを守る家づくりに向けた第一歩になるでしょう。

監修:新井智美
CFP®/1級ファイナンシャル・プランニング技能士
プロフィール
トータルマネーコンサルタントとして個人向け相談の他、資産運用など上記相談内容にまつわるセミナー講師を行う傍ら、年間100件以上の執筆・監修業務を手掛けている。