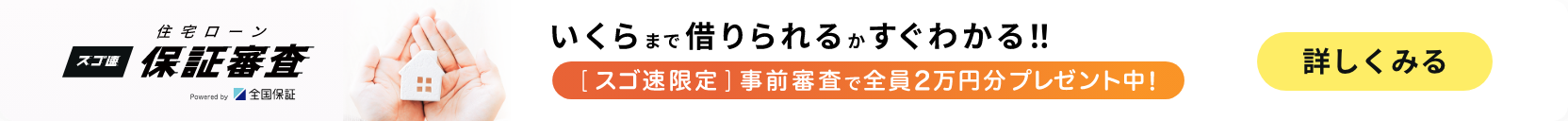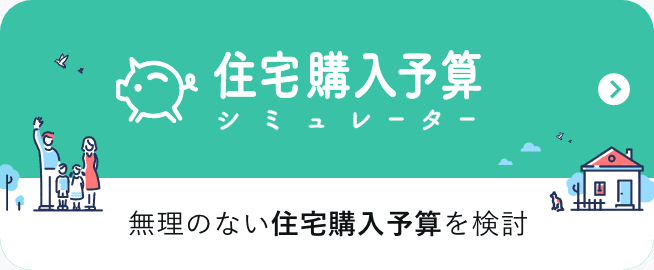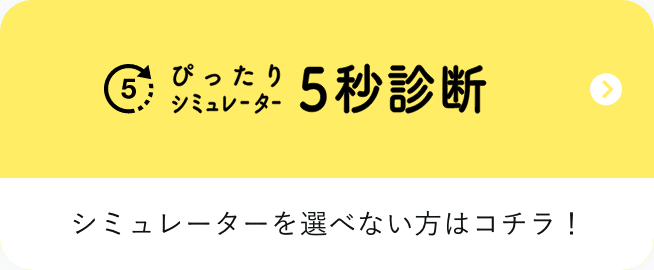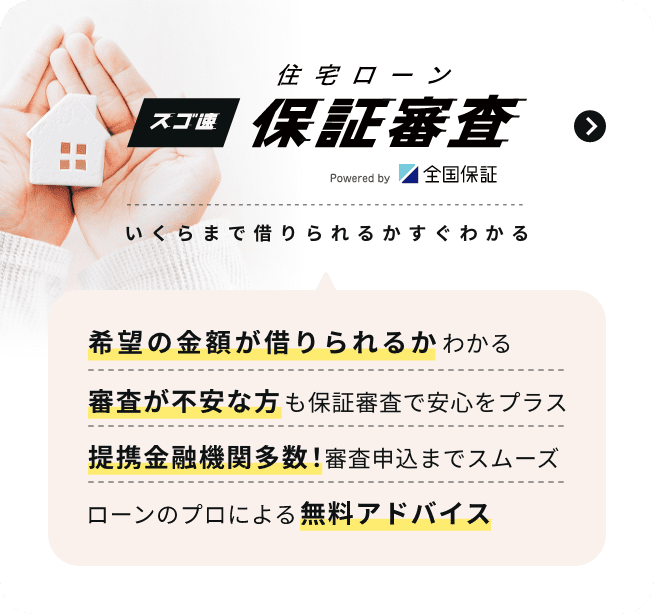2024年最新版!住宅購入時やリフォームに使える補助金・助成金まとめ
住宅を購入する場合、もしくは住宅を建てる場合、要件を満たせば国の助成金を受け取ることができます。今回は主な補助金・助成金制度の概要やその申請方法についてご紹介します。
01住宅の購入時に利用できる補助金・助成金制度一覧
ZEH補助金制度など、住宅を購入もしくはリフォームする場合に活用したい補助金・助成金制度を紹介します。
子育てエコホーム支援事業
子育てエコホーム支援事業とは、エネルギー価格など物価の高騰によって家計に影響を受けやすい子育て世代もしくは若者夫婦世帯に対し、省エネ性の高い新築住宅の購入やリフォームにおける補助金を交付する制度です。
対象者
- 省エネ性の高い住宅を新築もしくは購入する人
- 自己所有の住宅を省エネ住宅に改修する人
上記のいずれかに該当し、かつ以下のいずれかに当てはまる世帯
- 子育て世帯
- 申請時点において、2023年4月1日時点で18歳未満の子どもがいる世帯
- ただし、2024年3月末までに工事に着手する場合は、2022年4月1日時点で18歳未満の子どもがいる世帯
- 申請時点において、2023年4月1日時点で18歳未満の子どもがいる世帯
- 若者夫婦世帯
- 申請時点において夫婦であり、かつ、2023年4月1日時点で夫婦のいずれかが39歳以下である世帯
- ただし、2024年3月末までに工事に着手する場合は2022年4月1日時点で夫婦のいずれかが39歳以下である世帯
- 申請時点において夫婦であり、かつ、2023年4月1日時点で夫婦のいずれかが39歳以下である世帯
対象となる住宅
開口部や外壁、屋根・天井、床の断熱や省エネ設備の設置のほか、ビルトイン食器洗剤機や宅配ボックスなど子育て対応が行われている住宅(バリアフリーや空気清浄機能の設置も対象)
補助金額
- 新築・購入長期
- 優良住宅:1戸あたり100万円
- その他:1戸あたり最大30万円
- ZEH住宅:1戸あたり最大80万円
- リフォーム
- 長期優良住宅:1戸あたり最大45万円
- 中古住宅の購入
- 1戸あたり最大60万円
応募方法
公募期間内(2024年は3月中旬~予算の上限に達するまで)に申請を行い、審査を受け、認められると補助金が給付されます。
予算については、2023年度は2100億円でしたが、2024年度は当初予算案として400億円が計上されており、今後拡大されることが予想されます。
正式なスケジュールについては、国土交通省の子育てエコホーム支援事業のサイトにて順次更新されますので、こまめにチェックしておきましょう。
ZEH支援事業
ZEH(ゼッチ)とはネット・ゼロ・エネルギー・ハウスの略で、断熱性・省エネ性能を上げること、そして太陽光発電などでエネルギーを自ら創ること(創エネ)により、年間の消費エネルギー量(空調・給湯・照明・換気)の収支をプラスマイナスゼロにすることを目指す住宅のことです。
ZEH支援事業は「ZEH」、「ZEH+」に別れており、それぞれで補助額が異なる点に注意が必要です。
ZEHに該当するための要件は以下の通りです。
ZEH
以下の1~3の全てに適合した住宅
- 強化外皮基準(1~8地域の平成28年省エネルギー基準を満たした上で、UA値 1、2地域:0.40[W/㎡K]以下、3地域:0.50[W/㎡K]以下、4~7地域:0.60[W/㎡K]以下)
- 再生可能エネルギー等を除き、基準一次エネルギー消費量から20%以上の一次エネルギー消費量削減
- 再生可能エネルギー等を加えて、基準一次エネルギー消費量から100%以上の一次エネルギー消費量削減
ZEH+
ZEH+では、ZEHの条件を満たし、さらに以下の2つの条件を満たしていなければなりません。
- 省エネ基準から25%以上の一次エネルギー消費量削減
- 以下のうち、2つ以上を導入する
- 外皮性能の更なる強化
- 高度エネルギーマネジメント
- 電気自動車(PHV車を含む)を活用した自家消費の拡大措置のための充電設備又は充放電設備
また、Nearly ZEHやNearly ZEH+、ZEH OrientedもZEH支援事業の対象です。
Nearly ZEHとは、住宅のスペースの問題により、太陽光発電装置を十分に設置できないケースを考慮し、基準がZEHよりも低くなっているモデルのことです。Nearly ZEH+はNearly ZEHの要件を満たし、省エネ基準から25%以上の一次エネルギー消費量削減の更なる省エネルギーを実現し、かつ以下の要素の内2つ以上を採用した住宅を指します。
- 外皮性能の更なる強化
- 高度エネルギーマネジメント
- 電気自動車を活用した自家消費の拡大措置
そして、ZEH Orientedとは、安全性や天候の問題などによってZEHの要件を満たすことが難しい地域を考慮し、創エネを必要要件としないモデルのことです。
また、Nearly ZEHやNearly ZEH+、ZEH Orientedの定義は以下の通りです。
Nearly ZEH
以下の条件に適合した住宅
- 強化外皮基準(1~8地域の平成28年省エネルギー基準を満たした上で、UA値 1、2地域:0.40[W/㎡K]以下、3地域:0.50[W/㎡K]以下、4~7地域:0.60[W/㎡K]以下)
- 再生可能エネルギー等を除き、基準一次エネルギー消費量から20%以上の一次エネルギー消費量削減
- 再生可能エネルギー等を加えて、基準一次エネルギー消費量から75%以上100%未満の一次エネルギー消費量削減
Nearly ZEH+
Nearly ZEHの要件を満たし、省エネ基準から25%以上の一次エネルギー消費量削減の更なる省エネルギーを実現し、かつ、以下の3つの要素のうち2つ以上を採用した住宅
- 外皮性能の更なる強化
- 高度エネルギーマネジメント
- 電気自動車を活用した自家消費の拡大措置
ZEH Oriented
以下の条件に適合した住宅
- 強化外皮基準(1~8地域の平成28年省エネルギー基準を満たした上で、UA値 1、2地域:0.40[W/㎡K]以下、3地域:0.50[W/㎡K]以下、4~7地域:0.60[W/㎡K]以下)
- 再生可能エネルギー等を除き、基準一次エネルギー消費量から20%以上の一次エネルギー消費量削減
いずれの場合もエネルギーにかかる設備は当該住宅の敷地内に設置されていなければなりません。
対象者
新築住宅を建築もしくは購入する人
対象となる住宅
- ZEH
- ZEH
- Nearly ZEH(寒冷地、低日射地域、多雪地域に限る)
- ZEH Oriented(都市部狭小地の2階建以上及び多雪地域に限る)
- ZEH+
- ZEH+
- Nearly ZEH+(寒冷地、低日射地域、多雪地域に限る)
補助額
- ZEH
- 1戸あたり55万円
- ZEH+
- 1戸あたり100万円
直交集成板(CLT)、地中熱ヒートポンプ・システム、PVTシステム、液体集熱式太陽熱利用システム等を導入する場合、それぞれのシステムに応じた補助額が加算されます。
応募方法
こちらも公募制となっており、2023年度の2次公募は2023年11月日~2024年1月9日でした。期間内に申請を行い、審査を受け、認められると補助金が給付されます。
2024年の公募期間や申請の手順などについては決定次第、ZEH事業を運営する一般社団法人環境共創イニシアチブのホームページで随時告知されます。公募は例年、先着制がとられており、定員に達し次第、締め切られるので、ZEH補助金の活用を考えている人はこまめにホームページをチェックし、早めに応募をするようにしてください。
地域型住宅グリーン化事業補助金
地域型住宅グリーン化事業は、各地域の木造住宅の生産体制を強化し、環境負荷の低減を図ることを目的とし、国土交通省の採択を受けた住宅供給グループ(原木供給・製材・建材・設計・施工などの業者)が建てる省エネルギー性能や耐久性能等に優れた木造住宅を対象に、補助金が交付される制度です。あくまでも事業者を対象とした制度で、施工主が直接申請や受給に関わらない制度で、補助金は最終的に施工主に支払われるものです。木造住宅や省エネ住宅を検討している人は本事業の採択を受けた業者に相談して適用条件を満たす家を作ると、費用を抑えること可能となります。
対象となる住宅
補助の対象となるのはいずれかに該当する木造住宅です。
- 長寿命型(長期優良住宅)
- 高度省エネ型(認定低炭素住宅又は性能向上計画認定住宅)
- ゼロ・エネルギー住宅型
- 省エネ改修型
また補助の対象となる木造住宅については下記の要件を満たす必要があります
- 主要構造部(建築基準法第2条第5号の定義による)が木造のもの
- 本事業に採択されたグループごとの共通ルールに則して、グループ構成員である中小住宅生産者等により供給される新築住宅であること
ただし「ゼロ・エネルギー住宅型」については「戸建住宅の新築および改修」を、省エネ改修型においては、「戸建て住宅の改修」のみを対象とします。なお、いずれもモデルハウスは対象外とします。
さらに、ZEHもしくはZEH水準の住宅に求める共通要件として、以下のいずれかを満たさなければなりません。
- 断熱材、太陽光パネルなどの荷重を見込んだ構造計算を実施
- 壁量計算などにより構造安全性を確認したもの
- 設計者・施工管理者・大工技能者のうちいずれか1人が、住宅省エネルギー技術講習会の修了者、または別途定める講習会等の受講者等であること
- 長寿命型、ゼロ・エネルギー住宅型、高度省エネ型及び優良建築物型の新築は採択通知の日付以降に改修工事の開始すること
- 主要構造部に用いる木材は、各採択グループが定める地域材を使用すること(省エネ改修型を除く)
補助金交付額
- 長寿命型
- 建設費用の10分の1、もしくは1戸あたり最大140万円
- ただし、補助を受ける事業者が地域型住宅グリーン化事業において、長期優良住宅の補助金活用実績が4戸以上ある場合は、最大1戸あたり125万円
- 建設費用の10分の1、もしくは1戸あたり最大140万円
- ゼロ・エネルギー住宅型
- 建設費用の10分の1、もしくは1戸あたり最大150万円
- ただし、補助を受ける事業者が地域型住宅グリーン化事業において、長期優良住宅の補助金活用実績が4戸以上ある場合は、最大1戸あたり125万円。また認定長期優良住宅の認定を受けている場合は1戸あたり150万円
- 建設費用の10分の1、もしくは1戸あたり最大150万円
- 高度省エネ型
- 建設費用の10分の1、もしくは1戸あたり最大90万円
- ただし、補助を受ける事業者が地域型住宅グリーン化事業において、長期優良住宅の補助金活用実績が4戸以上ある場合は、最大1戸あたり70万円。また、一部の条件を満たす場合は条件に応じた補助額が加算
- 建設費用の10分の1、もしくは1戸あたり最大90万円
応募方法
工事を施工する会社が申請を行います。
補助金の活用方法については、「こどもエコ活用タイプ」と「通常タイプ」の2種類に分けられ、いずれかを物件ごとに選択する必要がある点に注意が必要です。
LCCM住宅整備推進事業
LCCM住宅とは、ZEHよりさらに省CO2化を進めた先導的な脱炭素化住宅で、建設時、運用時、廃棄時において出来るだけ省CO2に取り組み、さらに太陽光発電などを利用した再生可能エネルギーの創出により、住宅建設時のCO2排出量も含めライフサイクルを通じてのCO2の収支をマイナスにする住宅です。
対象者
LCCM住宅を新築する人
対象となる住宅
- 強化外皮基準(ZEH水準の断熱性能)を満たすもの
- 再生可能エネルギーを除き、一次エネルギー消費量が現行の省エネ基準値から25%削減されているもの
- ライフサイクルCO2の評価結果が0以下となるもの
- 建築場所が土砂災害特別警戒区危機に該当しないこと
など
補助金額
建設費用の2分の1、もしくは1戸あたり最大140万円
応募方法
指定された申請期間中に工事を請け負った会社が申請を行います。
先進的窓リノベ2024事業
2024年はリフォームを行う人に向けた補助制度も多く用意されています。先進的窓リノベ2024事業とは、既存の窓を断熱窓にリフォームする人にむけた補助制度で、住宅の省エネや省CO2加速化を目指した支援事業です。
対象者
リフォーム工事を発注する人
対象となる住宅
居住用の住宅
補助金額
1戸あたり5万~200万円
応募方法
リフォーム工事を請け負った会社が申請を行い、対象者に還元します。リフォーム工事については、2023年11月2日以降に着手したものが対象で、申請期間は2024年3月中旬~予算の上限に達するまでとなっています。
給湯省エネ2024事業
省エネルギー推進の目的で、効率の高い給湯器を設置する際に利用できます。なお、中古住宅を購入する場合に、給湯器の交換を条件にする際も該当します。
対象者
リフォームを発注する人や新築住宅および中古住宅の購入者
対象となる給湯設備
- ヒートポンプ給湯機(エコキュート)
- 電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯機(ハイブリッド給湯機)
- 家庭用燃料電池(エネファーム)
補助金額
- ヒートポンプ給湯機(エコキュート):1台あたり8万円
- 電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯機(ハイブリッド給湯機):1台あたり10万円
- 家庭用燃料電池(エネファーム):1台あたり18万円
戸建ての場合は、いずれか2台までとなります。
応募方法
原則として給湯器の設置工事を請け負った会社が申請し、対象者に還元します。工事については、2023年11月2日以降に着手したものが対象で、申請期間は2024年3月中旬~予算の上限に達するまでとなっています。
02地方自治体で行っている補助金・助成金制度について
ここまで国が運営する補助金・助成金制度について見てきましたが、都道府県や市区町村などの地方自治体が運営する補助金・助成金制度もたくさんあります。住宅の新築や購入を考えている場合は、住所のある地方自治体の窓口やホームページで、どのような制度が提供されているのかを確認すると良いでしょう。たとえば、2024年現在、全国の地方自治体では、次のような補助金・助成金制度が提供されています。
大阪市新婚・子育て分譲住宅購入融資利子補給制度(大阪府大阪市)
対象住宅
- 大阪市内の住宅(戸建住宅・集合住宅)
- 床面積が50㎡以上
- 検査済証の交付を受けている新築住宅
- 耐震性があることが確認できる中古住宅
対象となる融資
- 返済期間が10年以上
- 利率が年0.1%以上
- 指定された金融機関が取り扱うもの
対象者
住宅を初めて取得する人で、申し込み時に新婚もしくは子育て世帯
- 新婚世帯
- 申込者及び配偶者のいずれもが40歳未満で、婚姻届提出5年以内の子育て世帯ではない世帯
- 子育て世帯
- 同一世帯に申込者または配偶者の小学校6年生以下の子どもがいる世帯
助成金額
最大50万年
その他
住宅取得にかかる契約締結日から1年を経過していないことや、前年の所得金額が1200万円以下であることなどの要件を満たす必要があります。
住宅用スマートエネルギー設備等導入奨励金(神奈川県相模原市)
対象住宅
- ZEHコース:ZEH設備の導入
- 自家消費コース:太陽光発電システム、定置用地理有無イオン蓄電池、V2H設備の導入
対象者
- 自分が居住する住宅を新築もしくは改修によってZEHもしくはLCCM住宅にした人(購入も含む)
- 自分が居住する住宅に対象となる設備を導入した人(購入も含む)
補助金額
- ZEHコース
- 15万円(LCCM住宅の場合25万円)
- 自家消費コース
- 対象設備につき各3万円
申請できるコースは1つのみで、併用はできません。また、年間の予定件数が決められており、先着順となります。
住宅を対象とした補助金・助成金は、工事の着工前に申請・認可が必要なものがほとんどです。着工後は申請が認められないケースが多いので、住宅の新築や購入を決めたら、すぐに利用できる制度がないかどうかを調べ、要件を満たせるものがあれば申請を行いましょう。
また、補助金・助成金制度は期限付きで実施されているものがほとんどであり、その内容も社会情勢や時期に応じて変更されます。ここで紹介した制度の内容については、いずれも2024年1月現在のものです。実際に申請などを行う際は、必ず各制度の公式ホームページなどで最新の内容を確認するようにしてください。
ところで、これから物件を探す方には「スゴい速い住宅ローン審査」(スゴ速)がおすすめです。まだ物件が決まっていなくても事前審査が受けられ、最短15分で住宅ローンの借入可能額がわかります。
住宅ローンがいくら借りられるかを明確にしてから物件探しが始められます。

監修:相山華子
ライター、OFFICE-Hai代表、2級ファイナンシャル・プランニング技能士
プロフィール
1997年慶應義塾大学卒業後、山口放送株式会社(NNN系列)に入社し、テレビ報道部記者として各地を取材。99 年、担当したシリーズ「自然の便り」で日本民間放送連盟賞(放送活動部門)受賞。同社退社後、2002 年から拠点を東京に移し、フリーランスのライターとして活動。各種ウェブメディア、企業広報誌などで主にインタビュー記事を担当するほか、外資系企業のための日本語コンテンツ監修も手掛ける。20代で不動産を購入したのを機に、FP(2級ファイナンシャル・プランニング技能士)の資格を取得。金融関係の記事の執筆も多い。
関連キーワード