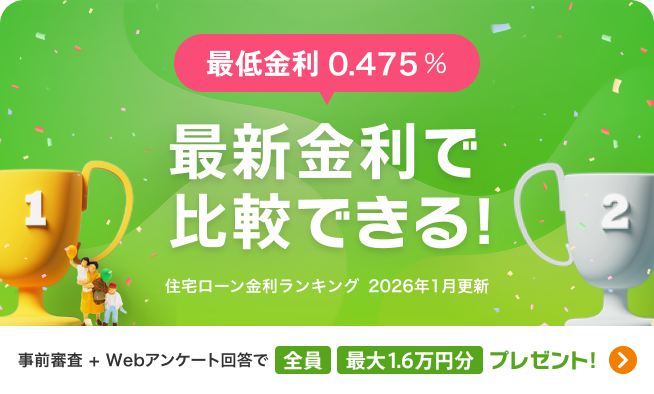北海道で家を建てるなら注目!住宅認定制度「HOKKAIDO WOOD HOUSE」と補助金の条件を解説
2025年6月、北海道で新たにスタートした住宅認定制度「HOKKAIDO WOOD HOUSE(通称:HWH)」は、道産木材を活用した質の高い住宅に認定を与える制度です。一定の基準を満たした住宅は、北海道から定額20万円の補助金が支給されるほか、金融機関によっては住宅ローンの金利優遇を受けられるなど、魅力的な制度となっています。 本記事では、HWH制度の概要や認定基準、補助金申請の流れ、制度を活用するメリットなどについて、わかりやすく解説します。北海道での家づくりを検討している方は、ぜひ参考にしてください。
- 01北海道で始まった新しい住宅認定制度「HOKKAIDO WOOD HOUSE」とは?
- 住宅認定制度「HOKKAIDO WOOD HOUSE(HWH)」の概要
- 対象となる住宅の条件
- 02HWHを活用する3つのメリット
- 安心・高品質な「道産木材の家」が建てられる
- 住宅ローン金利優遇の対象になる
- 国や自治体の補助制度と併用できる可能性がある
- 03HWHの認定を受けて補助金を活用するには?申請の流れをチェック
- ステップ1|認定申請の準備と手続き
- ステップ2|補助金の公募開始を待って申請
- ステップ3|工事完了後の実績報告と補助金交付
- 04HWHを活用した家づくりはどんな人におすすめ?
- 木の家・自然素材にこだわりたい人
- 家づくりコストを少しでも抑えたい人
- 北海道で地元に貢献できる家を建てたい人
- 05北海道で家を建てるならHWH制度の活用は必見!
01北海道で始まった新しい住宅認定制度「HOKKAIDO WOOD HOUSE」とは?
まずは、北海道で新たに始まった住宅制度「HOKKAIDO WOOD HOUSE(HWH)」の概要を押さえていきましょう。
住宅認定制度「HOKKAIDO WOOD HOUSE(HWH)」の概要
2025年6月1日から運用が開始された「HOKKAIDO WOOD HOUSE(HWH)」は、北海道独自の住宅認定制度です。地元林業・製材業の振興と地域材の普及と、環境に配慮した家づくりを促進することを目的にスタートしました。
認定を受けた住宅は、北海道の補助制度(道産木材住宅建設促進事業)により、推奨基準を満たす場合には1棟あたり定額20万円の補助金申請が可能です。ただし、補助対象となる工事期間は2025年4月1日以降に開始し、2026年1月31日までに完了していることが条件です。また、金融機関によっては住宅ローンの金利優遇の対象となるケースもあります。
対象となるのは、北海道が定めた「認定基準」または「推奨基準」に合致する住宅で、補助金を受けるには推奨基準を満たす必要があります。それぞれの基準については、次の段落で詳しく紹介します。
対象となる住宅の条件
【認定基準】
- 北海道内に建築される一戸建て住宅であること
(持家の新築または増改築に限る) - 延べ床面積が70平方メートル以上であること
(増改築の場合:対象部分が70平方メートル以上) - 建築主本人または施工業者が認定申請を行うことが可能であること
- 国・他の補助制度を併用する場合は、それぞれの制度で併用が認められていること
- 2025年4月1日以降に工事を開始し、2026年1月31日までに完了していること
(完了日は「建築基準法における検査済証の交付日」とする)
【推奨基準】
- 認定基準を満たしていること
- 延べ床面積1平方メートルあたり0.1立法メートル以上の道産木材を使用していること
- ZEH水準(断熱等性能等級5 + 一次エネルギー消費量等級6)を満たすこと
上記は、2025年度分の要件です。今後、追加・変更の可能性もあるため、申請を検討する際は最新情報を確認してください。
02HWHを活用する3つのメリット
HWH認定を受けることにより、家づくりにさまざまなメリットが得られます。ここでは、主な3つのメリットについて解説します。
安心・高品質な「道産木材の家」が建てられる
HWH認定を受ける最大のメリットは、住宅の信頼性と資産価値の向上です。北海道が定める厳しい基準をクリアした住宅であることが公的に証明されるため、売却や相続の際にも評価されやすくなります。また、北海道産木材は熱伝導率が低く、断熱材と組み合わせることで寒冷地に適した快適な住環境を実現できる点も魅力です。
住宅ローン金利優遇の対象になる
多くの金融機関では、長期優良住宅や高性能住宅を対象とした住宅ローン金利の優遇プランを用意しています。こうしたプランを活用できれば、家づくりにかかる初期費用や返済負担を軽減できる可能性があります。HWH認定住宅も対象となるケースがあるため、金融機関に相談してみましょう。
ちなみに、HWH認定住宅(推奨基準)を対象とした金利優遇プランを提供している主な金融機関は、2025年8月時点で以下のとおりです。
- 北洋銀行:ほくようゼロカーボン応援プラン
- 北海道銀行:道銀カーボンニュートラル住宅ローン
- 北海道労働金庫:ろうきん住宅ローン「ゼロカーボンプラン」
- 住宅金融支援機構:フラット35 地域連携型
国や自治体の補助制度と併用できる可能性がある
HWH認定制度は、国や自治体が提供する他の補助金制度との併用が可能です。国の子育てエコホーム支援事業や、各自治体の住宅補助制度(例:札幌市の次世代住宅補助)などと組み合わせることで、受け取れる補助金の総額を大幅に増やせる可能性があります。太陽光発電や蓄電池の設置費用に対する補助金などとも併用できるケースがあるため、経済的な負担を大きく軽減できるでしょう。
ただし、同一の支出に対して重複して補助金を受け取ることはできません。また、併用する制度側で制限が設けられている場合もあるので、各制度の要件を事前に確認することが重要です。
03HWHの認定を受けて補助金を活用するには?申請の流れをチェック
HWH認定住宅の補助金制度は、北海道の「道産木材住宅建設促進事業」による制度です。スムーズに補助金を受け取れるよう、申請の流れとポイントを把握しておきましょう。
ステップ1|認定申請の準備と手続き
設計時にHWH認定基準を満たしているかを確認し、必要書類を北海道に提出します。申請に必要な書類は以下のとおりです。また、申請は「建築主」およびHWHメンバーに登録されている「設計者」「施工者」のいずれかが行えます。
- 認定申請同意書
- 建築確認済証の写し(建築確認が不要の場合はこれに代わるもの)
- 道産木材製品が使用されていることが証明できる書類の写し
(合法木材証明書、納品書、伝票、設計図面など) - 推奨基準を満たす場合:道産木材製品の使用量及びZEH水準に適合していることが証明できる書類の写し
(BELS評価書、住宅性能評価書、長期優良住宅建築等計画認定通知書など)
審査を通過すれば、認定証と「HWHマーク」が交付されます。このマークは、道産木材を活用した質の高い住宅であることの証明となります。
ステップ2|補助金の公募開始を待って申請
HWH認定を受けた後は、別途「補助金申請」を行う必要があります。補助金の申請は抽選や先着順ではなく、公募型(要件を満たせば原則採択)である点が特徴です。ただし、予算枠に達すると受付が終了する場合があるため、早めの準備が欠かせません。
2025年度は、第1回受付が7月14日~8月1日に実施され、第2回受付は11月頃の予定です。必ず最新情報を確認してスケジュールを立てましょう。
ステップ3|工事完了後の実績報告と補助金交付
HWH認定住宅の補助金交付は住宅完成後です。まず、交付対象となった事業者が「実績報告書」を北海道に提出し、内容確認を受けます。この書類審査を通過して補助金交付という流れですが、書類に不備があると支給が遅れる可能性があります。そのため、建築主と施工業者が密に連携し、正確な書類を準備することが重要です。
04HWHを活用した家づくりはどんな人におすすめ?
北海道で注文住宅を建てる際、HWHの活用をおすすめしたい人の特徴を紹介します。「自分に当てはまる」と感じた場合は、HWH認定取得を目指してみてはいかがでしょうか。
木の家・自然素材にこだわりたい人
無垢材や自然素材を使った家は、一般的な住宅に比べてコストがかかる傾向がありますが、補助金制度を活用することで高品質な木の家を手の届きやすい価格で建てやすくなります。自然素材の調湿性や断熱性は、乾燥しやすい冬季や夏の湿気が気になる季節にも有効です。道産木材を使用することが要件のHWH制度を活用することで、地域に貢献しつつ、北海道の四季に合った快適な空間づくりが実現します。
家づくりコストを少しでも抑えたい人
HWH推奨基準を満たした住宅は、北海道の補助金や住宅ローンの金利優遇を受けられる可能性があります。要件を満たす場合には他の補助金制度との併用が可能なこともあり、総合的に見ると建築コストを軽減できるケースが少なくありません。
寒冷地である北海道では、家の断熱性能の高さが光熱費の削減につながるため、初期費用とランニングコストの両面でメリットが期待できます。特に子育て世帯や若年層にとって、家づくりの初期費用を軽減しながら快適な暮らしを実現できるのは、大きな魅力といえるでしょう。
北海道で地元に貢献できる家を建てたい人
道産木材を積極的に使用するHWH制度を利用することで、北海道の林業や製材業など地域経済の循環に直接貢献できます。また、地元の森林資源を活かした家づくりは、森林の適切な管理やCO₂削減にもつながり、環境保全に貢献したいと考える人にも最適な制度です。
05北海道で家を建てるならHWH制度の活用は必見!
北海道で家を建てるなら、2025年6月にスタートした「HOKKAIDO WOOD HOUSE(HWH)」制度の活用を検討しない手はありません。北海道産の木材を使った高品質な家づくりができるだけでなく、補助金や住宅ローンの金利優遇を受けられる可能性があります。国や自治体の補助制度と併用できるケースも多く、上手に活用すれば家づくりにかかるコストを大きく抑えられるでしょう。
ただし、補助金や優遇制度でお得になるとはいえ、実際の自己負担額や月々の返済額を把握しておくことは大切です。そこでおすすめなのが、当サイト内の住宅ローンシミュレーターです。借入希望額などを入力するだけで、かんたんに月々の返済額を試算できるため、補助金を含めた総費用をイメージして無理のない資金計画を立てましょう。

監修:新井智美
CFP®/1級ファイナンシャル・プランニング技能士
プロフィール
トータルマネーコンサルタントとして個人向け相談の他、資産運用など上記相談内容にまつわるセミナー講師を行う傍ら、年間100件以上の執筆・監修業務を手掛けている。