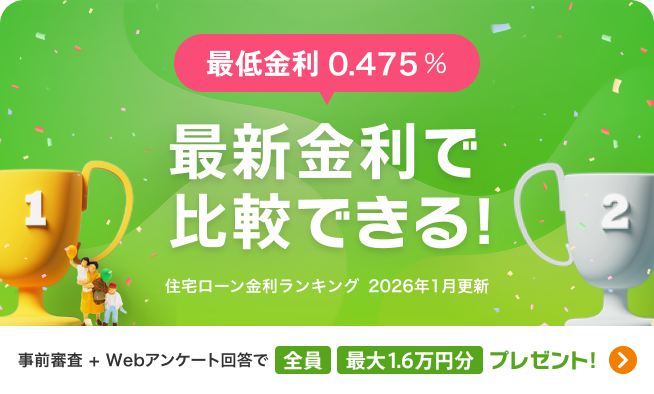約8割が変動金利を選択!2025年の住宅ローン利用実態を最新調査から読み解く
住宅ローンの利用にあたっては、借入額や返済期間などたくさんの項目で決断を迫られますが、その中でも多くの人が最初に悩むのが「金利タイプを変動型と固定型、どちらにするか」でしょう。2025年4月の住宅金融支援機構の調査によると、実際の住宅ローン利用者のうち約8割の人が「変動金利」を選んだことが明らかになりました。日銀の金融政策の転換や物価上昇の影響を受けて、今後の住宅ローン市場では金利上昇が懸念されているにもかかわらず、なぜここまで変動金利が支持されているのでしょうか。 そこで、今回は住宅金融支援機構の調査結果をもとに、住宅ローンの金利タイプの選ばれ方や返済期間、借入額の実態などを解説します。住宅ローン利用者のリアルな現状を紹介するので、これから借り入れを検討する方は参考にしてください。
- 012025年最新調査で判明!住宅ローン利用者の約8割が変動金利を選択
- 変動型が選ばれる背景とは?
- 固定期間選択型・全期間固定型の利用率は減少傾向に
- 世代によって異なる金利タイプの選び方
- 02返済期間は長期化の傾向に!35年超のローンが増加中
- 主流は「30〜35年」、一方で「35年超〜50年」もじわり増加
- 若年層ほど長期ローンを選択する傾向に
- 03借入金額・返済負担率は?
- 自己資金はどれくらい?融資率90〜100%が最多
- 返済負担率は「15~20%」がボリュームゾーン
- 04金利上昇をどう見ている?住宅ローン利用者の見通しと不安
- 約半数が「金利は上昇する」と予想
- 金利リスクへの理解と備えに温度差あり
- 「備えはない・分からない」が増えている現実
- 05住宅ローン選びで後悔しないために
012025年最新調査で判明!住宅ローン利用者の約8割が変動金利を選択
住宅金融支援機構が2024年10月から2025年3月までに住宅ローンの借り入れをした人を対象にした調査では、79%の人が変動金利を選択しました。これほど多くの人が変動金利を選ぶ背景には現在の金利水準や世代ごとの価値観の違いなど、さまざまな要因が関係しています。
そこで、まずは住宅金融支援機構の「住宅ローン利用者の実態調査」の最新データ(2025年4月調査)をもとに、金利タイプの選択傾向とその理由を詳しく解説していきます。
変動型が選ばれる背景とは?
現在の住宅ローンで変動型が多く選ばれている最大の理由は「金利水準の低さ」です。日銀がマイナス金利を解除した影響で住宅ローン金利は2024年半ばから上昇傾向ですが、変動型に関してはまだ年0.5~0.6%程度で借りられる商品が多く、月々の返済額がそれほど大きな負担にならない場合があります。
また、これまでの住宅ローン金利の推移から「金利が急激に上がるリスクは少ない」と考える利用者もおり、当面の負担軽減を優先し商品を選ぶ傾向が続いているようです。フラット35などの全期間固定型は完済まで金利が変わらない安心感はあるものの、契約当初の金利は変動型より高く設定されるため、少しでも住宅取得コストを下げたい人たちに敬遠されがちである点も、変動型が選ばれる傾向が続く要因となっています。
固定期間選択型・全期間固定型の利用率は減少傾向に
選択した金利タイプの調査結果では変動型の人が79%もいるのに対し、固定期間選択型は12.2%(前回調査比-1.3%)、全期間固定型は8.8%(同-0.2%)しかいないうえ、どちらも前回よりわずかに減少しています。
固定型は返済額が変わらない安心感はありますが、初期金利が高めであることがネックとなり、「変動型よりも割高」という印象から敬遠されやすいようです。特に物価上昇や建築費の高騰で都市部を中心に住宅価格が高くなっている状況においては、月々の負担を少しでも抑えたい層を中心に変動金利が選ばれやすい環境となっています。
一方で、住宅ローン利用予定者を対象とした調査では、2024年4月以降に固定型を選びたいという意向が増加に転じており、「利用実績」と「今後の意向」にギャップが生じている点も見逃せません。こうした背景を踏まえると、今後の金利動向が利用者の判断に一層大きな影響を与えることが予想されます。
その金利動向を示す一例として、固定型の金利に連動することの多い長期金利は、2025年7月15日に1.595%まで急上昇しました。この要因としては参議院選挙を前にした各党のばらまきによる日本の財政悪化への懸念や日銀の金融政策修正を背景にした動きが関係していると考えられます。
長期金利が上昇すると、金融機関によっては全期間固定型だけでなくその他の金利タイプにも影響する恐れがあるので、変動金利の人も「長期金利が上がっても関係ない」という楽観視はできない状況です。これから住宅ローンを選ぶときは借入当初の金利の低さだけでなく、将来の金利上昇を見据えた柔軟性のある返済計画を踏まえた選択がますます重要になるでしょう。
世代によって異なる金利タイプの選び方
利用した住宅ローンの調査結果では、30代以下の若年層ほどペアローンや収入合算の商品を選択する(30~39歳で約42%、20~29歳で約67%)傾向が強いです。一方、40歳以上ではペアローン・収入合算ともに利用していない人の割合が約75%に上るなど、できるだけリスクを避ける姿勢がうかがえます。
こうした動きの背景には「共働きで今の収入に余裕がある若年層」と「教育費や老後資金も見据えた堅実な返済計画を考える中高年層」とのライフステージの違いが影響していると考えられます。収入の安定性や将来設計によって選ぶべき商品や金利タイプが異なるという点は住宅ローン選びの重要なポイントです。
02返済期間は長期化の傾向に!35年超のローンが増加中
今回の住宅金融支援機構の資料では、住宅ローンの返済期間についても調査しています。それによると、最も回答が多かったのは「30年超〜35年以内」でした。しかし、35年を超える超長期住宅ローンの利用者も着実に増えており、今後のスタンダードとなる可能性もありそうです。ここからは住宅ローンの返済期間に関するデータと傾向を解説します。
主流は「30〜35年」、一方で「35年超〜50年」もじわり増加
返済期間の項目を見ると、最も回答が多かったのは「30年超~35年以内」の45.8%で、前回調査(48.6%)より2.8%減少しているものの、依然として主流であることがわかります。一方で注目すべき傾向としては、「35年超~50年以内」の住宅ローン利用者が25.5%と前回調査(20.9%)に比べ4.6%ほど増えたことです。
こうした住宅ローンの長期化が進んでいる背景には、「住宅価格や建築費の上昇による借入額の増加」によって、「毎月の返済額を抑えるために返済期間を延ばす選択肢が現実的になっている」という事情があります。すでに一部の金融機関では「40年ローン」や「50年ローン」を取り扱う動きが活発化しているなど、長期返済を前提とした住宅取得の選択肢が広がりを見せています。
若年層ほど長期ローンを選択する傾向に
返済期間の長期化は、特に20代~30代の若年層で顕著となっています。住宅ローンの仕組み上、返済期間が長くなるほど利息を含めた総返済額は増えてしまいますが、その一方で毎月の返済額は抑えられるので家計が楽になることもあります。人生の早い段階で住宅を購入する世代にとっては、長期ローンを選ぶことで月々の返済負担を軽減し、これからかかる教育費や生活費とのバランスをとりやすくなる点が魅力的に映るのでしょう。
また、若年層ならではの考え方として将来の収入増加を見越し、「今は生活に余裕をもたせ、総返済額が増える分は繰り上げ返済で調整する」という柔軟な返済スタイルを想定できる点も超長期住宅ローンを選びやすくなっている要因だといえます。
03借入金額・返済負担率は?
ここまで、住宅ローン利用者の金利タイプの選択や借入期間の現状について紹介してきました。しかし、これから住宅ローンの利用を考えている方の中には、「実際の借入金額や返済負担率」が気になる人もいるでしょう。住宅購入者の資金計画の実態はどのようになっているのでしょうか。
自己資金はどれくらい?融資率90〜100%が最多
融資率(借入額÷住宅価格)について調査した項目を見ると、「90%超~100%以下」の人が26.5%と最も多いという結果でした。このことから、住宅ローン利用者の4人に1人はほとんど自己資金がない、もしくは諸費用程度しか用意していないようです。
また、「80%超~90%以下」(15.5%)、「100%超」(13.5%)も含めると融資率が80%を超える人の割合は55.5%で、半数を超える人が多くの融資を受けて住宅ローンを利用していることがわかります。
一部では自己資金をしっかり用意している人もいるものの、この調査結果からはかつて「頭金は2~3割程度必要」といわれていた住宅ローンの常識が変わりつつあることが読み取れるでしょう。融資率の増加は建築費高騰や都市部を中心にした住宅価格の上昇はもちろん、それに加えて「低金利を最大限活用したい」「手元資金を残しておきたい」といった利用者の考え方も背景にあると考えられます。
返済負担率は「15~20%」がボリュームゾーン
融資率は増加傾向にある一方で、返済負担率(年間返済額※ ÷ 年収 × 100)はこれまでとほとんど変わらず手堅く推移しています。同調査の返済負担率を見ると、「15%超~20%以内」が24.3%で最も多く、続いて「10%超~15%以内」(21.2%)、「20%超~25%以内」(18.0%)という結果でした。一般的に住宅ローンを組む際は返済負担率25%以内が家計に無理なく返済できる目安だといわれており、多くの利用者がその範囲内に収めようとしていることがわかります。
ただし、返済負担率が高くない世帯でも共働きを前提で収入合算している場合は、将来の収入変動やライフイベントに備えた余裕を持った返済計画を立てておいたほうが無難です。将来設計をしっかり考えたうえで、無理なく返済を続けられるラインを見極めることが住宅ローン返済の長期的な安定につながります。
04金利上昇をどう見ている?住宅ローン利用者の見通しと不安
2025年は日銀の金融政策の正常化や物価上昇を受けて、長期金利にじわじわと影響が出始めたタイミングです。しかし、今回の調査では金利上昇の懸念を抱きつつも十分な備えをしていない人も多く、「わからないまま借りる」ことのリスクが浮き彫りになっています。そこで、最後に住宅ローン利用者の金利見通しとその備え方の現実について解説します。
約半数が「金利は上昇する」と予想
「今後1年間で住宅ローン金利がどうなると思うか」という質問に対しては、65.7%の人が「現状よりも上昇する」と答えており、前回調査時(62.9%、2024年10月)よりも2.8%増えました。また、「ほとんど変わらない」は23.2%、「現状よりも低下する」は1.8%で金利が現状維持もしくは下がると考えている人は少数派であることがわかります。
しかし、実際に選んだ住宅ローンのタイプ別に金利が「現状よりも上昇する」と答えた人をみると、全期間固定型61.4%、固定期間選択型49.7%なのに対し、変動型が68.8%と最も高くなっています。つまり、金利上昇リスクを感じつつも、毎月の返済額を抑えることを優先して変動金利を選択している人が多いのが現実のようです。
金利リスクへの理解と備えに温度差あり
住宅ローン金利の見直しルールなど、「自分のローンにおける金利リスクをどの程度理解しているか」という質問に対しては、変動型・固定期間選択型の利用者のうち約50%が「十分理解している」または「ほぼ理解している」と回答しました。その一方で、「理解しているか少し不安」「よく理解していない」「全く理解していない」と答えた人も約50%いて、リスク意識には大きなばらつきがあるようです。
一般的に住宅ローンには金利上昇が起きた場合でも、毎月の返済額が急激に増加しないように5年ルールや125%ルールが設定されています。最近ではネット銀行を主流に5年ルールや125%ルールを設けていないところも出てきています。回答結果からは返済額見直しの仕組みについて理解していない人が一定数いることが読み取れ、将来的に金利上昇が起きたときに返済に困るリスクが懸念されます。
「備えはない・分からない」が増えている現実
先述したように、多くの人が今後の金利は上昇すると考えていますが、具体的な対策はあまり考えていないのが現実のようです。金利が上昇し、返済額が増加した際の対応について聞いた質問では、「繰り上げ返済」や「借り換え」などの具体策を挙げる人も一定数いますが、「検討がつかない、わからない」と答えた人もいました。
特に「検討がつかない、わからない」と答えた人の割合は、毎月の返済額が増加したケースほど多く(1万円増加では19.2%だが5万円増加では44.0%の人が選択)、返済額が大幅に増えた際の備えができてない現状が浮き彫りになっています。必要な情報にアクセスできていないことが「備えがないまま借りる行動」につながっている可能性もあり、実際に住宅ローンを利用する際はこうした情報格差を事前に埋める取り組みが重要だといえます。
05住宅ローン選びで後悔しないために
今回紹介した住宅金融支援機構の最新調査からは「低金利を活かしたい」という利用者の意識の強まりと、それに伴う変動型への圧倒的な支持がわかりました。しかし、それと同時に返済期間の長期化やフルローンに近い借り入れ、金利リスクへの備えの不十分さなど将来的な不安要素も浮かび上がっています。住宅ローンは多くの人にとって長期にわたる大きな契約であり、目先の金利や月々の返済額だけで判断すると思わぬ後悔を招くかもしれません。
住宅ローン選びで後悔しないためにも、自身や家族のライフプランに合った金利タイプと返済期間を選ぶことと、将来の収支変化を見据えた余裕ある返済計画を立てることが重要です。当サイト内には自分にぴったりな予算を考えるのに役立つ4つの住宅ローンシミュレーターがあります。これから住宅購入を検討している方は、まずは住宅ローンシミュレーターを活用して、資金計画を立てることから始めてみてください。

監修:新井智美
CFP®/1級ファイナンシャル・プランニング技能士
プロフィール
トータルマネーコンサルタントとして個人向け相談の他、資産運用など上記相談内容にまつわるセミナー講師を行う傍ら、年間100件以上の執筆・監修業務を手掛けている。
関連キーワード