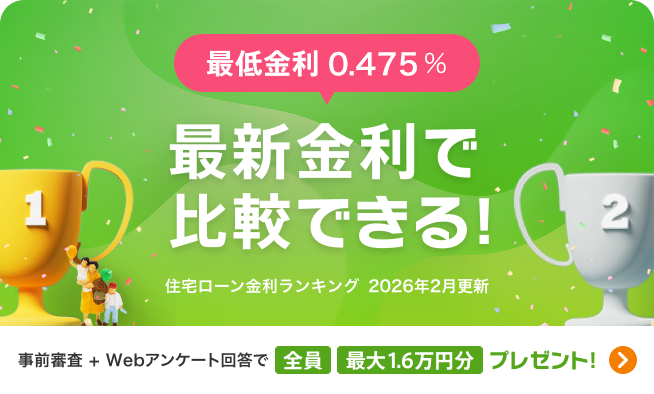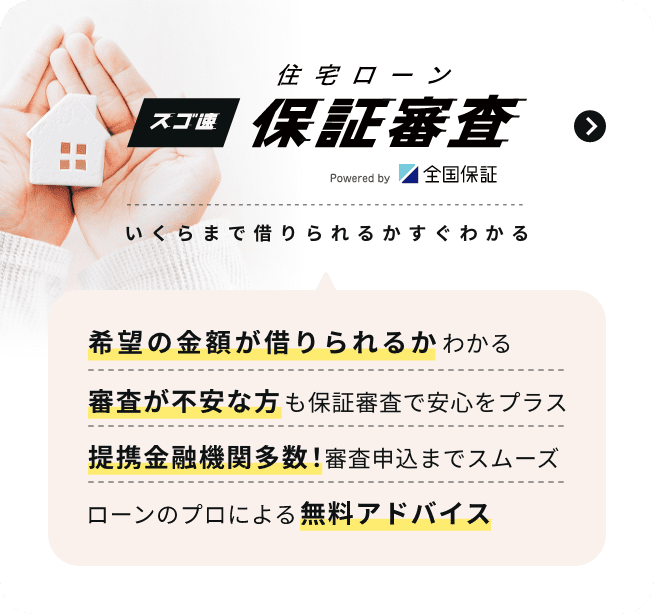【予算別】2025年の住宅市場&住宅購入のコツ、住宅ローンの選び方
三菱UFJ信託銀行が行った「2024年度下期 デベロッパー調査」によると、現在の不動産市場は価格帯別に異なる動きがみられるとのことです。例えば戸建てでは、8000万円以上1億円未満の高価格帯の物件は、さらに販売価格の上昇傾向が見られる一方で、8000万円未満の中~低価格帯の物件では価格の横ばい、またはやや下落する傾向があると報告されています。 不動産は需要と供給で価格が決まるため、ニーズの強さによって交渉に大切なポイントが変わります。また、購入価格は住宅ローンの総返済額に大きく影響するので、価格帯別に自分に合った住宅ローンを知っておくとよいでしょう。 本記事は、2025年の住宅市場の最新動向を紹介し、さらに価格帯別に住宅購入の成功戦略や住宅ローンの選び方について解説します。
01【首都圏】2025年、住宅市場の最新動向
三菱UFJ信託銀行がマンションデベロッパー25社、戸建てデベロッパー12社に対して行った調査(2025年1月時点)によると、直近のマンションおよび戸建て住宅の供給は、どちらも用地価格が予想以上に高騰しているなどの理由から減少傾向にあります。
特にマンションでは、価格が上昇したことにより、高価格帯を中心に販売が鈍化傾向にあります。都心部などの物件では、価格の上昇が落ち着きつつあるという見方も出ています。一方、戸建ては建築コスト上昇の影響を受けているものの、郊外型のニーズが依然として強く、マンションに比べると引き続き堅調とのことです。
また、住宅ローンに関してはこれまで低金利の恩恵を大きく受けられる変動金利を利用する消費者が多かったのですが、昨今の日銀の利上げ路線の影響を受けて固定金利の利用を検討する人が増加しています。仮に今後も住宅ローン金利が上昇した場合、消費者の購買意欲が減退し、特にマンションにおいては、さらなる供給戸数の減少や販売価格の下落が懸念されています。
02予算別に考える、住宅購入のポイントとは?
上述したように、三菱UFJ信託銀行の調査によるとマンション・戸建てともに全体の供給数は減少傾向ですが、価格帯によってその動きには違いがあるようです。そこで、ここからは価格帯別の住宅市場の動向と、最適な購入戦略について解説します。
高価格帯(8000万円以上1億円未満)
高価格帯の物件の特徴は販売数が鈍化しているため、購入にあたり値引き交渉の余地があることです。その傾向は特にマンションほど顕著なので、この価格帯の物件購入を考えている人は交渉するときに少し強気にでてみるのもよいでしょう。高価格帯の物件で値引き交渉しやすい理由としては以下の3つが挙げられます。
- 高価格帯の物件は購入者が限定される
- 販売が長引くと売主にとって不利になる
- 価格設定がもともと「余裕を持って高め」に設定されている
まず1について、高額物件はそもそも年収が高い層など購入できる人が限られています。住宅ローン審査のハードルも高く、人気の高い物件でも実際に購入できる人はそれほど多くありません。つまり、価格が安い物件に比べると競争相手が少ないため売れ残りやすく、販売する側も値引きに積極的に応じるケースがあるというわけです。
次の2については住宅を売る側の事情が関係しています。個人、企業ともに住宅を売る側は在庫を抱えている間は維持費がかかるため、できるだけ早く売り切りたいと考えています。そのため、第1期、第2期など決められた販売時期の終盤に差し掛かると価格交渉に応じてもらいやすいです。戸数の多いマンションでは、一気に全戸を売り出すと空室が発生する可能性があり、人気のないマンションという印象を与えてしまいがちです。そのようなケースを避けるため、不動産会社では分割して販売を行う方法がよく見られます。募集が何期なのか、また最終記なのかは不動産会社のホームページなどで確認できます。特に住み替えや資産整理を目的としている場合は相手側が短期間で売却したいケースが多いので、交渉に応じてくれる可能性が高いでしょう。
最後に3は、高価格帯はお金を持っている富裕層向けの物件なので、最初から価格が高めに設定されていることが多いからです。富裕層は気に入った物件ならあまり価格を気にせず購入するので、人気のある物件は早期にフルプライス(定価)で売れてしまうことも少なくありません。
反対にいうと、上述したような「販売が長引いている物件」は値下げに応じてくれることがよくあります。売る側の都合で早く売り切りたい場合は「完成済みの新築物件」でも交渉に乗ってくれることもあるので、高価格帯の物件は積極的に値下げ交渉をしてみることをおすすめします。
中価格帯(4000万〜8000万円)
4000万~8000万円の中価格帯の特徴は「価格上昇の影響を受けやすく、値引き交渉しにくい」ことです。そのため、住宅購入者の間で予算オーバーするケースが増加しており、価格高騰が顕著な都心部の新築マンションよりも中古や都心部以外の戸建てを検討する人が増えています。中価格帯の住宅が値引き交渉しにくい理由は以下の3つが挙げられます。
- 需要が安定していて、売れやすい
- 価格設定がシビアで、値下げの余地が少ない
- 売主(特に新築デベロッパー)が価格を崩したくない
1については、中価格帯がデベロッパーの対象とする顧客の最も多いゾーンに該当しているからです。この価格帯は世帯年収600万~1500万円程度の人がよく購入するため、高価格帯に比べて購入希望者が多く、競争率が高いため、売主側も値引き交渉には強気の姿勢で臨んでくることが多いでしょう。特に新築マンションは人気エリアで抽選になるほど販売好調なため、値下げ交渉はほぼ不可能な状況となっています。
次に2はこの価格帯の物件は最初から市場相場とほぼ同等に設定されているからです。中価格帯の顧客は高価格帯に比べると予算がそれほど潤沢ではないので、売主が「交渉前提の上乗せ価格」を提示していないことが多いです。つまり、もともと適正価格で販売されていることが多く、価格交渉の余地があまりないといえます。
最後に3はこの価格帯のマンションの販売戸数が多いからです。中価格帯は対象となる顧客が多く、その分だけ供給数もほかの価格帯に比べると多いので、売主は一部の値引きが他の契約に影響することを特に警戒しています。例えば、同じマンション内で1戸だけ値引きすると、他の買主からも値引きを要求されるかもしれません。それがどんどん広がっていくと、全体の販売額は大きく減少してしまうでしょう。
以上のことから、特に新築を中心として「最終的な売れ残り在庫」以外は価格交渉しにくい状況となっています。そのため、中価格帯で予算オーバーしそうな場合は「新築の売れ残りで値引き交渉してみる」または「中古物件をリノベーションする」という選択肢を視野に入れるとよいでしょう。
低価格帯(4000万円以下)
4000万円以下の低価格帯は中価格帯よりもさらに値引き交渉をするのは厳しいです。その理由としては、以下の2つが挙げられます。
- 競争率が高い
- 不動産投資の対象になることが多い
1は住宅価格が高騰している状況において、特に都心部を中心に4000万円以下の物件は不足気味で消費者間の競争が激しくなっているからです。住宅としては手ごろな価格であるため、購入希望者が多く早い者勝ちですぐに契約が決まってしまうことも珍しくありません。そのため、売主側としては値引きをする必要性をあまり感じない価格帯となっています。
一方、2についてはこちらも不動産としては購入しやすい価格であることから、特に利便性の高い駅近やリノベーションをして付加価値を出しやすい築古の物件を中心に中古住宅を購入したあと、転売もしくは賃貸住宅に転用するニーズが高いです。そのため、一般消費者が購入するには決断までのスピード感が求められます。
以上のことから、低価格帯の住宅は基本的に価格交渉の余地がほとんどありません。特に人気の新築物件の値引きは難しいため、価格交渉の代替策としてエアコン・カーテン・照明などの設備面のサービス追加を交渉するのがおすすめです。
ただし、低価格帯であっても中古住宅についてはマンション、戸建てともに値引き交渉できる場合があります。狙い目としては「売主が個人(早く手放したいと思っている可能性が法人所有物件よりも高い)」「市場に長期間売れ残っている(目安は3ヵ月以上)」「築年数が古い(築20年以上はリノベーション前提だから)」の3つです。交渉の際はリフォームや修繕が必要なポイントを指摘したうえで、売り出し価格の5~10%程度を目安にすれば、値引き交渉が成立する可能性が高まります。
なお、売主側にとって即決してくれる買主はありがたい存在です。住宅ローンの事前審査を通しておけば、スムーズな契約につながり、売主が値引きに応じやすくなる可能性もあります。そのため、交渉の前に住宅ローンの事前審査を受けておくことをおすすめします。
03【予算別】2025年の住宅ローン、どう選ぶ?
現在の住宅市場は価格帯別にニーズの強さが異なり、それによって値引き交渉のしやすさや購入に必要なスピード感に違いがあります。しかし、いずれにしても住宅を探す前に住宅ローンの事前審査を受けておいたほうが交渉材料の1つになるうえ、手続きがスムーズに進むでしょう。そこで、ここからは価格帯別に選ぶべき住宅ローンの金利タイプや審査に通るためのポイントを紹介します。
高価格帯は固定金利が無難。ただし例外もあり
基本的に、住宅ローンは高額な借り入れをするほど金利上昇の影響を受けやすいといえます。借り入れする額にもよりますが、この価格帯では金利が0.5%上がるだけでも、総支払額が数百万円単位で増加する可能性があります。そのため、現在のような金利上昇局面にあるときは変動金利でリスクを取るよりも、やや高めでも固定金利で安定性を重視する方が無難です。
また、全期間固定型は契約時に総支払額が確定するため、金融機関側にとって貸し出しリスクが低く、審査が通りやすいです。もともと富裕層向けのサービスであるプライベートバンキングが提供するローンでは固定金利を提案されるケースが多いので、そうした提案を受けたら前向きに検討してみることをおすすめします。ただし、現金資産に余裕があって、短期間で繰り上げ返済できる人や借入比率が低い人などは、金利上昇時のリスクヘッジが十分にできる人はこの限りではなく、変動金利が適しているケースもあります。
中価格帯は変動金利が有利だが、固定金利も検討の余地あり
中価格帯は高価格帯に比べると金利上昇リスクを受けにくいこともあって、一般的に「変動金利+繰り上げ返済」を選択する人が多いでしょう。金利が徐々に上がってきているとはいえ、まだ低金利による利息負担軽減の恩恵を受けやすい状況です。そのため、良いタイミングで繰り上げ返済できれば総支払額の抑制も期待できます。
ただし、中価格帯でも世帯年収によっては十分高い買い物になるので、長期間の安定を重視するなら固定金利を検討するのもよいでしょう。仮に変動金利と固定金利のどちらにするかを迷う人はミックスローンも選択肢の1つです。
また、頭金は10~20%ほど用意すると金利優遇を受けやすくなります。住宅ローン控除を活用しながら、30~35年の計画的な返済計画を作成することが大切です。
低価格帯は変動金利が基本。ただしリスク管理が重要
低価格帯も中価格帯と同じように、低金利の恩恵を受けやすい「変動金利+繰り上げ返済」が主流です。ただし、金利上昇時に変動金利を選択していると確実に総支払額は増えるので、リスクが怖い人は頭金をできるだけ多く用意して借入金額を抑えたり、住宅ローン控除を活用したりして、毎月の返済負担軽減を図るとよいです。そのうえで、資金に余裕があれば繰り上げ返済を検討することをおすすめします。
なお、低価格帯は他の価格帯に比べると借入金額が少ないので、金利上昇時の総支払額増加の影響を受けにくいです。そのため、固定金利は金利上昇リスクが特に心配な場合の選択肢に限られます。基本的には変動金利を選択し、金利上昇リスクには頭金や繰り上げ返済を活用して、借入金額を抑えることが有効です。
04住宅ローンは金利タイプの選択が重要!繰り上げ返済も計画的に
経済情勢の変化などを背景に、日本の住宅市場では価格帯ごとに消費者ニーズが変化しています。そのため、これから住宅を探す人は、価格帯に応じて「どのような交渉が有効か」「どのタイミングで決断すべきか」といったポイントを事前に把握しておきましょう。
住宅ローンを組む際には、変動金利や固定金利といった金利タイプの選択によって将来的な総支払額が大きく変わります。しかし、金融機関ごとに適用金利や条件が異なるため、「どの金融機関が自分にとって最適なのか」を見極めるのは簡単ではありません。住宅ローン選びで失敗しないためには、複数の金融機関を比較し、自分に合った住宅ローンを見つけることが不可欠です。当サイトでは、住宅ローンの返済計画の作成に役立つシミュレーターや、金利タイプ別に比較できる「最新金利ランキング」をご用意しています。住宅ローンを検討している人は、ぜひご活用ください。

監修:新井智美
CFP®/1級ファイナンシャル・プランニング技能士
プロフィール
トータルマネーコンサルタントとして個人向け相談の他、資産運用など上記相談内容にまつわるセミナー講師を行う傍ら、年間100件以上の執筆・監修業務を手掛けている。