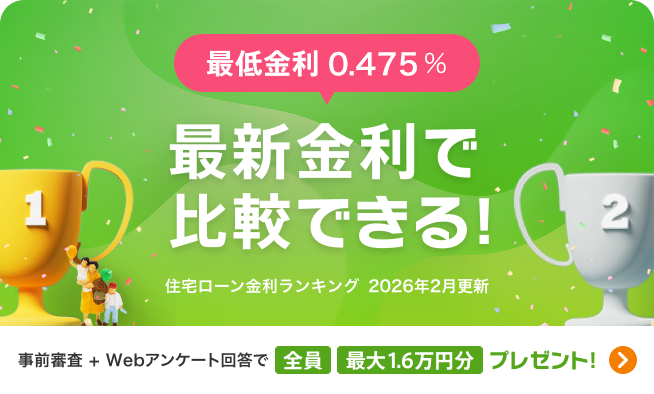2025年4月に変わる建築基準法、マイホーム購入希望者が知っておくべきポイント
住宅は安心して暮らすことができるように、建築基準法で構造や設備などの最低基準が定められています。そんな住宅を建てる際のルールともいえる建築基準法が2025年4月1日から大きく改正されることをご存じでしょうか。今後は同法改正によって、今まで以上にマイホームの安全性や省エネ性能を高めることが求められ、従来よりも安全・快適に暮らせるようになります。 しかし、その一方でこれから住宅を購入・建築する人にとっては手続きやコスト面での影響が避けられません。そこで、この記事では一般の住宅購入希望者が知っておくべき、2025年4月1日から適用される建築基準法の改正内容について紹介します。
01これまで簡略化されていた「小規模住宅」の耐震性・安全性チェックが義務化に
2025年4月1日から適用される建築基準法の中で、大きな変更があったのが「4号特例の縮小」です。4号特例とは建築基準法第6条第1項第4号に当てはまる建築物において、建築士が設計した新築の小規模住宅(例:木造2階建て以下、延べ床面積500㎡以下)が構造や設備に関する一部審査を省略できる制度を指します。この特例によって、これまで該当する建築物は耐震性などの安全性能を示す指標となる構造計算が義務化されておらず、実際に建築確認申請時に構造計算書や構造関係資料の提出も求められませんでした。
しかし、改正後は4号建築物の記載がなくなります。これまで4号建築物として区分されていた建物は構造や延べ床面積などに応じて、審査省略制度対象外の新2号建築物(木造2階建て、木造平屋建て・延べ床面積200㎡超)と、審査省略制度の対象となる新3号建築物(木造平屋建て・延べ床面積200㎡以下)の2つに分けられます。
「小規模住宅」の耐震性・安全性チェック義務化による影響
4号特例が実質的に縮小されることで起きうる影響としては、「建築期間の延長」が挙げられます。なぜなら、新たに審査省略制度対象外の新2号建築物が増えて審査が厳格化されるため、ハウスメーカーや工務店が行わなければならない手続きが増えることが予想されるからです。仮にこれまでよりも引き渡しまでの期間が長くなるようであれば、引っ越しや入居スケジュールの変更を余儀なくされる人も出てくるかもしれません。
そのため、これから従来の4号特例に合致しそうな住宅を購入・建築する予定の人は、設計段階から余裕を持ったスケジュールを作成することが大切です。信頼できる建築士や業者と連携を密にして、必要な準備を計画的に行うことを心掛けましょう。4号特例縮小の詳細については以下の記事で詳しく解説しているので、興味がある方はこちらも読んでみてください。
02省エネ基準の義務化
建築基準法のもう1つの主な変更点は、「省エネ基準の義務化」です。省エネ基準とは「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(建築物省エネ法)」で定められている基準のことで、既存の制度でも一部の建築物ではすでに義務化されています。しかし、2025年4月からは原則として、すべての新築の住宅に対して省エネ基準を満たすかどうかの審査が建築確認手続きで行われ、基準を満たしていないと着工が認められません。
省エネ基準は「一次エネルギー消費量」と「外皮性能」という2つの指標で評価されます。一次エネルギー消費量とは空調や換気、照明、給湯などで使用されるエネルギーの総量です。簡単にいうと、住宅に暮らすときに消費するエネルギーを表す指標で、太陽光発電システムなどで自家発電する場合は、その創出エネルギー量を総量から差し引くことができます。
一方の外皮性能は外壁や屋根、窓といった建物の外皮部分の断熱性能を示す指標です。「UA値(外皮平均熱貫流率)」と「ηAC値(平均日射熱取得率)」の2つで表され、地域ごとに基準値が決められています。今後の住宅はこれらの基準を満たすことで省エネ性能が確保され地球温暖化の防止に役立つほか、快適な居住環境や光熱費削減に貢献することが期待されています。
省エネ基準の義務化による影響
省エネ基準の義務化によって、これからマイホーム購入を検討する世帯で懸念されるのは「コストの増加」です。省エネ基準を満たすには、これまでの一般的な住宅よりも高性能な断熱材や設備の導入が必須です。グレードの高い設備を導入すると建築コストが上がるため、従来と同じ基準で考えると予算オーバーするリスクが高まるでしょう。各自治体や国では消費者の負担を軽減するために省エネ基準の義務化に伴って各種補助金や減税措置を実施しているので、そうした制度を積極的に活用することをおすすめします。
例えば、国土交通省と環境省は2025年度から「GX志向型住宅」と呼ぶ新たな省エネ性能の基準を設け、それに該当する住宅を購入した世帯に補助金を支給する予定です。同制度では「7段階ある断熱性能等級が上から2番目の6以上」「住宅で消費するエネルギーを太陽光パネルなどの再生可能エネルギー設備などによって実質ゼロ以下に抑える」などの要件をクリアした住宅を購入するすべての世帯に1戸あたり最大160万円が支給されます。
なお、2025年度からはGX志向型住宅の設立によって、これまで実施されていた補助金は「ZEH」水準の住宅で1戸あたり80万円から40万円に、「長期優良住宅」で100万円から80万円にそれぞれ減額される見込みです。GX志向型住宅の詳細は以下の関連記事で詳しく解説しているので、こちらも参考にしてください。
03今後は家づくりの初期費用が増加する懸念も!住宅ローンシミュレーターで資金計画を立てよう
2025年4月1日から適用される改正建築基準法によって、これからマイホームを購入する世帯では、主に「4号特例の縮小による建築期間の延長」や「省エネ基準の義務化による建築コストの増加」が懸念されます。また、その他にも「接道義務を果たしていない物件や既存不適格建築物は再建築不可物件とみなす」といった改正も含まれているため、マイホームの新築・購入だけでなく、大規模リフォームにも影響が出る可能性もあります。
再建築不可物件であっても主要構造部を触らない部分的なリフォームは可能であるものの、建築基準法の改正によって住宅の取得にさまざまな影響が出ることが考えられます。これからマイホームの購入や既存住宅のリフォームを検討している人は、早めにハウスメーカーや工務店に相談することをおすすめします。
特に省エネ基準の義務化によって建築コスト上昇リスクが高まるほか、ZEH水準や長期優良住宅の補助金が減額されるなど、今後は初期費用が増加しやすくなることが予想されます。そのため、資金計画はこれまで以上にしっかり立てることが大切です。当サイトでは住宅ローンの資金計画作成に役立つ各種シミュレーターを用意しているので、これからマイホームの取得を考えている人はぜひ試してみてください。

監修:新井智美
CFP®/1級ファイナンシャル・プランニング技能士
プロフィール
トータルマネーコンサルタントとして個人向け相談の他、資産運用など上記相談内容にまつわるセミナー講師を行う傍ら、年間100件以上の執筆・監修業務を手掛けている。