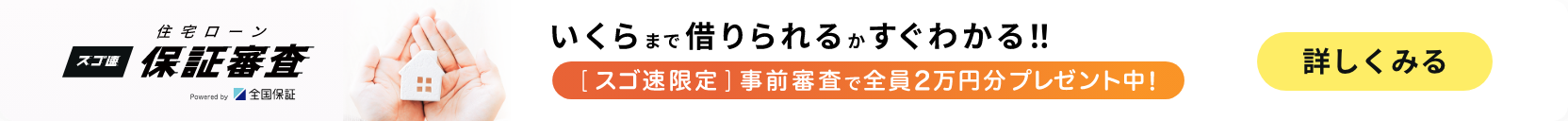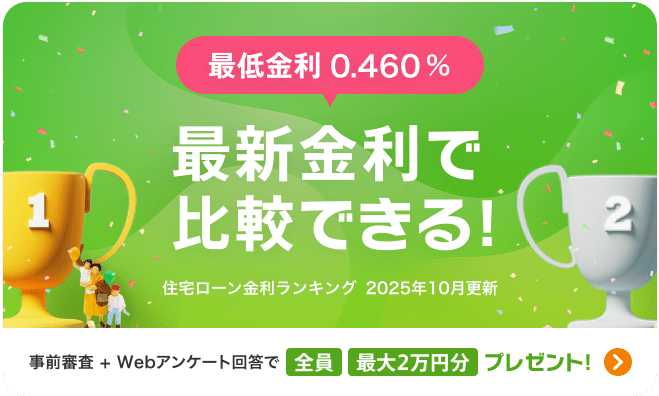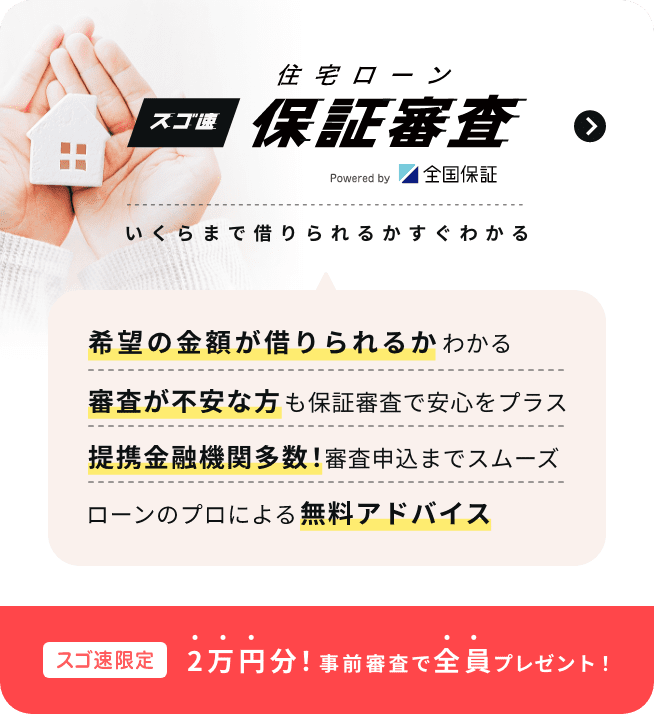長期金利が6年ぶり高水準 住宅ローン固定金利、変動金利への影響は?
2022年1月31日、住宅ローンに影響を与える長期金利は、約6年ぶりに一時0.185%まで上昇し、その後も上昇傾向が続いています。長期金利の上昇により、住宅ローン金利にはどのような影響が出ているのでしょうか?
016年ぶりの高水準となった長期金利
長く低水準が続いてきた住宅ローン金利に、変化が見え始めています。2022年1月31日には、住宅ローン金利に影響を与える長期金利の指標となる10年物国債利回りが0.185%まで上昇、日銀がマイナス金利政策を導入した2016年1月以来の高水準を記録しました。その後も長期金利は上昇傾向が続き、2月4日には0.2%を突破、以降は0.2%台で推移しています。長期金利の上昇を受けて、メガバンクなど主要金融機関は2月と3月、全期間固定型住宅ローンの適用金利を相次いで引き上げました。
今回の長期金利上昇の要因のひとつとして指摘されているのが、アメリカの長期金利上昇です。アメリカでは深刻なインフレ(物価上昇)を防ぐための金融政策の引き締めにより、2021年末ごろから長期金利が上昇、そのあおりを受けて日本の長期金利も上昇に転じたと考えられています。
では、長期金利が上がると、なぜ固定金利型住宅ローンの金利が上昇するのでしょうか?その理由は、各金融機関は全期間固定型の住宅ローンの適用金利を、主に長期金利を参考に決定するからです。
一方の変動型住宅ローンの金利についてはほとんどの金融機関が、日銀の金融政策の影響を受ける「短期プライムレート」という指標に1%を足したものを基準金利とし、そこから一定の利率を引き下げて適用金利に設定しています。日銀が今も大規模金融緩和政策を継続しているため、変動型の金利は引き続き年0.4~0.5%の低水準で推移しています。
これまでは、金利の低さを理由に全期間固定型ではなく変動型の住宅ローンを選ぶ人も多く、住宅金融支援機構の「住宅ローン利用者調査」(2021年10月)によると、2021年4月~9月に住宅ローンを利用した人のうち、67.4%が変動型の住宅ローンを利用しています。
02住宅ローン金利、今後の動きは?
では、これから住宅ローン金利はどのように推移していくのでしょうか。日本の住宅ローンの金利にも大きな影響を与えるアメリカの金融政策を見てみると、FRB(米連邦準備理事会)は2022年3月、2年ぶりにゼロ金利政策を終了、政策金利を0.25%引き上げました。さらに22年末までに7回の利上げを想定するとしています。
一方、日本では2022年2月14日、政府が長期金利の上昇抑制を目的に「指し値オペ」と呼ばれる公開市場操作を行うことを通知し、10年物国債を日銀が利回り0.25%で無制限に買い取ることによって、長期金利が0.25%以上に上がらないようにする方針を明らかにしています。アメリカや欧州が金融緩和の縮小に進む中、日本は金融緩和政策を維持することを宣言したことになります。
逆にいうと、今後日本の長期金利はアメリカの金利上昇に影響を受け、現在の水準よりも高い0.25%で推移していく可能性があるということです。そうなると、長期金利の影響を受ける全期間固定型住宅ローンの金利も上昇していく可能性があります。
変動型住宅ローンの金利については、日銀が指し値オペを行って金融緩和政策を維持する姿勢を明らかにしたことから、当面の間は低水準が続くものとみられています。
しかし、この先も金融緩和政策が維持される保証はなく、物価目標が達成されるなど一定の条件が出そろえば、日銀がアメリカに倣って金融緩和政策を見直す可能性は大いにあります。仮にそうなると、金融緩和政策により低く抑えられていた変動型住宅ローンの金利も上昇に転じることになります。
2021年以降、日本でも原油価格の高騰やサプライチェーンの停滞などを背景に、燃料や食料品など幅広い分野で値上げのラッシュが続いており、金融緩和策の見直しが行われるのではないかという観測も出ています。実際、「金融緩和政策が見直されて、変動金利が上昇するのでは?」との危惧から、各金融機関には全期間固定型の住宅ローンについての問い合わせや、変動型の住宅ローン利用者からの繰り上げ返済の相談が増えている旨が報じられています。
また、金利が上昇傾向であることや変動金利の先行きが見通せないことを理由に、マイホームの購入そのものを見送る人も増えていく可能性も考えられます。実際、金融緩和政策を見直したアメリカでは、住宅ローン金利の上昇が重荷となって住宅の販売件数が減少傾向に転じています。
この先、日本の金融政策や住宅ローン金利がどうなるのか、確かなことは誰にもわかりませんが、少なくとも、変動型住宅ローンの利用を検討している人は、金利上昇のリスクを十分に理解した上で慎重に判断すべきでしょう。
03金利の違いで月々の支払いはどのくらい変わる?返済額シミュレーターを使ってみよう
では、実際に金利の違いで毎月の支払額はどのくらい変わるのかを、「毎月の返済額シミュレーター」で試算してみましょう。例えば、変動型住宅ローンで4000万円を返済期間35年、ボーナス払いなしで借りた場合を想定し、年利0.5%と0.8%の場合で試算したところ、次のような結果になりました。
年利0.5%の場合
- 毎月の支払額:10万3834円
- 総支払額:4362万円
年利1.0%の場合
- 毎月の支払額:11万2914円
- 総支払額:4745万円
金利が0.5%上がると、毎月の支払額が1万円近く高くなり、総支払額も約150万円増えることがわかります。毎月の返済額シミュレーターでは、変動型、固定期間選択型(10年)、全期間固定型のそれぞれを選んだ場合の支払い金額の比較も可能です。住宅ローン探しや返済プランを立てる際に、ぜひお役立てください。

監修:相山華子
ライター、OFFICE-Hai代表、2級ファイナンシャル・プランニング技能士
プロフィール
1997年慶應義塾大学卒業後、山口放送株式会社(NNN系列)に入社し、テレビ報道部記者として各地を取材。99 年、担当したシリーズ「自然の便り」で日本民間放送連盟賞(放送活動部門)受賞。同社退社後、2002 年から拠点を東京に移し、フリーランスのライターとして活動。各種ウェブメディア、企業広報誌などで主にインタビュー記事を担当するほか、外資系企業のための日本語コンテンツ監修も手掛ける。20代で不動産を購入したのを機に、FP(2級ファイナンシャル・プランニング技能士)の資格を取得。金融関係の記事の執筆も多い。
関連キーワード