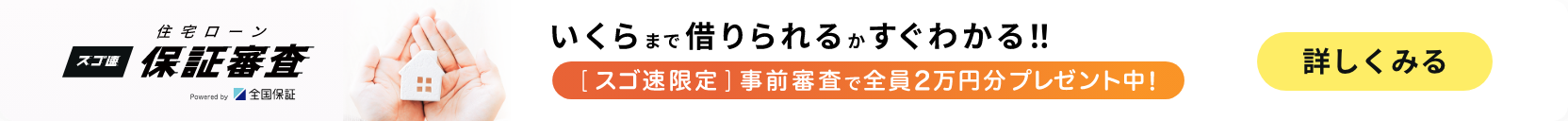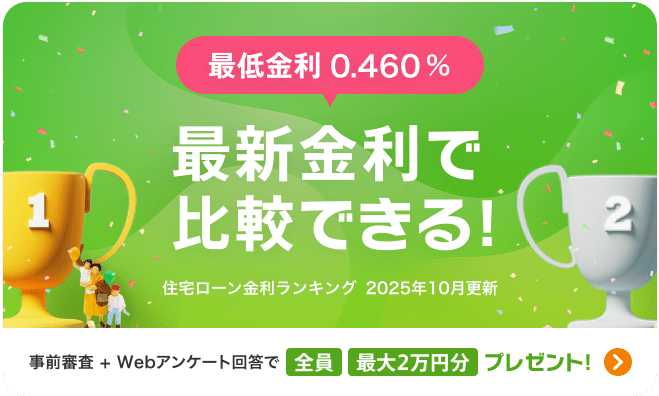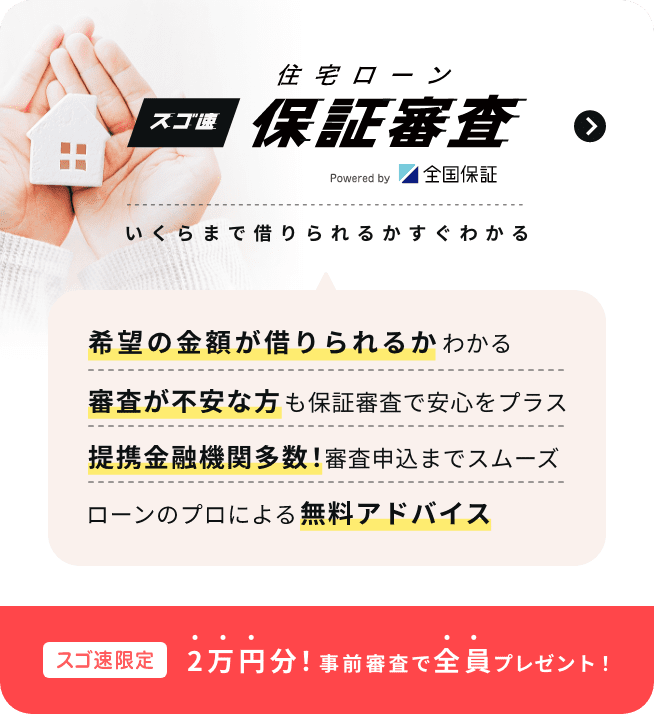建築条件付き土地は割安で購入できる?メリット・デメリットや契約の流れを解説
公益社団法人全国宅地建物取引業協会連合会(全宅連)は2021年8月25日、「建築条件付き土地」の取引に関連する宅建事業者の業務について、新たな契約書ひな形を作成すると発表しました。不動産の広告でよく目にする「建築条件付き土地」とはどのようなものなのでしょうか?そのメリットとデメリットも併せて解説します。
01建築条件付き土地とは
建築条件付き土地は、「売買契約後一定期間内に、売主が指定するハウスメーカーなどの施工会社で家を建てる(建築請負契約を結ぶ)」という条件がついた土地のこと。「一定期間」は土地ごとに異なりますが、一般的には売買契約後3カ月以内であることが多いようです。あらかじめハウスメーカーが建てた「建売住宅」に対して、建築条件付き土地は土地を売ってから住宅の建築を始めるので「売建住宅」と呼ばれることもあります。
建築条件付き土地の購入~入居までの流れ
建築条件付き土地の購入から入居までの一般的な流れは、以下の通りです。
- 土地の売買契約を結ぶ
- 土地の売主が指定したハウスメーカーと建築プランなどを話し合う
- 指定された期間内にハウスメーカーと建築請負契約を結ぶ
- 着工
- 完成・入居
なお、建築条件付き土地の場合、建築請負契約が成立して初めて土地の売買契約の効力が発生することになるため、指定された期間内に指定されたハウスメーカーと建築請負契約を締結しなかった場合、売主側は土地の売買契約を解除できることになっています。つまり、買主が売主の指定するハウスメーカーとの建築請負契約を解除したり、他のハウスメーカーと建築請負契約を締結したりした場合は、土地の売買契約は解除されてしまうことになります。
なお、買主とハウスメーカーとの間で建築プランなどが折り合わなかったことなどが理由で建築請負契約が締結されず、土地の売買契約が解約される場合は、原則として手付金や預り金などは売主から買主に返還されます。ただし、「他に欲しい土地が見つかった」などの買主側の自己都合で土地の売買契約をする場合は、原則として手付解除(手付金を放棄することで契約を解除する)の手続きが必要になることに注意が必要です。
02建築条件付き土地のメリットとデメリット
建築条件付き土地は、一般的な住宅取得とは異なるため、メリットやデメリットを確認した上で検討することをお勧めします。
建築条件付き土地のメリット
建築条件付き土地のメリットには以下のようなものがあります。
間取りや仕様をある程度自由に決められることが多い
住宅と土地がセットで売られる建売住宅の場合、すでに建物が完成しているので、原則として間取りや仕様に自分の好みや希望を反映できませんが、建築条件付き土地の場合は、ハウスメーカーと協議しながら建築プランを決めることができるため、希望通りの間取りや仕様を選ぶことができます。ただし、あらかじめハウスメーカーによって基本的な建築プランが決められていて間取りや仕様の変更ができない場合もあり、トラブルに発展したケースも報告されています。土地の売買契約を締結する前にハウスメーカー側に建築の条件をよく確認し、納得した上で契約するようにしましょう。
一般的な土地よりも割安な場合がある
建築条件付き土地は一般的な土地に比べて住宅を建てるにあたっての自由度が低いので、土地価格が割安に設定されていることがあります。
建物に仲介手数料がかからない
建売住宅を購入する場合は建物と土地に仲介手数料がかかります。一方、建築条件付き土地の場合、仲介されるのは土地のみなので、当然、建物分の仲介手数料はかかりません。
建築過程を見ることができる
建売住宅の場合、原則として完成した建物の状態しか確認できませんが、建築条件付き住宅の場合、家を建てる過程を見て工事の品質を確認することができます。
建築条件付き土地のデメリット
一方で、建築条件付きの土地には下記のようなデメリットがあります。
ハウスメーカーが選べない
他に希望するハウスメーカーがあっても、売主の指定するハウスメーカーしか選ぶことができません。また、契約内容によっては、そのハウスメーカーによる「基本プラン」しか選べないケースもあることに注意が必要です。
建築契約の締結までに建築プランを決めなくてはならない
ある程度自由に間取りや仕様を決められるメリットがある一方、短期間でハウスメーカーと打ち合わせを重ねながら建築プランを決めるのは簡単なことではありません。時間切れになって不本意なまま建築契約を結ぶことのないよう、土地の売買契約前に希望条件などをまとめておきましょう。
住宅ローンの実行前に「つなぎ融資」が必要
建築条件付き土地に家を建てる場合、まず売主に土地代を支払い、住宅が完成してからハウスメーカーに建築費を支払う流れになり、土地代と建築費は支払いのタイミングが異なります。
土地を購入する段階では、まだ建物の建築プランが決まっていないため建築代金も確定していないので、建築代金については住宅ローンの融資を受けることができません。つまり、建築条件付き土地に住宅を建てる場合は土地と建物の購入費用をまとめて住宅ローンを組むことはできないのです。したがって、土地代金は、建物の完成後に住宅ローンが実行されるまでの間に必要になる資金を一時的に融資する「つなぎ融資」を利用して支払い、建築代金については、間取りや仕様が決まったのちに住宅ローンを申請し、建物の完成後に建物代金を支払うことになります。
一部ではトラブルも
一般的な土地に家を建てる場合に比べて様々な制約があるため、建築条件付き土地の売買がトラブルに発展することも珍しくありません。よく耳にするのが「広告ではフリープランと謳っていたのに、実際にはハウスメーカーの提示するプランしか選べなかった」、「建築請負契約を急がされ、プランがあやふやなまま契約を結んでしまった」など、ハウスメーカーとの間のトラブルです。建築契約締結前なら土地の売買契約を解除して白紙に戻すことができますが、契約締結後やすでに工事が始まってしまった後では対応が難しくなってしまい、結局泣き寝入りになるというケースもあるようです。トラブルにならないように、契約前に疑問点を解消する、条件をよく理解して納得した上で契約することが大切です。
なお、ハウスメーカーと買主との間のトラブルが起きた際に、買主が土地を仲介した不動産業者に相談するケースがよく見られます。本来、不動産業者が業務として関与するのは土地の売買契約までで、建築請負契約には関与しないのですが、成り行き上、不動産業者がトラブル対応を強いられているケースがあり、不動産業者の間で問題視されていました。
そこで、全宅連は2021年8月に、「宅建業者が建築条件付き土地取引の関連業務(トラブル対応など)を行う際に、仲介手数料以外の費用を買主から受け取れるようにする契約書の雛形を作成する」と発表しました(※1)。雛形は2021年秋に公開される予定です。今後、宅建業者によるサポート体制が整備されていけば、建築条件付き土地を巡るトラブルの抑制に繋がっていくかもしれません。
※1 出典:全国宅地建物取引業協会連合会・「建築条件付き土地売買契約に係る宅地建物取引業法の解釈・運用に関する回答について」P5
03住宅購入予算シミュレーターで無理のない購入予算を確認
実際に住宅の購入を検討するにあたっては、無理のない購入予算を知ることが必要です。「住宅購入予算シミュレーター」で予算の目安を確認してみましょう。

監修:相山華子
ライター、OFFICE-Hai代表、2級ファイナンシャル・プランニング技能士
プロフィール
1997年慶應義塾大学卒業後、山口放送株式会社(NNN系列)に入社し、テレビ報道部記者として各地を取材。99 年、担当したシリーズ「自然の便り」で日本民間放送連盟賞(放送活動部門)受賞。同社退社後、2002 年から拠点を東京に移し、フリーランスのライターとして活動。各種ウェブメディア、企業広報誌などで主にインタビュー記事を担当するほか、外資系企業のための日本語コンテンツ監修も手掛ける。20代で不動産を購入したのを機に、FP(2級ファイナンシャル・プランニング技能士)の資格を取得。金融関係の記事の執筆も多い。
関連キーワード