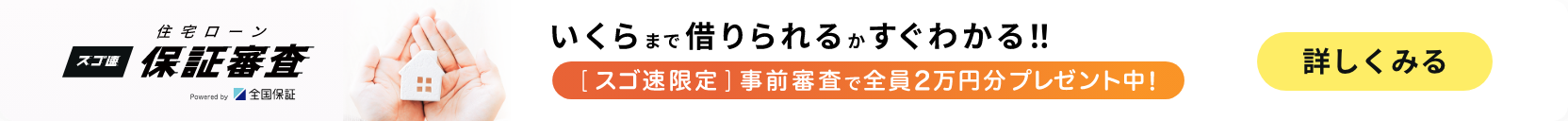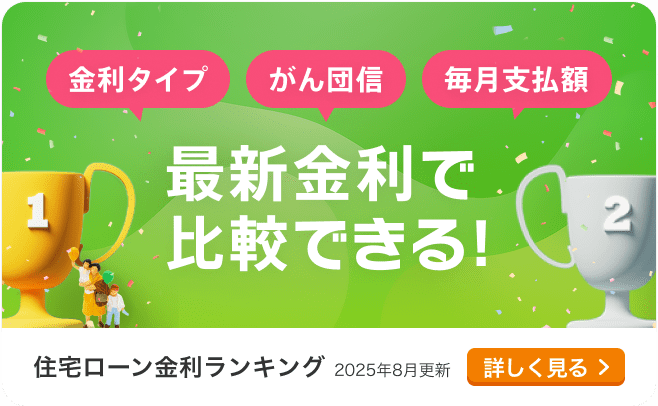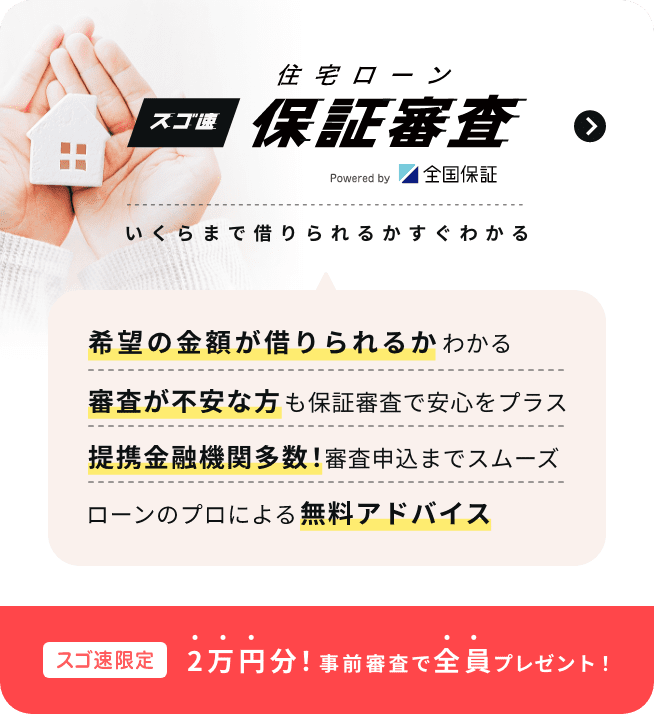ボーナスシーズンに考える、住宅ローンでボーナス併用払いを使うリスク
今年も夏のボーナスシーズンがやってきました。人材の流動化や賃金体系の変化、さらにコロナ禍による業績悪化などの影響で、ボーナスそのものの位置づけが変化しつつある今、住宅ローンの返済に「ボーナス時加算」を利用しても問題ないのでしょうか?今回は最近のボーナス事情と、住宅ローン返済におけるボーナス時加算のメリット、デメリットについて考察します。
012021年夏のボーナスの見通しは?
コロナ禍で迎える2度目の夏のボーナスシーズン。いまだに先行きは不透明で、小売りや飲食、観光など幅広い業界が苦しい状況に置かれていますが、今夏のボーナスの見通しは、どうなっているのでしょうか?
三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社のレポート「2021年夏のボーナスの見通し」によると、2021年夏の民間企業(事業所規模5人以上)のボーナス平均支給額は1人当たり37万4654円と、前年夏のボーナスに比べ2.3%減少するものとみられています。産業別に見ると、製造業は平均47万1797円(前年比-4.1%)、非製造業は35万3722円(同-2.0%)、国家公務員は66万1100円(同-2.8%)と、いずれも前年を割り込む見込みで、昨年冬のボーナスに引き続き、新型コロナウイルスの感染拡大による経済状況の悪化が反映されるものとみられています。
2021年夏のボーナス見通し
| 1人当たり平均支給額 | 前年比 | |
| 民間企業(全体) | 37万4654円 | -2.3% |
| 民間企業(製造業) | 47万1797円 | -4.1% |
| 民間企業(非製造業) | 35万3722円 | -2.0% |
| 国家公務員 | 66万1100円 | -2.8% |
02今どきのボーナス事情
今年の夏はボーナスの減額にとどまらず、支給そのものを取りやめる企業も増えるものとみられ、先ほどの三菱UFJリサーチ&コンサルティングのレポートでは、今夏、ボーナスを支給する事業所で働く労働者の数は、前年より1.9%少ない3988万人となると予想しています。実際、業績悪化を理由に、すでにボーナスの減額や不支給を公表している企業もあります。たとえば、コロナの影響で大きく業績を落とした全日本空輸(ANA)は2021年5月に、同年のボーナスについて夏冬ともに支給しない旨を公表しました。同社では昨年も冬のボーナス支給を見送っていますが、年間ゼロとするのは記録が残る1962年以降初めてのことです。
急にボーナスが減額されたり、支給されなくなってしまうと、ボーナスをあて当てにして買い物をしたり、ローンを組んでいた従業員は大いに困ってしまいます。ボーナスは労働の対価として支払われる賃金ではなく、労働基準法で支払いが義務付けられているものではありません。ボーナスを支給するか否かはもちろん、金額や時期などについても企業側の判断で決めることができます。今回のANAのように業績が落ちたことを理由にボーナス支給を取りやめたとしても、就業規則に「業績によっては、ボーナスを支給しない」旨の記載があれば、原則としては問題ありません。
実際、ボーナスを支給しない企業は珍しくなく、厚生労働省の「毎月勤労統計調査 令和2年夏季賞与の支給状況」(※1)によると、2020年の夏にボーナスを支給した企業は全体の65.3%。2014年夏は68.4%だったので、ボーナスを支給する会社は減少傾向にあるようです。
※1 出典:
厚生労働省「毎月勤労統計調査 令和2年夏季賞与の支給状況」
厚生労働省「毎月勤労統計調査 平成27年9月分結果速報等」
ボーナス支給の企業減少の背景は?
ボーナスを支給する企業が減少傾向にある背景は、コロナによる経済状況の悪化だけではありません。従来の「月給+年2回のボーナス」という給与体系から、ボーナスのない「年俸制」を導入する企業が増えているのです。年俸制とは、勤続年数や年齢にかかわらず、従業員本人の能力や実績をもとに1年分の給与があらかじめ提示される給与制度です。本人の努力や業績が給与に反映されやすいため、実力主義・成果主義が重視される海外では広く普及しており、近年では日本でも、全社員もしくは一部の管理職社員を対象に年俸制を採用する企業が増えています。厚生労働省の「平成26年就労条件総合調査」(※2)によると、年俸制を採用している企業の割合は、従業員数が1000人以上の企業では26.4%、300~999人の企業で21.2%、100~299人の企業では12.1%となっており、規模の大きな企業ほど年俸制を採用しているケースが多くなっています。また、産業別では、年俸制を採用している割合が最も高いのは情報通信業(26.0%)で、次いで学術研究、専門・技術サービス業(24.2%)、金融・保険が20.7%という結果となりました。厚生労働省は年俸制の割合に関してはこの年以降の調査を行っていませんが、さらに増えている可能性があります。
仮に転職をする場合、転職先は年俸制でボーナスがなかったということも十分あり得ることです。
※2 出典:厚生労働省「平成26年就労条件総合調査」第17表
03住宅ローン ボーナス時加算のメリット・デメリット
勤務先でボーナスが支給される人の場合、住宅ローンを組む際に「ボーナス時加算」を利用するケースが珍しくありません。ボーナス時加算とは、住宅ローンの月々の返済額を、年2回のボーナス月のみ加算して返済する方法のことで、「ボーナス払い」や「ボーナス併用払い」と呼ばれることもあります。仮に7月と12月をボーナス月に設定した場合、1年のうち7月と12月だけは「毎月の返済額+ボーナス加算額」を合わせた金額を返済することになります。返済総額のうち、いくらをボーナス時加算分とすることができるのかは金融機関によって異なりますが、一般的には返済総額の40~50%を上限とするところが多いようです。ボーナス支給月に多めに返済することで、月々の返済額を抑える効果が期待できる一方、ボーナス加算には一定のデメリットも指摘されています。あらためてボーナス時加算のメリットとデメリットをまとめて確認しておきましょう。
ボーナス時加算のメリット
ボーナス時加算には以下のようなメリットがあります。
月々の返済額を抑えられる
ボーナス時加算をすることで、毎月返済していく均等払い分を減らすことができるので、ボーナス月以外の月の支払額を抑えることができます。
例えば、以下の条件で住宅ローンをボーナス時加算ありで返済した場合と、加算なしで返済した場合、毎月の返済額がどのくらい違うのか、「スゴい住宅ローン探し」の「住宅ローンシミュレーション」を使って試算してみましょう。ここでは4つのシミュレーターの中から「毎月の返済額シミュレーター」を使います。
試算する条件は下記のように設定しました。
借入希望額:3000万円
返済期間:25年
金利:変動金利0.375/年
試算をすると、以下のような結果となりました。
ボーナス時加算1回10万円×2回/年)ありの場合
月々の返済額:8万7313円
ボーナス時加算なしの場合
月々の返済額:10万4776円
ボーナス時加算ありの場合では、加算なしの場合に比べて、月々の返済額を約1万7000円安く抑えられることがわかります。
ボーナス時加算のデメリット
一方で、ボーナス時加算には以下のようなデメリットがあります。
ボーナスの減額や支給が取りやめになると、返済できないおそれがある
安定して年2回のボーナスが支給されていれば問題ありませんが、勤務先の業績が急激に悪化するなどして、ボーナスが減額されたり支給が取りやめになったりした場合、加算分の返済ができなくなるおそれがあります。
総返済額が増えてしまう
毎月返済する均等払い分は少しずつ元金が減っていくため、支払う利息も少しずつ減っていきます。しかし、ボーナス時返済分は半年に1回しか元金が減らないので、その分、支払う利息が多くなります。
そのため、同じ返済期間で、年間に同じ金額を返済するのであれば、ボーナス時加算ありの場合は、ボーナス時加算なしの場合に比べて、総返済額も増えます。
04ボーナス時加算を選んだ際の注意点
住宅ローンの返済にボーナス時払いを使うか否かは、上に挙げたメリットとデメリットを十分に比較検討した上で決断するようにしましょう。
そして、ボーナス時払いを利用する場合は、矛盾するようですが、「加算分をボーナスで払う」という意識を持たないことが大切です。というのも、先に述べた通り、今後、ボーナスが減額や支給停止になることは決してあり得ない話ではないからです。
また、転職をする場合、新たな勤務先が年俸制でボーナス制度そのものがないケースもありますし、急にリストラをされたり、病気やけがで働けなくなったりする可能性もゼロではありません。仮にボーナスが減額、あるいは支給されなくなっても、滞りなく住宅ローンの返済を続けられるよう、最初にボーナス時加算の金額を大きく設定しすぎないこと、余裕資金を確保しておくことが大切です。もし、今後も現状と同じ程度のボーナスが継続して支給される確信が持てず、他に余裕資金がない場合は、住宅ローンを組む際にボーナス時加算を利用せずに毎月の均等払いを選び、余裕資金ができたタイミングで繰り上げ返済をする方法を選んだ方が無難かもしれません。
なお、万が一、ボーナスが減給もしくは支給停止になり、ボーナス時加算分が支払えなくなった場合は、すぐにローンを借りている金融機関に相談し、ボーナス時加算をやめて毎月均等払いに返済プランを変える手続きをしましょう。プラン返済にあたって審査や手数料が必要になることがありますが、支払いが滞って住宅の差し押さえなどのトラブルに発展する前に、速やかに金融機関に相談をすることが大切です。

監修:相山華子
ライター、OFFICE-Hai代表、2級ファイナンシャル・プランニング技能士
プロフィール
1997年慶應義塾大学卒業後、山口放送株式会社(NNN系列)に入社し、テレビ報道部記者として各地を取材。99 年、担当したシリーズ「自然の便り」で日本民間放送連盟賞(放送活動部門)受賞。同社退社後、2002 年から拠点を東京に移し、フリーランスのライターとして活動。各種ウェブメディア、企業広報誌などで主にインタビュー記事を担当するほか、外資系企業のための日本語コンテンツ監修も手掛ける。20代で不動産を購入したのを機に、FP(2級ファイナンシャル・プランニング技能士)の資格を取得。金融関係の記事の執筆も多い。
関連キーワード