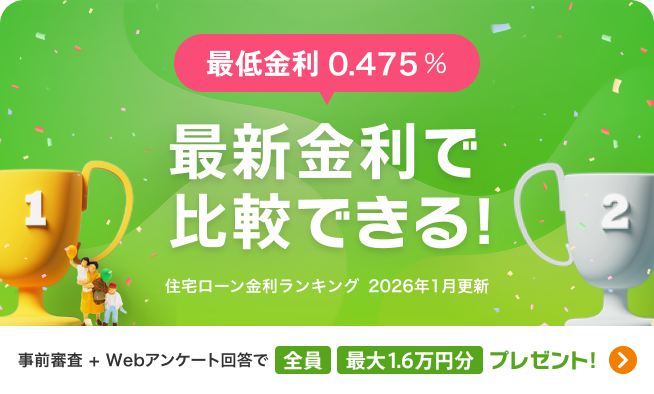家賃が2.5倍、知らぬ間にオーナー交代…賃貸派が見落としがちな住まいのリスクとは
「ある日突然、家賃が2.5倍になったら──」2025年1月、東京都内の賃貸マンションで、そんな信じがたい出来事が起きました。きっかけはマンションのオーナーが外国企業に変わったこと。入居者には、日本語と外国語で書かれた“家賃大幅アップ”の通知が届き、一部の人は転居を余儀なくされました。 賃貸住宅は気軽に住み替えができる一方、オーナーの事情で「急な値上げ」や「退去要請」が起こるリスクもあります。こうした不安から自分や家族の暮らしを守る手段の一つが、「マイホームを購入する」という選択です。 この記事では、今回の家賃急騰の例をもとに、賃貸住宅に潜むリスクと、その対策として「マイホームを購入するという選択肢」について解説します。
- 01ずっと借りられると思っていた――家賃2.5倍の衝撃事例とは
- 突然届いた「家賃2.5倍」の通知
- 気づいたらオーナーが外国企業に
- スーツケースだらけのエレベーター、民泊化で入居者の生活が激変
- 02なぜ起きる?賃貸住宅に潜む「見えないリスク」
- オーナー変更
- 契約更新時の家賃値上げ
- 外国人オーナー物件
- 03借りて住むことは本当に安心?賃貸のメリット・デメリット
- 気軽に住み替えOK!賃貸のメリットは「自由さ」と「初期費用の少なさ」
- ただし賃貸は「ずっとここに住める」という保証はない
- 04「住みたい家」じゃなく「住み続けられる家」を選ぶ時代へ
- 05ずっと安心して住める場所を選ぶために、住宅ローンの無理のない返済額を確認しよう
01ずっと借りられると思っていた――家賃2.5倍の衝撃事例とは
先述した賃貸マンションの「突然の家賃2.5倍」という騒動は、なぜ起きたのでしょうか。まずはその出来事の背景を紹介し、そのあとで「賃貸住宅の見えないリスク」について解説します。
突然届いた「家賃2.5倍」の通知
東京都内の賃貸マンション入居者に、通知が届いたのは2025年1月のことでした。その通知には「2025年8月から家賃を従来の月額7万2500円から月額19万円まで引き上げる」という旨が記載されていました。理由は「公共料金を始めとする諸費用の増加のため」。しかも、文面は日本語と中国語の併記で書かれていたうえ、「1カ月以内に更新しないなら退去を迫る」という威圧的な表現も含まれていたのです。値上げの実施までには6カ月以上の猶予があったものの、経済的な事情から、住み慣れた住まいを離れることになった入居者もいました。
気づいたらオーナーが外国企業に
今回、このような通知が出された背景には、オーナーが変わっていたことが要因として挙げられます。当該物件はすでに中国籍の企業によって買収されていましたが、賃貸契約ではオーナーが変わったときに賃借人へ通知しなくても法律的に問題ないケースが多いです。そのため、入居者が知らない間に契約相手が変わっていることもよくあります。今回の事例でも事前にオーナー変更の通知がなく、入居者がそのことを知らなかったため、戸惑いが広がり、大きな騒動へと発展しました。
スーツケースだらけのエレベーター、民泊化で入居者の生活が激変
入居者に値上げを迫る権利があるとはいえ、いきなり家賃を2.5倍にすると賃借人の反発を招くことはオーナー側も容易に想像できたはずです。にもかかわらず強気な方針を打ち出した背景には、より高い利益を見込める民泊への転用があったと考えられます。
実際、家賃値上げの通知後には、建物内でスーツケースを持つ短期滞在者の姿が頻繁に確認されるようになりました。こうして一部の入居者が退去し、代わりに短期滞在者が増えたことで、入居者の入れ替わりが激しくなり、それまで静かだった住環境も一変したといいます。
02なぜ起きる?賃貸住宅に潜む「見えないリスク」
今回の板橋区の賃貸マンションで起きたような外国人投資家による物件取得は、今や珍しいことではありません。円安の影響で日本の不動産は、外国人投資家から割安に見られ、特に都市部を中心に人気のある物件が狙われています。そこで、ここからは外国人投資家による物件取得によって入居者に影響が及ぶケースについて解説していきます。
オーナー変更
賃貸住宅は複数人が居住する物件ですが、あくまでも不動産の一種なので所有者(オーナー)は自由に売却できます。仮にオーナーが変わっても、原則として法的には通知義務がないため、入居者が知らないうちに所有権が移転していることもあります。入居者側は「気が付いたらオーナーが変わっていた」という事態になっており、急な家賃の値上げに戸惑うこともあります。
契約更新時の家賃値上げ
家賃は契約期間ごとに見直される「契約更新時」であれば、合法的に変更可能です。民法や借地借家法などによって入居者の権利は一定程度守られているものの、家賃の値上げに正当事由があると認められる場合、更新に同意しないと契約終了で退去しなければいけないケースもあります。周辺の相場とかけ離れたあまりに大幅な値上げは不当とされる場合もありますが、「強引な値上げによって退去を促す手法」として、契約更新時に家賃の値上げを悪用する事例も散見されます。
外国人オーナー物件
東京などの都市部を中心として外国人投資家による不動産取得が増加していますが、これは日本の不動産価格が割安だと考えられているからです。日本の物価は上昇傾向ではあるものの、世界ではさらにインフレが進んでいる国もあるうえ、円安による影響で外国人からは相対的に割安に映り、投資対象として注目されています。
特に中国やシンガポール、香港などの資本はマンションやアパートをまとめて購入するケースもあるなど、日本の都市部の不動産は依然として人気です。オーナーが外国人に変わり、より高い収益を求めて「居住用」から「収益用(民泊・短期賃貸)」に物件の用途を変えることで、昔から住んでいた入居者の立場が弱くなるリスクが考えられます。
03借りて住むことは本当に安心?賃貸のメリット・デメリット
ここまで賃貸住宅に住むリスクの1つであるオーナーチェンジについて解説してきました。すべてのオーナーチェンジが入居者にとって悪い方向に進むわけではないものの、そうしたリスクがあることは覚えておきましょう。ここからは、賃貸暮らしに不安を感じた方へ向けて、賃貸に住むメリット・デメリットを整理します。
気軽に住み替えOK!賃貸のメリットは「自由さ」と「初期費用の少なさ」
賃貸住宅に住む最大のメリットは、柔軟性と初期費用の少なさです。入居の際にかかる費用には敷金や礼金、家賃、引っ越し費用などが挙げられますが、多くの場合、数万~数十万円程度で済みます。マイホーム購入のように頭金の用意や住宅ローン審査への対応は不要なため、住まいの選択肢として取り入れやすいでしょう。
初期費用の少なさを活かして結婚・転勤といったライフステージの変化にも対応しやすいうえ、周辺環境の悪化や近隣住人とのトラブルといった解決が難しい問題が起きた場合でも、引っ越すことで回避できるのは、賃貸住宅ならではのメリットです。
ただし賃貸は「ずっとここに住める」という保証はない
賃貸住宅のメリットは、「住みたい場所を気軽に選べる」という点が挙げられます。しかし、仮に理想の物件を見つけても、そこに長く住み続けられるとは限りません。たとえば、今回紹介した事例のように、オーナー側の事情で契約更新を拒否されるケースが考えられます。
賃貸住宅は建て替えや売却、民泊化に代表されるように、オーナーの都合で入居者が退去を余儀なくされることがあります。そのため、「いざというとき、自分の都合に関係なく住まいを失う」というリスクは常に存在します。
特に民泊化のように短期賃貸への転用が進むと、安全性やプライバシー、騒音といった問題で入居者は悩むことになるかもしれません。他にも、高齢になると家賃支払いの懸念からオーナーに契約更新を断られる場合があるなど、不都合がついて回るのがデメリットです。
持ち家と賃貸住宅のメリット・デメリットについてもっと知りたい方は、以下の関連記事で詳しく解説しているので、こちらも参考にしてください。
04「住みたい家」じゃなく「住み続けられる家」を選ぶ時代へ
持ち家と賃貸住宅には双方にメリット・デメリットがあるので、どちらを選んだほうがいいという明確な答えはありません。ただし、覚えておきたいのは、賃貸住宅に住む際に毎月支払う家賃は常に「消費されるだけ」なのに対し、持ち家は購入すれば「住宅が資産として手元に残る」ことです。
将来的に住宅ローンを完済した際には、その後の住居費は固定資産税や修繕費程度に抑えられるので、長期的に考えれば生活費のコストダウンを図れるでしょう。住宅を資産の一部としてとらえることで将来の教育費や老後資金とバランスを取りやすくなり、人生設計も立てやすくなるはずです。
また、不動産所有者ならではのメリットとして、将来的に売却・賃貸運用など物件を資産として自由に活用できる点や、オーナー変更または契約更新のたびに家賃の値上げに怯え無くて良い点も挙げられます。賃貸住宅のように気軽に引っ越しをすることはできませんが、間取りや内装、設備を自分好みに設計したり、リフォームしたりすることはできるので、住環境を自分の思い通りにできるのも魅力です。
持ち家と賃貸住宅のメリットについては以下の関連記事でも紹介しているので、気になる方はチェックしてみてください。
05ずっと安心して住める場所を選ぶために、住宅ローンの無理のない返済額を確認しよう
住宅に求める役割は人それぞれですが、大前提として安心して暮らせる場所でなければ生活が成り立ちません。賃貸住宅には柔軟性や初期費用の少なさといった魅力があるものの、オーナー交代による突然の家賃値上げや民泊転用などの見えにくいリスクが潜んでいるのも事実で、「住み続けたいと思った家を退去しなければならない事態に陥る可能性がある」という現実を知っておきましょう。
住宅選びをするうえで大切なのは、自分や家族にとって「何を優先したいか」を明確にすることです。安心して長い間住み続けられる場所を求めているのであれば、住宅購入を前向きに考えてみることをおすすめします。ただし、住宅を手に入れれば必ず安心して暮らせるというわけではありません。周辺環境や立地条件を視野に入れた住宅選びが大切ですし、無理な資金計画で購入すると将来の返済が家計を圧迫し、せっかく手に入れた安心が不安に変わってしまうリスクもあります。特に現在の住宅ローン金利は上昇傾向なので、「自分が借りられる限度額」だけでなく、「無理なく返済できる金額」を知ることが安心した住宅選びの第一歩になるでしょう。
当サイトでは、金利の違いによって月々の返済額がどれくらい変わるかを比較できる『毎月の返済額シミュレーター』をご用意しています。また、現在の家賃から購入予算を逆算できる『借入可能額シミュレーター』もあり、住宅購入の資金計画に役立ちます。これから住宅選びをする人はぜひ活用してみてください。

監修:新井智美
CFP®/1級ファイナンシャル・プランニング技能士
プロフィール
トータルマネーコンサルタントとして個人向け相談の他、資産運用など上記相談内容にまつわるセミナー講師を行う傍ら、年間100件以上の執筆・監修業務を手掛けている。
関連キーワード