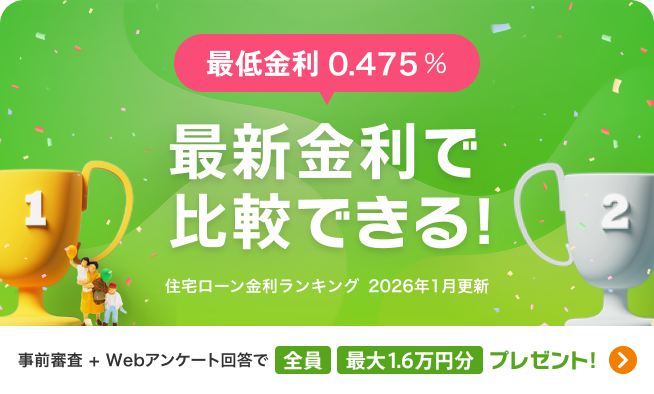約8割が悩む「家の湿気」問題とは?建てる前に知っておきたい土地と間取りのポイント
周囲を海に囲まれている日本は、世界的に見ても降水量が多い国として知られています。このような気候の日本で、住宅を建てるときに気を付けておきたいポイントが「湿気対策」です。実際に住宅メーカーの一条工務店が行った調査によると、約8割の人が夏場の自宅で「湿気による不快感がある」という結果が出ています。 湿気による不快感の原因は、立地や周辺環境だけではありません。間取りや通風といった“住んでみないと気付きにくい設計上の要素”も大きく関係しています。そこで、この記事では湿気で後悔しない家づくりをするために知っておきたい「土地と間取りの落とし穴」について解説します。
01カビ・結露・不快感…湿気トラブルが起こる家の共通点とは?
まずは一条工務店の調査から、湿気によるストレスを感じている人の声を紹介し、その後、それを放置した際に起こり得る深刻なトラブルについて解説します。湿気によるトラブルにはどのようなものがあるか、一緒に確認していきましょう。
住宅メーカーの調査で判明!約8割が“湿気のストレス”を実感
一条工務店が全国の男女1369名を対象に行った「夏の住まいの暑さ・湿気に関する意識調査2025」で、「夏場、自宅内の湿気が気になることはありますか?」という質問をしたところ、「とても気になる(37.1%)」「やや気になる(39.2%)」と答えた人は合計で8割近くに上りました。
その中でも不快感のある場所(複数回答可)として挙げられたのは「寝室(49.6%)」「脱衣所(46.3%)」「浴室(41.9%)」で、リビング(39.8%)や洗面所(37.9%)、キッチン(29.8%)、クローゼット(27.8%)がそれに続く結果となりました。
回答では、湿気がこもりやすく換気しにくい脱衣所や浴室、クローゼットのほか、寝室やリビングなど長時間過ごす場所の湿度を気にする人も多く見られました。帰宅時や就寝時など「一日の中でもっともくつろぎたい時間帯」に不快感が積み重なると、生活の満足度が下がってしまうため、快適な暮らしを続けるためにも不快感のない住宅を選ぶことが大切です。
放置するとどうなる?湿気による意外なトラブル
住宅内の湿気が長期間高い状態が続くと、暮らす人の不快感だけでなく、建物自体にもダメージを及ぼす恐れがあります。たとえば、窓や壁に水滴がつく結露をそのまま放置すると、やがて構造部分にまで湿気が浸透して断熱材や木材の腐食、金属の錆びを引き起こし、住宅の寿命を縮めてしまうことがあります。
また、見た目には問題がない住宅でも、天井裏や家具の背面など、目に見えない場所でカビが発生しているケースも少なくありません。カビが発生すると部屋の見た目が悪くなるだけでなく、アレルギーや喘息など健康被害の原因にもなり得ます。特に子どもや高齢者のいるご家庭では、注意が必要です。
こうした問題が起きた住宅では、対策として室内の湿度を自動的に調整してくれる吸放湿壁紙への張り替えや、湿気を調整してくれる断熱材への入れ替えといった方法が挙げられます。ダメージの程度が深刻な場合は、大掛かりなリフォームが必要になる場合もあり、結果として修繕コストが増加し、想定外の出費につながるかもしれません。
02家を建てる前に!湿気がたまりやすい土地の特徴とその対策
湿気が多い住宅は、住む人に不快感を与えるだけでなく、建物自体にも大きな悪影響を及ぼす場合があります。せっかく建てる住宅で安心かつ快適に暮らすためにも、これから紹介する湿気がたまりやすい土地の特徴やその対策について知っておきましょう。
湿気がたまりやすい土地の特徴
湿気がたまりやすい場所として注意したいのは、「周囲に山や森がある」「川や池、田んぼが近い」といった土地です。それぞれ、前者は風が通りにくくて日照も弱いため、ジメジメとして湿気がこもりやすいこと、後者は地盤が緩く水分を含んでいる場合が多いうえ、地中から湿気が上がってくる恐れがあるためです。
また、低地や谷地のような地形にある土地も注意しましょう。こうした土地は、雨水の通り道になっていることが多く、梅雨の時期など降水量の多い季節では常に湿った状態になりがちです。特に排水が悪い場所は湿気がこもりやすいうえ、山際の土地では土砂崩れの心配もあることから、自治体のハザードマップをよく確認してから住宅の建設を検討することをおすすめします。
そのほかでは、住宅密集地や細い通路の奥に敷地がある旗竿地も湿気がこもりやすいといわれています。どちらも周囲に山や森がある環境と同じで、「隣家との距離が近くて風が通り抜けにくく、採光も確保しにくい」といったことがその理由です。
土地の見えないリスクを見抜く方法
湿気がこもりやすい土地にはいくつかの特徴がありますが、場所によって条件は全く異なるので、住宅を建てる際は可能な限り自分の目で現地を確認しておきましょう。その際は複数の時間帯でチェックすることがポイントです。なぜなら、昼間は気温が上がるので湿度が下がりやすい一方、夜間になると気温が下がって相対的に湿度が上がりやすいからです。
また、自治体のハザードマップや過去の浸水履歴からも、ある程度湿気がこもりやすい土地かどうかを判断できる場合があるので、調べてみるのもよいでしょう。たとえば、浸水しやすい地域は土壌が粘土状であったり、湿地の跡地や埋め立て地であったりすることが多いです。そのため、水はけが悪く、雨がやんでも地中の水分が抜けにくくて、床下や建物周辺に湿気がたまりやすくなることが考えられます。
自分で調べても分からない場合は、地元の不動産会社や住民に聞いてみるのも1つの方法です。地元情報に詳しい人の話からは、ネットでは調べられない「土地のクセ」や「湿気に関する体感情報」を教えてもらえることがあるので、知り合いなどがいる場合は積極的に聞いてみることをおすすめします。
もっと詳しい客観的なデータを知りたい場合には、周囲の建物や地形との関係を図面や模型、3Dソフトなどを活用して施工会社にシミュレーションしてもらう方法もあります。すべての施工会社が対応しているわけではありませんが、建物の配置や窓の位置によって風の入り方や抜け方を確認してもらうだけで改善点が見つかる場合もあるので、とりあえず問い合わせてみるとよいでしょう。なお、日照時間は季節によって大きく変わるので、シミュレーションの際は、特定の月だけでなく、1年を通した日照時間を確認してもらうのがおすすめです。
03湿気がこもりやすい家の間取り・構造の特徴とは
湿気がこもりにくい住宅を建てるには、土地の状況や周囲の環境に気を付けることが重要ですが、それと同じぐらい家の間取りや構造にこだわることも大切です。そこで、ここからは湿気がこもりやすい間取り・構造の特徴を2つのポイントから解説します。
床下・基礎の湿気対策が甘い
水分を多く含んだ空気は地面付近にたまりやすいので、床下や基礎の湿気対策は重要です。床下の通風や防湿対策が不十分だと建物全体の湿度が上がってしまい、いくら換気をしてもなかなか不快感が消えない要因となります。
一般的に、建物の底面全体に鉄筋コンクリートを施工する「ベタ基礎」のほうが、柱や壁の下にのみコンクリートを施工する「布基礎」に比べて、地面からの湿気を遮断しやすいといわれています。施工コストはベタ基礎のほうが高くなりがちではあるものの、湿気に不安のある人はベタ基礎を検討してみるとよいでしょう。
ただし、施工精度も重要で、床下の防湿シートや防湿コンクリートがきちんと施工されていない場合、いくらベタ基礎でも地中からの水蒸気を十分に防げず、湿気が床材に影響を与え建物の劣化を早めることがあります。また、床下の換気口が少なかったり、風が抜けない設計だったりすると、湿気が床下にたまってカビやシロアリの発生原因となることもあるので気を付けましょう。
調湿・断熱が不十分
主に冬場に発生する結露は室内の湿気を悪化させる要因の一つで、これは住宅の断熱性能不足が原因で起こることが多いといわれています。特に壁や天井・床の断熱材の種類や入れ方が適切でない場合、冬場に結露が発生しやすくなって木材の腐食や金属部品の錆びの原因となるためです。そのため、周囲の環境などから湿気対策に不安のある土地に住宅を建てる場合、内装材に珪藻土や漆喰、エコカラットといった調湿性のある素材を選ぶことをおすすめします。
また、外壁と内壁の間に空気の逃げ道となる「通気層がない構造」では、壁内結露が起きやすく、柱や断熱材の劣化につながることがあるため注意が必要です。なお、断熱性能を高めると湿気対策になるだけでなく、エアコンの利用頻度が下がり、光熱費削減にも効果があります。
光熱費削減と快適な暮らしを両立できる住宅に興味がある人は、以下の関連記事も参考にしてください。
04湿気に強い家にするための予算づくりのコツ
ここまで紹介してきたように、湿気に強い家を建てるには土地の特徴を知ったうえで、間取り・構造に気を付けることがポイントです。しかし、すべての条件を満たそうとすると、必要な費用が膨らみ、予算オーバーになるかもしれません。そこで、最後に湿気に強い家にするための予算づくりのコツについて紹介します。
優先順位を決めて“必要な対策”に絞る
湿気に強い家にするには調湿性能の高い内装材を用いたり、通風をよくするために窓を多く設置したりといった方法があります。しかし、それらの対策をするにはコストがかかるので、完璧にするのは予算の都合上、難しい場合もあるでしょう。そのようなときは、まずは湿気がたまりやすい場所を優先的に対策しましょう。
たとえば、「寝室や脱衣所、収納など空気がこもりやすい場所に重点的に調湿建材を使う」「リビングの設計では窓の向きや大きさに注意して採光と通風を確保する」といった方法です。また、日当たりが悪いことが多く、冬場の結露に悩まされがちな北側の部屋は、断熱や換気を特に強化するとよいでしょう。予算にメリハリをつけることで、湿気対策をしても予算内に収まる可能性が高くなるはずです。
“目に見えにくい部分”にこそ予算をあてる
住宅設計を考えるときは、ついデザイン性などの「見た目」を重視しがちです。しかし、湿気対策のような新築時には見えない部分をおろそかにすると、住み始めてからの快適性や住宅寿命、住む人の健康に問題が生じ、後悔するかもしれません。そのため、予算を考えるときはデザインや設備のグレードアップよりも建物の構造や性能に関わる部分を優先しましょう。
湿気が原因で発生するカビや結露、木材の腐食などは住宅寿命を縮め、将来的なリフォーム費用の負担増につながる可能性があります。湿気対策の適正な予算は土地の立地や周辺環境によって変わりますが、目安としては30万~100万円程度が想定されるため、施工会社とよく相談してみてください。
05「湿気」は家づくりの見落としポイント!まずは家の予算から考えよう
湿気は目に見えない問題であるため、家づくりの際は対策の予算配分が後回しになりがちです。しかし、湿気対策は土地選びや間取り設計、建材選びなど家づくり全体に関わるテーマであるだけでなく、後から対策の必要性に気付いてもできることには限りがあります。そのため、できるだけ最初から住宅設計に組み込んでおくことが大切です。
とはいえ、「どこにどれくらい費用をかけるか」は全体の予算に左右される部分もあるので、まずは世帯年収から無理のない返済プランを把握することから始めるとよいでしょう。当サイト内には住宅予算を考えるのに適した各種シミュレーターがあり、その中でも住宅ローンシミュレーターを使えば毎月の返済額や借入可能額をすぐにチェックできます。湿気対策も含めて後悔のない家づくりをするために、ぜひ活用してみてください。

監修:新井智美
CFP®/1級ファイナンシャル・プランニング技能士
プロフィール
トータルマネーコンサルタントとして個人向け相談の他、資産運用など上記相談内容にまつわるセミナー講師を行う傍ら、年間100件以上の執筆・監修業務を手掛けている。
関連キーワード