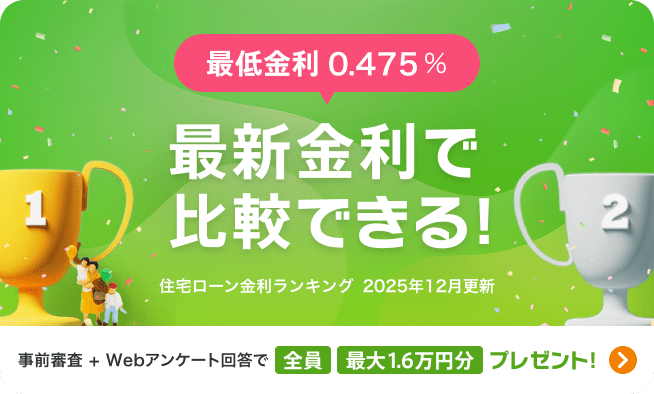なぜ今、新築タワマンが減っているのか?供給減少&価格高騰の背景と賢い買い方
近年、一定の需要があるにもかかわらず、新築タワーマンションの供給が大幅に減少しています。かつては、東京の都心部や湾岸エリアを中心に次々と開発されていたタワーマンションですが、2025年現在では供給が限られ、価格も上昇を続けています。 この背景には、さまざまな要因があり、結果的に新築タワーマンションの価格は、過去20年間で約2倍にまで上昇しているといいます。 この記事では、新築タワーマンションの最新市場動向と近年の価格推移、今後の市場予測や賢い買い方のポイントまで幅広く解説します。
- 01新築タワーマンションの供給ピークは「2000年代中盤」と「2010年代中盤」
- 2020年代、新築タワーマンションの供給数が減少傾向に
- 02新築タワーマンションの供給減少の主な原因
- 建築コストの高騰
- 人手不足と人件費の増加
- 都市部の開発可能な土地の減少
- 03今後のタワーマンション市場はどうなる?
- 新築タワーマンションの供給は今後も限定的
- 中古市場が活況に!築浅物件の人気が上昇
- 04タワーマンション「賢い買い方のポイント」チェックリスト
- 立地を重視する
- 管理体制がしっかりした物件を選ぶ
- 長期的な資産価値と維持コストを考慮する
- 05タワーマンションは資産価値の維持や将来的な売却を見据えた物件選びを!
01新築タワーマンションの供給ピークは「2000年代中盤」と「2010年代中盤」
不動産の市場調査やデータ分析を手がけるマーキュリーの調べによると、新築タワーマンションの供給は2000年代中盤(2004〜2007年)と、2010年代中盤(2013〜2015年)にピークを迎えました。
マーキュリーによれば、2000年代中盤の第1次ピークは港区や品川区などの都心部、江東区を中心とする湾岸エリアで再開発が活性化したとのことです。都心回帰の流れにより、利便性の高いエリアで大規模タワーマンションの開発が進んだことが、供給数の増加に結びついたと考えられます。
第2次ピークは、2011年の東日本大震災後、高い利便性と耐震性を兼ね備える、都心部のタワーマンションに対する需要が高まったことが主な要因です。2013年には、全国で1万戸を超える新築タワーマンションが供給されています。2015年には、東京23区の平均販売価格の上昇トレンドが明確化しており、この時期から投資目的での購入も増えていることがうかがえます。
2020年代、新築タワーマンションの供給数が減少傾向に
主な年ごとに、超高層マンション(20階建て以上)の竣工・計画戸数の推移をまとめてみましょう。
主な年ごとの超高層マンション竣工・計画戸数(首都圏・近畿圏)
| 首都圏 | 近畿圏 | |
|---|---|---|
| 2007年 | 2万3868戸 | 5547戸 |
| 2015年 | 1万3624戸 | 3015戸 |
| 2019年 | 8547戸 | 5239戸 |
| 2024年 | 8699戸 | 3912戸 |
ちなみに、東京カンテイによれば、全国で2024年に竣工したタワーマンションの戸数は1万130戸でした。2023年は1万5330戸だったことから、全国的にも減少傾向にあることがわかります。
ただ、近年は地方中核都市の駅前などでは、大規模タワーマンションや複合再開発プロジェクトなどが盛んに行われています。2025年には、これまでタワーマンションの供給がなかった宮崎県でも1棟竣工予定です。
02新築タワーマンションの供給減少の主な原因
2020年代に入ってタワーマンションの供給が減少している背景には、建築コストの高騰・労働力不足・土地不足の3点があります。それぞれの原因について詳しく解説します。
建築コストの高騰
建材費の上昇に加え、昨今の歴史的な円安の影響で、輸入資材の価格が高騰しています。2018年以降、建築コストは過去5年間で約30%も上昇しており、とりわけ、高層建築での価格上昇が顕著になっています。
マーキュリー調べでは、タワーマンション平均価格は東京23区・大阪市ともに、過去20年間で2倍以上に高騰している状況です。
タワーマンションの平均価格
| 東京23区 | 大阪市 | |
|---|---|---|
| 2004年 | 5300万円 | 3864万円 |
| 2023年 | 1億1764万円 (約2.2倍) | 7863万円 (約2倍) |
2014年以降は、建築コストの上昇に加え、供給エリアが都心部の好立地に限定されてきたこともあり、価格上昇が顕著になっています。東京23区の平均価格は1億円を超え、特に都心部や湾岸部の高額物件は、もはや一般の購入層には手の届かない価格帯です。
建築コストの高騰は、地方のタワーマンション開発にも大きな影響を及ぼしています。例えば、岐阜市のJR岐阜駅北側で計画されていた34階建てのツインタワーマンションは、コストの大幅上昇で採算が合わなくなったことから、片方が34階建てから20数階建てへと計画変更されました。
人手不足と人件費の増加
建設業界では職人不足も深刻化しています。タワーマンションなどの高層建築には、高度な技術が求められるため、労働力不足による人件費高騰の影響は甚大です。職人を確保できずに工期を延長せざるを得なかった分、かかったコストを販売価格に上乗せするケースも少なくありません。
首都圏の大規模物件における工期は10年で3割も延びたというデータもあり、東京23区や大阪市の大規模再開発プロジェクトでは、コスト負担の増大が課題となっています。実際、人件費や建築費の増加が原因で、2020年以降に計画されていた再開発事業が延期・中止となったケースもあるほどです。
都市部の開発可能な土地の減少
都市部における開発可能な土地が減少していることも、タワーマンションの供給減少に拍車をかけています。既存のオフィスビルや商業施設を再開発する動きはあるものの、土地取得コストが高騰しているため、収益性の高いホテルなどに競り負けてしまうのです。
そこでデベロッパーが注力しているのが、コンパクトな高級マンションや賃貸マンションです。分譲マンションだと採算性の低い土地でも、このような物件なら事業として成立する可能性が高いため、都心部の好立地で供給が増えています。
03今後のタワーマンション市場はどうなる?
タワーマンション市場の近年の推移を見てきましたが、2025年以降も「供給減少」「価格上昇」「建築コスト高騰」の3つの要因により、一般の購買層にとっては購入が厳しい状況が続くと考えられます。今後の見通しを見ていきましょう。
新築タワーマンションの供給は今後も限定的
2025年以降も建築コストの下落要因は乏しく、コストの高止まりによって、タワーマンションの新規供給は抑制される見込みです。特に、駅近の大規模用地は限定的なため、都心部の利便性の高い新築タワーマンションは、一層希少な存在になるでしょう。
こうしたなか、東京では品川・渋谷・池袋・虎ノ門・日本橋といった、都心部や主要駅の近くの一等地において、新築タワーマンションの開発が継続中です。大阪でも、梅田・中之島・難波といった一等地での大規模再開発が進んでおり、一部でタワーマンションの供給が行われます。
また、首都圏の郊外や地方でもタワーマンションの建設が進んでいます。とりわけ注目を集めているのが、千葉県船橋市のJR船橋駅で建設中の51階建てタワーマンションです。上層階は3億円超と高額ですが、低層の小さめの物件は1億円を切るものもあり、値ごろ感があります。
中古市場が活況に!築浅物件の人気が上昇
上で述べた新築の供給数減少と価格高騰により、実需層が中古タワーマンション市場へ流れ始めています。
特に人気なのが、築10年以内の築浅中古タワーマンションです。2013〜2015年は第2次ピークにあたり、大量にタワーマンションが供給された時期のため、中古物件も多く出回っています。築10年以内であれば、設備や機能の充実した物件を新築よりも安く購入できるので、コストパフォーマンスが良好です。
例えば、中央区勝どきのタワーマンションは、築9年で平均価格9400万円あまりと、1億円を切っています。専有面積や階数によるものの、4000万円ほどで購入できる物件もあり、新築に比べると価格差は歴然です。
さらに築20年ほどになると、タワーマンションでも3000万円を切る物件が散見されるようになり、実需層でも十分手が届く価格帯といえるでしょう。
ただ、築20年になると、設備の劣化が目立つようになります。そのため、購入と同時にリフォームも考えているなら、リフォーム費用も考慮しておくとともに、ローンを組む際にリフォーム費用も含めて借りられるのかも確認しておきましょう。
中古マンションは、実際の住環境や管理状況を確認してから購入できるというメリットもあることから、今後も人気が高まっていくと予想されます。
04タワーマンション「賢い買い方のポイント」チェックリスト
タワーマンションの供給が限られている今、将来的な売却も見据えて、資産価値の下がりにくい物件を選ぶことが大切です。資産価値は「立地」「管理体制」「築年数」などの要素によって左右されます。次に紹介する3つのポイントを押さえ、タワーマンションを賢く買いましょう。
立地を重視する
タワーマンションの資産価値に最も影響を与えるのが「どこに建っているか」です。資産価値の下がりにくい物件を選ぶなら、まずは立地を重視しましょう。具体的には、以下の点に注目して選ぶのがおすすめです。
- 最寄り駅から徒歩5分以内
- 主要ターミナル駅にアクセスしやすい
- 周辺エリアで再開発が進んでいる
- 人気の学区や住環境の良いエリアにある
- 地盤が強いエリアにあり、地震があっても揺れにくい
管理体制がしっかりした物件を選ぶ
「マンションは管理を買え」といわれるほど、管理体制は物件選びの大切なポイントです。一般的に、大手管理会社が管理しているマンションは、維持管理のレベルが高いとされます。
管理費や修繕積立金は安いほど、月々の負担を減らせますが、安すぎると将来の大規模修繕時に追加徴収など大きな負担が発生するリスクもあります。大規模修繕計画が適切に計画されているかをチェックするとともに、管理費や修繕積立金が適正な設定になっているか国土交通省のガイドラインを参考にしながら確認しましょう。管理体制に関してのチェックポイントは次のとおりです。
- 管理費・修繕積立金の値上がり履歴
- 管理組合の議事録
- 修繕積立金の不足リスクの有無
- 共用施設の維持コストの高低
- 管理組合の稼働状況
長期的な資産価値と維持コストを考慮する
築年数が古くなるほど購入価格を抑えられる反面、古くなると売却が難しくなり、維持コストも多くかかります。長期的な資産価値や維持コストも考慮したうえで、最適な築年数の物件を選びましょう。
築5〜10年の築浅物件は、新築よりも価格の下落幅が小さいため、売却価格が極端に下がりにくい点が特徴です。リフォームの必要が少ないため、売却しやすいこともあり、人気があります。それだけに中古物件のなかでは価格が高めです。
2回目の大規模修繕が控える築15年以上の物件は、過去の修繕履歴などを確認する必要があります。修繕が適切に行われているかどうかが資産価値に大きく影響するほか、老朽化や管理の不備によって管理費や修繕積立金が大幅に上がる恐れがあるからです。
築20年以上ともなると、徐々に売却が難しくなってきます。築30年、40年となれば、住宅ローン控除の対象外となるケースもあり、買い手がつきにくくなるでしょう。近い将来、建て替え問題や、老朽化による修繕積立金の負担増大なども懸念されるため、購入には慎重な検討が求められます。
05タワーマンションは資産価値の維持や将来的な売却を見据えた物件選びを!
新築タワーマンションの価格高騰により、中古タワーマンション市場が活況を呈しています。中古は新築に比べてリーズナブルに購入可能ですが、築年数が経過すると、維持管理のコストが増えます。
タワーマンションの購入を検討する際は、ランニングコストも考慮し、無理のない資金計画を立てるよう心がけましょう。まずは、自分の年収でいくら借り入れられるのか、毎月の返済はどれくらいになるのか、当サイトの住宅ローンシミュレーターで試算するところから、検討を始めてはいかがでしょうか。
-
住宅購入予算シミュレーター
ライフイベントも加味し、住宅ローンの予算をトータルに計算できる -
毎月の返済額シミュレーター
検討している金融機関の金利と、金利ランキングの一番安い金利との比較もできる -
借入可能額シミュレーター
今払っている家賃から住宅ローンの予算が立てられる
目的に合わせて、最適な住宅ローンシミュレーターを活用しましょう。

監修:新井智美
CFP®/1級ファイナンシャル・プランニング技能士
プロフィール
トータルマネーコンサルタントとして個人向け相談の他、資産運用など上記相談内容にまつわるセミナー講師を行う傍ら、年間100件以上の執筆・監修業務を手掛けている。
関連キーワード