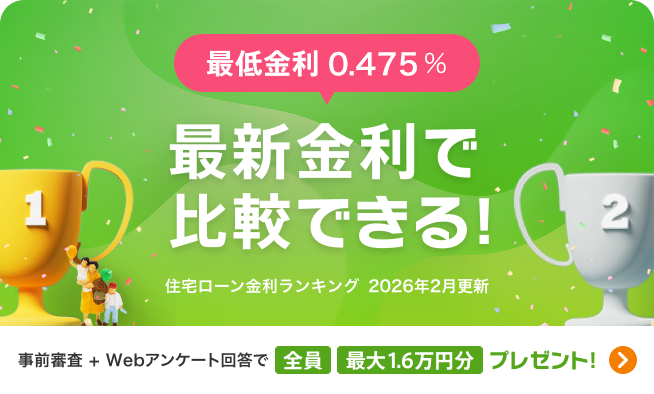マンションも「エネルギーゼロ」の時代へ ZEH-Mの魅力と注意点を解説
近年、環境問題への意識の高まりや光熱費の上昇を背景に、省エネ住宅への関心が急速に高まっています。そんな中、家庭での消費エネルギーを実質ゼロにするZEH(ゼロエネルギーハウス)の集合住宅版である「ゼロエネルギーマンション(ZEH-M)」が注目されています。今回は、マイホーム購入を検討する方に向けて、ZEH-Mの定義やメリット・デメリットを分かりやすく解説します。
01ZEH-M(ゼロエネルギーマンション)とは?
ZEHとは、高断熱・高気密な住宅に省エネ設備や再生可能エネルギー(太陽光発電など)を導入し、エネルギー消費を実質ゼロにすることを目指した住宅です。これまで戸建てが主流でしたが、近年では集合住宅にも導入が進み、マンション版のZEHとして「ZEH-M」が登場しました。
ZEH-Mは、住戸単位ではなく、建物全体を対象として、省エネ・創エネ技術を組み合わせ、消費エネルギー量の実質ゼロを目指します。これにより、各住戸だけでなく廊下やエントランスなどの共用部分も含めたマンション全体の省エネ性能が向上します。
ZEH-Mの種類と分類
ZEH-Mは、省エネ率や再生可能エネルギーの導入状況に応じて、以下の4つに分類されます。
| ZEH-M | ・再生可能エネルギーを含めて一次エネルギー消費量を100%以上削減 ・主に低層マンション(3階建て以下)が対象 |
|---|---|
| Nearly ZEH-M | ・再生可能エネルギーを含めて75%以上100%未満の削減 ・主に低層マンション(3階建て以下)が対象 |
| ZEH-M Ready | ・再生可能エネルギーを含めて50%以上75%未満の削減 ・主に4~5階建てのマンションが対象 |
| ZEH-M Oriented | ・省エネのみで20%以上の削減(再生可能エネルギーを導入する必要はない) ・主に6階建て以上のマンションが対象 |
高い断熱性能や省エネ技術を備えたうえで、再生可能エネルギーの導入割合が高いほど上位ランクのZEH-Mになります。
ZEH-Mで「エネルギーゼロ」を実現する仕組み
ZEH-Mでは、3つのポイントを組み合わせることでエネルギー消費量の実質ゼロを目指します。
1.高断熱・高気密性能
建物全体の断熱性を向上させ、冷暖房の効率を高めることでエネルギー消費を抑えます。
- 高性能断熱材を使用した外壁・屋根・床
- Low-Eガラスや二重・三重ガラス窓の採用
- 気密性を高める施工で外気の侵入を防止
2.省エネ設備の導入
最新の省エネ設備を導入することで、消費エネルギーを削減します。
- エコキュートや高効率エアコンなどの省エネ家電
- 共用部のLED照明・高効率エレベーター
- HEMS(ホームエネルギーマネジメントシステム)によるエネルギー使用の「見える化」
3.創エネ設備の活用
創エネ(創エネルギー)とは、エネルギーを新たに生み出すことを指します。具体的には、太陽光発電、風力発電、地熱発電などの再生可能エネルギーを活用して電力を生み出すことです。再生可能エネルギーを活用し、エネルギーを自給自足できる仕組みを構築します。
- 屋上や外壁に太陽光パネルを設置
- 蓄電池を導入し、発電した電力を夜間や停電時に活用
- V2H(Vehicle to Home)でEV車のバッテリーを非常用電源として利用
ZEH(ゼロエネルギーハウス)との違い
戸建てを対象にしたZEHと集合住宅を対象にしたZEH-Mは、どちらもエネルギー消費量実質ゼロを目指す点では変わりませんが、エネルギー管理やコスト負担などで若干の違いがあります。そこで、その違いを分かりやすく表にまとめてみたので、参考にしてください。
| ZEH(戸建て) | ZEH-M(マンション) | |
|---|---|---|
| エネルギー管理 | 自宅単位で管理・運用 | 建物全体+住戸ごとに管理 |
| 発電・蓄電 | 自宅の屋根に太陽光発電・蓄電池を設置 | 建物全体の屋上や共用部に設置 |
| コスト負担 | 施主が自己負担(補助金あり) | 住民全体で分担(コスト負担軽減) |
| 災害時の電力確保 | 蓄電池・EV活用で自宅の電力を確保 | 共有の電力供給が可能 |
02ZEH-Mのメリットとデメリット
ZEH-Mは省エネで地球環境に優しい住宅として注目を集めていますが、たくさんのメリットがある一方でデメリットもいくつかあります。ここからはZEH-Mのメリットとデメリットの双方を紹介していくので、ZEH-Mに興味を持った方は一緒にチェックしていきましょう。
ZEH-Mのメリット
1.光熱費の削減と快適な住環境の実現
ZEH-Mの最大のメリットは、光熱費の削減と快適な住環境です。ZEH-Mは高断熱・高気密設計が求められるため、外気の影響を受けにくく、室内の温度が安定しやすくなります。その結果、冷暖房の使用頻度が減り、光熱費の節約につながります。
また、高気密設計により結露の発生を防ぎやすいのも特徴です。冬場の室内と外気の温度差が原因で発生する結露が抑えられ、梅雨や夏場の湿気の侵入も防ぎやすくなります。湿度管理が容易になることで、カビやダニの発生を抑え、健康的な住環境を維持できるほか、建物の劣化を防ぐ効果も期待できます。
2.災害時の安心感
ZEH-Mの多くは、太陽光発電と蓄電池を備えているため、停電時でも一定の電力を確保できるという安心感があります。特に、共用部の電力供給が可能な設計であれば、災害時にエレベーターや共用照明を維持できるため、マンション全体の安全性が向上します。
3.資産価値の向上
ZEH-Mのような省エネ性能の高いマンションは、不動産市場でも評価が高く、将来的に売却するときに有利になりやすいといわれています。加えて、CO2排出量削減に貢献できる環境配慮型住宅として、今後の住宅市場においてさらなる価値の向上が期待されています。
ZEH-Mのデメリット
1.初期コストが高い
ZEH-Mは、高断熱・高気密仕様や太陽光発電システムなどの導入が必須となるため、一般的なマンションより建築コストが高くなる傾向があります。しかし、ZEH-Mの普及を促進するために、国や自治体が補助金制度を設けているケースがあるため、上手に活用すればコスト負担を軽減できるでしょう。
2.すべてのマンションがZEH-Mに対応しているわけではない
現時点では、新築マンションを中心にZEH-Mが導入されており、すべてのマンションで採用されているわけではありません。また、既存マンションをZEH-Mに改修することも可能ですが、コストや工期の面で現実的ではないケースが多いため、ZEH-Mを希望する場合は新築物件から探す方法が一般的な選択肢となります。
3.管理組合の理解と協力が不可欠
ZEH-Mでは、共用部の電力管理や設備維持が求められるため、管理組合による合意形成が必要不可欠です。もし管理組合での合意が得られなければ、予算が確保できず、適切な設備運用が難しくなる可能性があります。
また、発電した電力の使い方(共用部のみに使用するか、住戸にも配分するか)をめぐって意見が分かれることもあり、管理組合の運営が複雑になるケースも考えられます。さらに、太陽光発電システムや蓄電池、高断熱仕様の維持管理にはコストがかかるため、一般のマンションと比べて管理費が高くなる可能性があることも認識しておくべきポイントです。
そのため、ZEH-Mを選ぶ際には、管理組合の運営方針や設備管理の体制、管理費の見通しについても事前に確認しましょう。
03ZEH-Mの普及拡大も!
ZEH-Mは、地球温暖化防止に貢献するだけでなく、光熱費削減による家計負担の軽減という実用的なメリットも持つため、近年、消費者の関心が高まりつつあります。その影響を受け、マンション市場におけるZEH-Mの割合も増加しています。
デベロッパーの資料によると、2023年度には新築集合住宅2万3854棟のうち、半数を超える1万3766棟がZEH-Mシリーズの実績または計画物件となっています。特に大きな伸びを示したのが3階建て以下の低層ZEH-Mシリーズで、2022年度の7120棟から2023年度には約1.75倍の1万2509棟に増加しました。
集合住宅におけるZEH化の流れは、今後も加速すると予測されます。例えば、代表的な事例として株式会社大京と株式会社穴吹工務店が手掛ける「ザ・ライオンズ世田谷八幡山」(2025年9月竣工予定)があります。
この物件は、国が定めるZEH-Mの4区分のうち最高ランクである「ZEH-M」および全住戸「ZEH」の基準を満たす国内初の分譲マンションです。2025年2月頃から販売が予定されており、販売価格は未定ながら、大きな注目を集めています。
ZEH-Mの普及が進む一方で、以下のような課題も指摘されています。
- 低層マンションでNearly ZEH-M以上の水準を満たす物件がまだ少ない
- 中層以上の建物規模(4階建て以上)でのZEH-M導入割合が低い
しかし、消費者の関心の高まりを背景に、今後はより多くのZEH-M物件が登場することが期待されており、さらに普及が拡大する可能性が高いでしょう。
04ZEH-Mで賢く快適な暮らしを実現しよう!
今回紹介したZEH-Mは、高断熱・高気密設計と省エネ設備の導入に加え、太陽光発電などの創エネ技術を活用し、エネルギー消費実質ゼロを目指す次世代型マンションです。光熱費の削減や快適な住環境、環境負荷の低減など、多くのメリットがあるため、魅力を感じた方も多いのではないでしょうか。
ZEH-Mを検討する際は、管理組合の合意形成や初期コストの増加といった課題も考慮する必要があります。導入コストや運用方針について事前に情報収集を進め、納得のいく住まい選びをしましょう。
特に、初期コストの増加は住宅ローンの予算や返済計画に影響を及ぼすため、事前にしっかりとしたシミュレーションを行うことが大切です。当サイトでは、以下の便利なツールを提供しています。
- 住宅購入予算シミュレーター:年齢や年収、家族構成を入力するだけで、無理のない住宅予算を算出
- 借入可能額シミュレーター:現在の家賃から、適正な借入額を簡単に逆算
ZEH-Mの魅力を最大限に活かし、エコで快適な住まいを実現するために、ぜひこれらのツールを活用してみてください!

監修:新井智美
CFP®/1級ファイナンシャル・プランニング技能士
プロフィール
トータルマネーコンサルタントとして個人向け相談の他、資産運用など上記相談内容にまつわるセミナー講師を行う傍ら、年間100件以上の執筆・監修業務を手掛けている。
関連キーワード