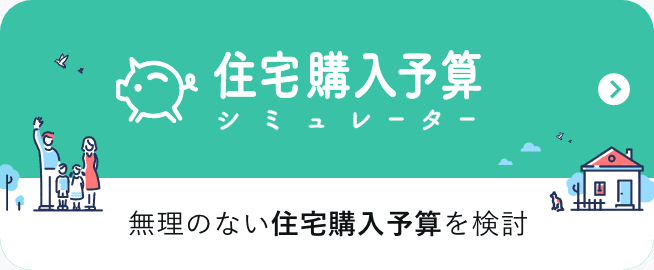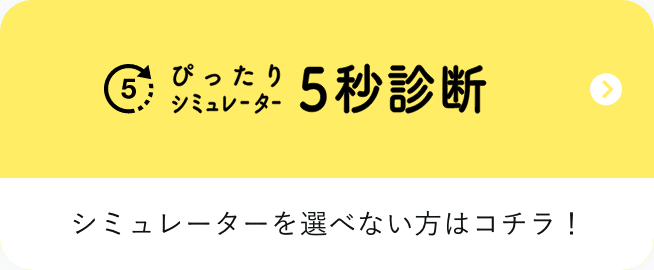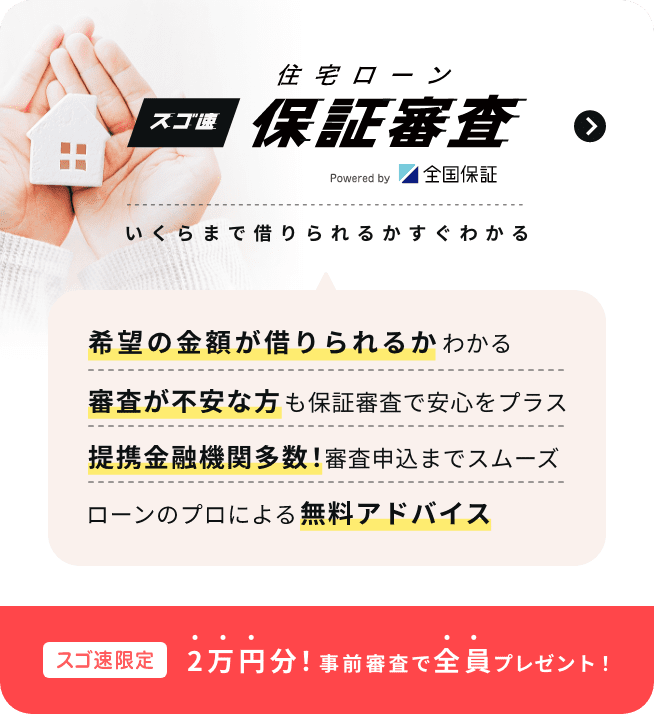賃貸物件で管理会社に支払う管理費とは?手数料の相場を紹介
賃貸物件の中には、賃料の他に管理費を支払わなければならないものがあります。この管理費は何に使われるお金で、何を基準に金額が決められているのでしょうか?また、賃貸物件の所有者にとっても物件の管理は大切なものです。賃貸管理を管理会社に委託する場合の手数料についても解説します。
01そもそも「管理費」は何のためのお金?
賃貸物件の管理費とは、マンションやアパートの共用部分の日常的な維持・管理に使われるお金で、主に次のような用途に使われています。共用部分の管理に直接かかる費用だけでなく、人件費や共用部分の保険料なども含まれます。
- エントランスやロビー、廊下や階段など共用部分の清掃費
- 管理人の人件費
- 共用部分の備品(電球や清掃用の洗剤など)の購入費
- エレベーターの保守管理費
- 共用部分の水道光熱費
- 建物敷地内の植栽の管理費
- 共用部分にかかる火災保険料や地震保険料
など
管理費の金額については法的に決められたものではなく、貸主が任意で決めることができ、相場は家賃の5~10%程度と言われています。1人のオーナーが建物ごと所有している小規模なアパートなどでは、管理費が全住戸一律の場合もありますが、一般的に管理費は各住戸の広さに応じて決められており、原則として広い住戸ほど高く設定されています。また、サービス体制や共用施設が充実しているグレードの高い物件は、人件費や施設の維持費がかかる分、同じ広さでも一般的な物件に比べて管理費が高くなります。借主にとって管理費は賃料とともに毎月支払わねばならない固定費であり、管理費が高い物件に住むと家計への負担が大きくなってしまうことに注意してください。なお、万が一、管理費を滞納すると賃料を滞納した場合と同様、賃貸契約違反で住み続けることができなくなってしまいます。契約時には賃料と管理費を合わせた額を毎月無理なく支払えるかどうか、慎重に判断するようにしてください。
なお、賃貸物件の中には「管理費無料」、「管理費込み」などと謳っているものもありますが、これは本来の賃料相当額に管理費を上乗せしたものを「賃料」として表示しているもので、結局は管理費を支払っていることになります。したがって、例えば管理費込みの賃料10万円を支払う場合と、賃料9万円・管理費1万円を支払う場合とでは、借り主の負担額は実質同額だということになります。ただし、賃貸契約を結ぶ際の敷金や契約更新時の更新料は「賃料の2か月分」のように、毎月の賃料をベースに決められるため、前者の方が借り主の負担額が大きくなってしまうことに注意が必要です。
02管理会社に管理を委託するメリット
物件の所有者の立場から、賃貸住宅の管理について見てみましょう。
アパートやマンションなど集合住宅の管理には、大きく分けて、所有者が自ら管理を行う「自主管理」と、管理会社に委託する「委託管理」の2つがあります。
自主管理の場合は管理会社への管理費用(手数料)が不要なので管理費を安く抑えられるメリットがありますが、その一方で専門知識がある人がいない場合は、問題が生じたときの対応が難しいことや、清掃やメンテナンスの技術が管理会社に委託する場合と比較すると見劣りする場合が多いこと、さらに住宅のトラブルは時を選ばず起こるため借主からの要望に24時間直接対応する必要があり大きな負担となります。また、家賃の滞納の催促や退去時の敷金精算などにも、所有者自らが直接対応しなければなりません。さらに所有者が自主管理を行う場合、遠方に居住しているケースでは迅速な対応が難しくなります。このように自主管理には多くの労力がかかるため、多くの賃貸住宅では、管理会社に管理を委託しているケースが多くなっています。
委託管理には、管理一切を丸ごと管理会社に委託する「全部委託」と、所有者がカバーできない部分のみを管理会社に委託する「一部委託」とがあります。いずれの場合も、委託する業務の内容は管理会社や契約内容によって異なりますが、一般的には主に以下のような業務を委託することができます。
- 入居者募集
- 契約の締結や更新
- 家賃の入金管理
- 家賃滞納者への督促
- 共用部分の日常的な維持・管理(清掃、備品の交換、ゴミ捨場の管理など)
- 住民からの相談やクレームへの対応
- 近隣地域への対応
など
一部委託は、これらの業務の一部は管理会社に任せ、そのほかは自主的に対応するものです。
委託管理は管理会社に手数料を支払わなければなりませんが、次のようなメリットがあります。
- 煩雑で手間暇のかかる管理業務から解放される
- プロならではのノウハウに基づいた適切な管理が受けられる
- 住民のトラブルや苦情に迅速に対応できる
03賃貸管理の手数料はどのくらい?
賃貸物件の管理を管理会社に委託するときの手数料は、「1部屋当たりの賃料×手数料率」で計算するのが一般的で、手数料率は5%程度が目安だといわれます。
ただし、業務範囲によって手数料は異なり、業務範囲を広く設定すると多くの場合手数料も高くなります。
業務範囲は管理会社ごとに独自に決められています。管理会社では標準的な「管理委託プラン」を用意しているところも多いのですが、そのプランの内容が必ずしもある物件にとって最適とは限らず、不要な業務までカバーされているケースも珍しくありません。不要な業務にまで手数料を支払うことのないよう、必要な業務をリストアップした上で複数の管理会社に見積もりを取り、納得できる管理会社と業務委託契約を結ぶようにしましょう。
ただし手数料を安く抑えたいばかりに、極端に清掃の頻度を減らしたり人件費を削ってしまったりするのも考えものです。手数料を削ると目先の負担は減るかもしれませんが、管理が不適切になってしまい、将来的に見ると資産価値の低下につながってしまうおそれがあるからです。過剰にコストをかける必要はありませんが、借主に安全かつ快適な住環境を提供し、資産価値を維持するのに十分なレベルの管理は維持するように心がけたいものです。また、残念ながらきちんと料金を支払っているのに実際には十分な管理が行われておらず、物件の状態が悪化し、借主からクレームが来てしまうケースも珍しくありません。できれば定期的に物件まで足を運び、適切な管理が行われているかどうかを確認することも大切です。
管理費は貸主・借主双方にとって、本来、決して無駄な経費ではなく、建物の資産価値を守り、快適で安全な住空間を維持するのに欠かせない経費です。信頼できる管理会社を選ぶとともに、定期的に管理内容や管理体制の見直しを行い、築年数や時代のニーズに応じた管理になっているかどうかを確認するようにしましょう。
管理費は、これまで見てきたように貸主が負担する管理コストを背景に設定されているものですが、前述した通り、明確な基準はありません。借主にとっては毎月支払う必要があるものなので、家賃と管理費を合算した金額で高いか安いかの判断をする必要があります。

監修:相山華子
ライター、OFFICE-Hai代表、2級ファイナンシャル・プランニング技能士
プロフィール
1997年慶應義塾大学卒業後、山口放送株式会社(NNN系列)に入社し、テレビ報道部記者として各地を取材。99 年、担当したシリーズ「自然の便り」で日本民間放送連盟賞(放送活動部門)受賞。同社退社後、2002 年から拠点を東京に移し、フリーランスのライターとして活動。各種ウェブメディア、企業広報誌などで主にインタビュー記事を担当するほか、外資系企業のための日本語コンテンツ監修も手掛ける。20代で不動産を購入したのを機に、FP(2級ファイナンシャル・プランニング技能士)の資格を取得。金融関係の記事の執筆も多い。
関連キーワード